- Home ユーラシアンオペラへの道
- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物
- 囁きはじめるユーラシアの風と歌
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
- ユーラシアンオペラ・用語集・索引
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
ペテルブルグ・モスクワ・グスリッツァ 2019

ロシア篇(ペテルブルグ・モスクワ・グスリッツァ)
1 全身音楽家 オレク・カラヴァイチュクのこと
2 ソ連時代の非合法アジト 「アートセンター」という場所
3 サインホとペレストロイカ
4 ウクライナ古謡の世界と熱狂「アウクツィオン」ライブ
5 アレクセイ・クルグロフと即興音楽のコンセプチュアルな世界
6 小さな美術館できいたカザフスタン大統領の辞任
7 フリーセッションの面白さ
8 禊(みそぎ) 大斎・マースレニッツァ・どんど焼き
9 森のなかのアートレジデンス
10 街の小さな博物館
11 ロシアの霊性1 舞踏と夢の歌
12 ロシアの霊性2 十字架と囚人の唄
13 バシコルトスタンのトランペット奏者、ユーリ・パルフェノフの眼
14 キャンディーズ in モスクワ
15 テングリ・ヴァージョン「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
1 全身音楽家 オレク・カラヴァイチュクのこと

3/15
2019年3月、カザフスタン(アルマティ)、タタールスタン(カザン)からと続く音楽詩劇研究所の「草原の道プロジェクト」ツアーはペテルブルグ、モスクワへと続く。ヨーロッパへの扉 、ペテルブルグに来たのは2008年以来だから、約10年ぶりだ。その前は2004年だった。両方とも3日ほどであったが、今回も同様に短い滞在だ。
アルマティやカザンと比べるとさらに北だ。寒いというよりは冷たい。東京でのユーラシアンオペラ公演から半年ぶりの再会となるウクライナの歌手アーニャ・チャイコフスカヤとのコンサートとそのためのリハーサルのみがこの地での予定だ。それらは彼女主導で行われるため少し肩の荷が下りて、「中休み」という気分で油断したのか鼻風邪をひいてしまった。
アルマティでの慌ただしい日々、カザンでの異文化同士が混ざり合う刺激なかで、このような古都の落ち着いた大きな都市での滞在はある意味休息の時だ。隙の時間を見つけては目的もなくひたすら街を歩いたものだが、現在のようにホテルの中でインターネットやWIFIの接続が容易になると、連絡ごとに縛られてしまう。ひさしぶりのこの街でも部屋の中に落ち着いてしまい、街について書けることが少ない。
だから帰国後に知った、ここペテルブルグの地にまつわるひとりの芸術家のことを書いてみようと思う。帰国後10日ほどたってから、今回のツアー、カザフスタン、ペテルブルグ、モスクワと一番時を長くしたペテルブルグ在住のダンスのアリーナ・ミハイロヴァから興奮気味なメッセージとともにある動画がSNSのメッセージに届いた。
いかにもアーチストらしい風体の老婆にも見紛う老いた男性と30代と覚しき男が、アパートの狭い部屋のダイニングキッチンで喋っているだけの長尺の動画だった。老人の声はしわがれているが変声期前の少年のようでもある。内容はロシア語なのでほとんどわからない。ミハイロヴァは、この老人がいっていることと、あなたが、これまでの共演で創作について話してくれたことは同じこと、だからそれを共有したい、と言った。
私が話していたことと同じとはどういうことか、と尋ねる間もなく、断片なのか、要約なのかわからないが、彼女がその場で英語に訳しながら、一行一行メッセージに送ってきた。
異教徒(もしくは無宗教)の音楽について
民族は形式ではない
それはルーツの一種
畏れ多いかもしれないが
それは天才とは違う
異教のなかにあるのは形式からの自由だ
しかしそれは同時に形式よりさらなる調和だ
次の動画が送られ、老アーチストがピアノを演奏する姿をみたとき、記憶が甦った。数年前ベルリンの大きなCDシヨップでのことだ。たしかモノクロだったと思うが、ジャケット写真に映る老人の姿がとても目をいたので思わずCDを手に取った。しかし中身がまるで想像できないので平積みに戻した。ミハイロヴァが英語でいうには、はじめのダイニングの動画は、彼女の友人(そこに映る30代くらいの男)が、その老人が亡くなって時を経て、ついさっき突然SNSに公開したものだそうだ。
その老人、作曲家のオレク・カラヴァイチュクは1927年にウクライナのキーウに生まれ、4歳の時にレニングラード(ペテルブルグ)に移住。7歳でピアノ演奏を披露し神童と謳われた。1960年代初頭にリサイタルを行ったが、そのときの演奏スタイルがスキャンダラスだったため、当局からコンサート活動を禁じられた。仰向けになったり、踊るように動いたり、声を出しながら弾く。無署名なものも多いが、映画のために無数の音楽を提供した。仕事の期日にとらわれず、トラブルも多かった。ロマン派風から現代音楽、ミニマリズム、ジャンルを意識するのではなく、インスピレーションのまま演奏し、録音した。ムスティスラフ・ロストロポーヴィッチとともにソ連を代表するチェロ奏者ダニイル・シャフランも彼の曲を演奏した。1960作曲家ドミトリー・ショスタコビッチもまた彼の天才を認めていたという。次のピアノリサイタルはようやく1984年になって行われた。ベートーベンとムソルグスキーなどをレパートリーに含んだ。
1990年以降、セルゲイ・パラジャーノフらの映画関係者や、天才音楽家として奇抜なパフォーマンスでペレストロイカ時代から前衛音楽をリードし早逝した伝説的な存在、セルゲイ・クリョーヒン、ロック歌手ヴィクトル・ツォイの未亡人マリーナなどの援助もありコンサートなども行われるようになった。現れなかったり、現れても弾かなかったりすることもあった。演奏に集中するために観客とのコンタクトを避け、枕カバーを頭にかぶって演奏した。ペテルブルグでは奇特な格好で街を徘徊する名物老人のように人々に知られた。経済的には困窮し、2016年89歳で亡くなった。
カラヴァイチュクの晩年の演奏スタイルは主に即興だ。弾き直さない、譜面には残さない。それは技芸や音楽理論をアドリブ表現に込めるジャズのようにではなく、インスピレーションを極度に重視した作曲だ。ショパンやモーツァルトの即興演奏に近いのかもしれない。大野一雄の即興舞踏を思い出した。氏の亡くなる数年前、一度横浜のご自宅、稽古場にお伺いしたことがあった。床に座してご飯を食べていたその姿がさえ踊りに見えた。カラヴァイチュクも大野も、観念的に即興を追求するのではなく、存在そのものが名付けようのない音楽や踊りだった。
「今度ペテルブルグに来る時、その友人の家を訪ねましょう。彼は、その老人の音楽を録音したものや楽譜、こうして撮りためていた映像をたくさんアーカイブしているから」と、自らの存在と表現を即興に託すダンサー、アリーナ・ミハイロヴァは言った。ぜひ訪ねたい。
2 ソ連時代の非合法アジト 「アートセンター」という場所

3/16
ウクライナの歌手アーニャ・チャイコフスカヤとのリハーサルのあと、数日後からモスクワとその近郊の村のアートレジデンスで共演するトゥバ共和国出身の歌手サインホ・ナムチラクから連絡があり急に会うことになった。現在の住まいであるウィーンから来る。自身の美術作品をギャラリーで受け取ってからモスクワに向かうので、夜行列車の出発時間まであいましょうとのこと。彼女も前2018年の東京と盛岡以来だから、半年ぶりの早い再会。もしかしたらそこで急遽演奏することになるかも、とのことでコントラバスを携え待ち合わせ場所に向かう。
「プーシキンスカヤ10」という名のアートセンターに到着して気づいた。そこは、私が初めてペテルブルグに、すなわち初めてロシアで演奏した2004年、在籍していた即興音楽のグループ、Exias-Jで演奏した会場と同じ場所だった。
ソ連時代の非合法アジトだった場所とのことで、妙に入り組んだ構造のアパートで中で迷ってしまったのを思い出す。その時は1960年代より日本のフリージャズの第一人者であるドラムの豊住芳三郎、ジャズ批評家、プロデューサーの故副島輝人氏も一緒だった。カフェバーやギャラリー、本屋、穴蔵のようなライブスペースが入った怪しい総合アートスペースだった。副島氏に連れられるままに名前も知らぬこの場所で演奏した記憶が甦った。地下カルチャーの匂いが満載だった。
その後に訪れた鉄道に乗って一日かけて行った北の涯アルハンゲリスクはなおさらだったが、当時はペテルブルグにせよ、モスクワにせよ、イメージとしての「ソ連」がまだ色濃く残っているような印象だった。このような場所は創設者、関係者やアーチストたちの強い思い入れによって発足し、それを存続させることは難しい。そのような場所の栄枯盛衰には、日本でもみたり関わったりもしてきたが、残念ながら長く続かずになくなってしまうことも多かった。このアートセンターが15年ほどたったいまなお残り、それなりに賑わっていたのは驚きだった。
チャイコフスカヤとのリハーサルが長びいて、盛岡から半年ぶりとなるサインホを少し待たせたが、笑みを浮かべて待ってくれていて安心した。彼女が洞窟のように入り組んだ館内をめぐり案内してくれ、地下のカフェバーでビールを飲みながら、明後日のモスクワでのコンサートの打ち合せをした。初共演になるロシアの新世代のジャズシーンを代表するサックスのアレクセイ・クルグロフ、シャーマンであるという謎の人物ヴィエラ・サージナ、サインホ、私、舞踏の亞弥が「ZenTrane」という企画でパフォーマンスを行う。サインホによって綿密にプログラムが決められており、彼女のコンサートに対するヴィジョンを知る。私はそれをそのまま受け入れ、構成を委ねることにした。
ここでの予定外の共演はなしくずしになくなったが、数日後の再会を確かめあって、大きな荷物をたずさえ夜行列車でモスクワへと発った。2mほどの二本の長い筒は美術家でもある彼女の作品だ。大きな荷物を飛行機に載せるにはとても費用がかかるという事情もあるが、ロシアの人々は長い列車移動に慣れているのだろうか。セルゲイ・レートフも14日のカザンの公演後に翌日のコンサートのためわれわれより早く列車でモスクワに向かった。11時間かかるが、寝てればよいのだから、飛行機での荷物運搬に関する煩雑さを考えるとこちらのほうがよいと仰っていた。二人とも60歳を越えた高名な音楽家であるが、やはり旅や移動に関して小さな島国のわれわれとは異なる感覚なのだろうか。
3 サインホとペレストロイカ

私は長い間ロシアを離れているからなかなか難しいだろう、との返事をサインホからもらっていた。このカザフスタン、タタール、ロシアと続くツアーに発つ数ヶ月前に、ツアーでモスクワに行くので、もしもその頃モスクワ近辺にいればぜひなにか一緒にやりたい、あるいは場所やコラボレーションの相手を紹介してほしいと伝えた。しかしその後しばらくして何か考えが思いついたのか、モスクワとその近郊の村グスリッツァのアートレジデンスのフェスティバルでのパフォーマンスを画策し、再共演の計画をすすめてくれた。
2017年にシベリアのイルクーツクで出会い(第四章)、翌2018年に、東京と盛岡(第五章、第六章)でコラボレーションを行った、トゥバ共和国出身のサインホ・ナムチラクは2000年頃にすでにヨーロッパへと移住している。
トゥバのシャマニズムやトゥバ語が彼女のアートや生き方のベースにあるというが、昨年盛岡で彼女自身は「私はほんとうのシャーマンではない」と言っていた。1957年に現在のロシア連邦トゥバ共和国の山村で産まれた彼女は、もちろんロシア語がネイティブ言語であり、トゥバ語(テュルク系の言語でありロシア語とは全く異なる)も話すことができる。
両親はトゥバ人で、父は詩人、ジャーナリストであり、母は教育者だった。幼少から祖母に歌を教わった。本来トゥバの女性は歌わないというシャーマニズムの文化、民謡だ。卒業後いくばくかの間勤めた繊維工場をやめ、首都クズルの音楽学校で合唱を学び、ロシア民謡も歌った。
その間、後に結婚し、娘を産み、離婚することになるプロデューサーの男性やその仲間たちから、禁じられた西側のラジオでロックなどを聴かされた。ピンクフロイド、レッドツェッペリン...民謡やソビエトの歌謡曲とも異なる世界に、恐怖を感じつつ惹かれていったそうだ。その後モスクワの音楽大学でトゥバやシベリア少数民族の音楽を研究。国立伝統芸能団の歌手としてソ連時代にデビューし世界各地で公演した。トゥバの民謡だけでなく、極東のアムール川流域の狩猟民族のナナイ族の歌、フィンランド近くのコラ半島のサーミ族の「ヨイク」という歌唱法で知られる歌など、ロシアのほかの少数民族の歌も歌った。
その後、ペレストロイカ期に勃興したアヴァンギャルド音楽の寵児となり、即興歌唱を始める。当時より彼女と共演を重ね、関係も深かったセルゲイ・レートフによれば、意外なことに、西洋のバロック音楽などもひじょうに美しく歌う歌手でもあったといい、それを聴いたことがあるそうだ。本名はロシア名で「リュドミーラ(リューダ)」というが、改名をすすめたのも自分だ、と教えてくれた。クズルに暮らしていた元ダンサーの女性の名前の響きが気に入っていて、そこからファーストネームを拝借したそうだ。
やがてヨーロッパへと活動の場が広がり、2度目の結婚を機に移住し、娘を連れウィーンに暮らすようになった。世界的にも知られるアーチストとなったが、鈍器で後頭部を襲われるという事件もあった。それ以来彼女の表現は変わってしまった、という噂も聴いたが定かではない。二重国籍が許可されないためオーストリア国籍のみをもつ。
ヨーロッパでつねに異邦人として、少数民族「トゥバ出身のアーチスト」として生きてきた彼女にとって、祖国であるロシアとはどういう場所なのだろう。昨年、東京で混乱していた彼女は、盛岡ではじめてその素顔の一端を垣間見せてくれた。モスクワはこの世界的なアーチストが自らの表現を確立した地だ。数日後から始まる次なるコラボレーションへの期待が高まる。
4 ウクライナ古謡の世界と熱狂「アウクツィオン」ライブ

3/17
アーニャ・チャイコフスカヤとの公演会場に、ホテルのある通りから市バスで向かう。チャイコフスカヤとは、このツアーではペテルブルグとモスクワでの二公演を含めて三公演を行う。2016年モスクワで出会って(第二章)から、けっきょく4年間毎年共演することになった。
今回は、ウクライナ出身の彼女が、自らの創作スタイルを築いたのがペテルブクだ。これまでと異なり、私のプロジェクトで彼女が歌うのではなく、基本的に彼女主体で行われる。じっくりと彼女の表現に向き合う機会でもある。これは次の創作にむけ大きな情報源にもなる。海外アーチストに限ったことではなく、共同作業をする相手とはそのような相互関係を築きながら創作することが私の理想だ。
民謡や古謡が「伝統芸能」になる前の歌を想像する。古の歌たちが、「未来」を映す風景になる。チャイコフスカヤがコントラバスのヴラジーミル・ヴォルコフとトランペットのヴァチェスラフ・ガイボロンスキーの両巨匠をたずさえたトリオによるウクライナ古謡のCD「青い湖」発売を記念する公演に、私のコントラバスとダンスの亞弥とアリーナ・ミハイロヴァが加わる。今回は諸事情により残念ながら、以前モスクワで共演した巨匠ヴァチェスラフ・ガイボロンスキーが加わらず、代わりに73歳、セルゲイ・レートフとのTRI-Oにも参加していたユーリ・パルフェノフが参加。
これは私がめざす「夢の歌」への入り口だ。それぞれの曲は即興で演奏される。民謡を譜面の状態からプリミティブな状態に戻してゆく。民謡なので、メロディーは繰り返しが多い。詩の情景もシンプルだが、物語的に展開するバラッドの形式も多い。チャイコフスカヤはそのくり返しをとても自由に引き延ばしたり、演劇的な所作をいれたりしながら歌う。
こうして歌を軸に音楽は自在に展開するが、これは彼らの即興の積み重ねによる「作品」でもある。リハーサルをしてみると、かなり暗黙の了解を含め決まっているタイミングやフレーズが多いことが分かる。こちらも詞の大意だけでくみとって即興の感性に頼るだけでは、深いコラボレーションにはならないと思った。机のないホテルの部屋でベッドに横たわりながら朝までかかりロシア語翻訳から重訳し、本番では、ウクライナ語、ロシア語、日本語を譜面台に並べてそれを見ながら演奏することにした。
両言語はもちろん類似も多いが、ウクライナ語話者はロシア語を理解するが、反対は難しいそうだ。チャイコフスカヤは、ロシアのお客さんが歌を聴いて、ウクライナ語を理解できないことを前提に、歌詞カードに両言語を記載して配布した。
詩の内容はたとえばこのようなものだ。
「ボーギ」より
妹よ、行きましょう、暗い森の中へ、
獣たちが僕たちを食べてしまうよ
森は答える「きちゃだめです」、獣たちはいいます「食べませんよ」
妹よ川の方に行きましょう、永遠に溺れて行きましょう
水は答える「洗い流しましょう」地は答える「受け入れません」
おいで、妹よ、野をわたり草をわけて
おまえは咲き乱れる白い花、僕は青い花
おまえは白で僕は青、世界の栄光へと導かれん
世界の栄光へ、そして二人は同じ色に染まる
「青い湖」
青い湖が広がる
王様は兵を集め戦争に行き
王様は城に帰ってきた
妻と産まれたばかりの子供がいるから
息子は産まれたばかりで自分ひとりで生きられない
王様が息子のところに戻ってきた
息子は育ち戦に行くだろう
王様の光りが消えてゆく
青い湖が広がる
王様は兵を集め戦争に行き
王様は城に帰ってきた
妻と産まれたばかりの子供がいるから
娘は産まれたばかりで自分ひとりで生きられない
娘は育ちやがてお嫁に行くだろう
王様の光りが消えてゆく

会場は日本で言えば、ブルーノート東京や、横浜のモーションブルーといった洒落た感じのクラブだった。ロシアの劇場音楽の発祥の地としてすでに1730年代から上演され続けているマリンスキー劇場のそば、ネヴァ川の運河沿いの映画スタジオでレストランやホールを兼ね備えた「レンドク」だ。
私と同じコントラバス奏者のウラジーミル・ヴォルコフは、2010年にモスクワでダンスのアリーナ・ミハイロヴァとのトリオで初共演させていただいた。サンクトペテルブルグ在住で、ロシアNo,1のベーシストといわれる。ジャンルの境界を越えるその活動は、ジャズ, 前衛、即興、現代音楽、バロック(ヨーロッパの古楽器ヴィオラ・ダ・ガンバも弾く)、ロック、民族音楽。その多岐にわたる活動から、近年は「ヴォルコフ・フェスティバル」がここペテルブルクの、ここ「レンドク」やモスクワの「ドム」で数日間に渡り開催されている。そのままロシアのコンテンポラリー音楽のシーンの多様性を象徴するようなラインアップだ。
自分も彼のように演奏に専念し、もっと上手に弾けるのなら、このような活動を目指していたかもしれない。音楽的指向も共通性することが多く、演奏スタイルや発想もかぶる。だからリハーサルでは同じような箇所で同じような音を演奏しようとすることが多く、二台の同じ楽器で即興的にアンサンブルさせることは、かえって難しかった。
ヴォルコフとパルフェノフが、われわれのコンサートを終えた後で、さらに移動して出演する、アウクツィオン(Auktyon)のコンサートに招待してくれた。私たちのコンサートは100人ほどのお客さんであったが、こちらは大きな「クラブ」で、超満員の1000人ほどのお客さん。バンドは1978年、レニングラード工科大学でヴォーカル兼ギターのレオニード・フョードロフとパフォーマー、詩人のオレグ・ガルクーシャによってつくられた。ポストパンクロック、のスタイルで演奏し、ペレストロイカ期より西側にも「知られざるソビエト、ロシアのニューウェーブ」を代表する存在として紹介された。ヨーロッパと中央アジアの民俗音楽、アバンギャルドジャズの要素を加えた伝説のオルタナティブロックバンドだ。グループの活動は現在まで継続し近年はアメリカの実験音楽、ジャズ、トム・ウェイツのバンド、キューバ音楽など越境的な活動で知られるギタリスト、マーク・リボーや、ニューヨークのダウンタウン即興要素の濃いジャムバンド、メデスキ、マーティン・アンド・ウッドのキーボード奏者ジョン・メデスキーを加えたプロジェクトとしての活動も行っている。
2004年にExias-Jのツアーでリトアニアの首都ヴィリニュスのジャズフェスティバルに出演するために行ったとき、街の小さなCDショップで、店主に自分のCDを買い取ってもらう代わりにお薦めのCDをもらって聴いたのが「アウクツィオン」との出会いだった。フレーブニコフの創造言語「ザウミ」の詩につけた曲も歌われた。ヴォルコフと初共演した10年前、モスクワで観に行こうとしたが、チケット完売で観られなかった。夢がかなった。次なる夢は共演だ。短いペテルブルグ滞在を終え、翌朝、モスクワへ飛行機で移動。
5アレクセイ・クルグロフと即興音楽のコンセプチュアルな世界

3/18
もう5度目になるモスクワは、過去に少し長い滞在もしたことがあり安心感がある。今回は、移動や連絡のとりやすさを重視し、チャイコフスカヤの暮らすアパートに近い、キタイゴーラド(中国街と訳せるが、現在その面影はなく、東京で言えば有楽町あたりのイメージ)という「赤の広場」からも遠くない中心地のホステルに滞在した。それゆえに宿代は安さ(一泊1500円くらい)を優先し、宿泊の環境はよいとはいえない。アパートの5階まで、カザフスタンから3週間分の衣裳や機材を含む大きな荷物を三人で手分けして運び、二段ベッドのある部屋に荷物もろとも転がり込んで、まさに旅芸人さながらだ。トイレもシャワーも共同。眠りに帰るだけの場所。贅沢は言えないが、正直もう少しゆっくりできる場所に滞在するような予算的な余裕がほしい。
禅とジョン・コルトレーン、まさにスピリチュアル感満載である。安ホステルから徒歩2分。われわれの滞在環境とは対照的な高級ジャズクラブのような場所で、毎週月曜日は「Zen Trane」という企画が行われており、アヴァンギャルドな音楽が楽しめるというわけである。そんな雑誌をもっていたことも忘れていたのだが、むかし古本屋で買った1966年の「Jazz批評」のコルトレーンの特集号を、主催者にお土産でもってゆくことを約束していた。 コルトレーンが来日してフリージャズを演奏した年で、ビートルズ公演の直後のことだ。



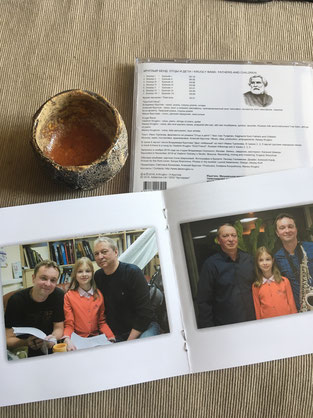
このコンサートも、サインホ・ナムチラクとすでにペテルブルグで打ち合せ済みだったので、きょうも演奏家としてじっくり演奏できた。音響も良い。
ロシアのジャズ新世代を牽引するるアレクセイ・クルグロフとも初共演。彼の活動領域もひじょうに多岐に渡り、ドイツのピアニストのヨアヒム・キューンら、他国の第一人者からも共演を求められ、演奏技術も一聴して最高峰とわかるききしにまさる、しなやかな美音だった。クルグロフはLEOレコーズというレーベルのフェスティバルのティレクションもまかされているとのこと。
イギリスの亡命ロシア人のレオ・フェイゲンが主宰するLEOレコーズは、ペレストロイカ期からロシアのアヴァンギャルド音楽を発表し、私も大学生や20代の頃からずいぶん、それらのCDを聴いた。これまで共演させていただいたロシアやリトアニアなどのアーチストの作品もほとんどそこから発表されている。ロシアの即興、ジャズアヴァンギャルド音楽の民俗文化への指向と演劇性は、ヨーロッパの同様のレーベルと比べて際立った特徴だった。現在のように動画が見られることはまずなかった頃だったが、音や写真からそれを想像することは難しいことではなかった。
アメリカ、ヨーロッパで始まったそのようなアヴァンギャルドな即興音楽シーンの潮流を、現在に至る動向を加味しながら国別に大雑把に比較すると、それぞれこのような特徴があった。
フランス・スイス:政治的なコンテクストとレジスタンスの伝統。その重要なカウンターカルチャーとしてローカルなフォークロアへの接近。
ドイツ・スイス:彫刻的な運動性を持つエネルギー。スコアミュージックと即興を対置、混在させながら展開。ナチズムへの反省によるのか、民族回帰的なフォークロアへの志向は少なく、コンセプチャルでパフォーマティブな現代アートとの親和性が高い。
オランダ:演劇的な批評性(たとえば西側からみた東ドイツのブレヒト)とカーニヴァル性が両立するなパフォーマティブな音楽。
イギリス:政治性も背景にしたコミュニティの模索、およびそれを実践するアンサンブル。アイロニカルな遊戯性。
スペイン、イタリア:伝統音楽も含むラテン的な歌謡性、フェリーニの映画にも通底する魔術的なカーニヴァル性。
東欧中欧:音響性やコンセプトのストイックな追求。
アメリカ:まさに多様だが、政治性も強い。またアフリカのユダヤなどのルーツのフォークロアや信仰への回帰や再解釈。ジャンルの融合と越境。
日本:土着的情念ともいえる演奏や身体性。その反動としての即物的な音響、サウンドアート志向。
オーストリア:90年代後半より、日本の「音響派」との交流などを通じ、即物的、ミニママムな音響性。
中国、香港、台湾:カウンターカルチャーとしてのノイズ音楽、電子音楽志向。
韓国:欧米や日本のレーベルより姜泰煥や金大煥などの独自の活動が紹介されたが、韓国のレーベルとして体型的に日本で紹介されることはなかった。
アルゼンチン:一時「アルゼンチン音響派」として、浮遊感をともなうエレクトニカサウンドがしばしば紹介された時期があった。伝統音楽の豊かなリズムを音楽に対する反動だろうか。
インターネット文化が隆盛する2000年頃以前までの私は、中古CDを買ったり、雑誌などで情報を追い求めたりして、そのようなシーンを熱心に追っていた。いずれにしても各国のレコード、CDレーベルにこんな傾向がそれぞれあったように思われる。現在はレーベルや国によるこのような特徴的な差異は少なくなっているようだ。
日本に戻ったあと自宅でアレクセイ・クルグロフがプレゼントしてくれた3枚の彼自身のCDを聞いた。とくに彼の父親とまだ10歳くらいの娘によるファミリーアルバムは久しぶりに傑作と思える内容だった。イワン・ツルゲーネフの小説「父と子」もとに朗読、歌と演奏が交錯する物語的な構成。ロシアのアヴァンギャルド音楽のエッセンスがつまったような楽しいアルバム。そのフォークロアのカーニヴァル性や演劇性はアレクセイ・クルグロフのような新世代の音楽家にも受け継がれていた。

彼は翌2020年1月に初来日した。新潟と東京で講演やコンサートを行い、再会することができた。ジャズピアニストの巨匠佐藤允彦や、ヴァイオリンの太田惠資などさまざまなミュージシャンと即興演奏を行った。招聘者の鈴木正美氏と私は、他のコンサートにない彼の作曲家、詩人、俳優でもあるという側面も紹介したいと思った。
クルグロフ作曲のウラジーミル・マヤコフスキーの「僕は愛する」の日本初演をDUOでおこなった。ほかにも彼の、彼自身の「回文」詩(パリンドローム)、ウラジーミル・ヴィソツキーのいくつかの詩の朗読とサックス演奏とDUOで即興演奏をした。革命にたいする情熱と諦めとの矛盾を30数年の生に凝縮してしまったような未来派詩人マヤコフスキーの「愛」に関する詩11篇からなる「僕は愛する」の最後をクルグロフが叫ぶと、デモのプラカードをイメージして観客に配布した布が、客席中でかかげられ、観客もロシア語や日本語で口にする。最後に口にしたのは「Люблю(リュブリュー ぼくは愛する)」。
2021年、この共演も含む彼の日本ツアーの、ドキュメントとなる三枚組のCDがロシアから発表された。
本日の共演者、サインホ・ナムチラクも詩集を出版する詩人でもあるし、クルグロフも詩人だ。私が知る中ではロシアほど詩が大事にされつづけている国はないと思う。音楽のなかでも同様だ。こんな話しを韓国にルーツをもつ日本の著述家の友人、金村詩恩に話したところ、韓国もそれは同様で、対して日本ほど詩がおろそかにされている国は、珍しいのではないかとのことだった。活動の拠点として、旧ソ連圏を含むロシアや、韓国が多くなったのはそのせいかもしれない。
6 小さな美術館できいたカザフスタン大統領の辞任

3/19
今回のカザフスタンでの「さんしょうだゆう」と、タタールスタンとロシアでのコラボレーションによるツアーを助成してくださっている国際交流基金のモスクワ支局から、助成事業実施状況のヒアリングの機会も兼ねて、昼食会への招待を受ける。中心地の高級レストランだった。局長は前歴が、ウズベキスタンでの勤務だったそうだ。私はアルマティでの、カザフ民族の民族主義や、言語のこと(ロシア語とカザフ語)などの印象を話した。
局長のお話によると、ウズベキスタンもカザフスタンも国際関係、主にロシア、アメリカ、中国とのバランスにより、言語に関する政策もその都度変わる。たとえば、カザフ語は先日、公式文書の表記のキリル文字からローマ字への移行が決定された。しかし定着化がどのように進むのか、先は読めないそうだ。ウズベキスタンはソ連崩壊後5年ほどで、そのように移行したが、カザフスタンはロシアとの関係が強固なのでより困難なようだ。
お話を伺いながら酒のないランチを終え、夕方に本日の会場である郊外の美術ギャラリーに到着。このツアーでカザフスタン、カザンと続けて共演したセルゲイ・レートフと4日ぶりの再会。本日は、レートフ、亞弥、私のトリオ。本ツアー中もっともミニマムな編成だ。
数日はインターネット規制や航空便の混乱があるかもしれない 、会うなりにカザフスタン出身のレートフが言った。計画的な禅譲であるらしいが 、ソ連崩壊後から現在に至るまで30年以上大統領の座に座っていた、カザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフが突然辞任したという。数日前に滞在していたアルマティでは、創作に没頭し、そのような予兆などもまったく聞くこともなかった。

中心街からやや離れ、人通りも多くない場所にあった美術館は、外も内もひっそりとした佇まいだ。アーシャ・マラクリナという若い女性作家の作品が展示されていた。孤独と政治的抑圧からの解放がテーマの作品群。寡黙だがメッセージの強い作品だ。もう閉廊時間は過ぎているのだろうか、スタッフ以外誰もおらず、しずまりかえっている。
楽屋としてあてがわれた部屋を覗くと、電気を消したまま隅っこで、舞踏の亞弥がステージの衣装を準備していた。これから小さなステージに出て、身体を収縮しながら踊る小さな舞踏家は、空間の陰影に溶け込んでいるみたいだった。
大都市郊外にあるこの美術ギャラリーにお客さんが少しずつ集まりはじめたが、レートフがいっていたとおりお客さんの数は少なそうだ。さきのカザフスタンのアルマティでの大人数での創作(第三部)、カザンでのコンセプトを共有したダンサーとのコラボレーションとセルゲイ・レートフと続けて時間を過ごしてきた。しかし今日は何も決め事をせず、わずかばかりの野生と知性をあらんかぎり開放させ、思う存分インプロヴィゼーションして濃密な時を過ごそう。
開演間近だったが、まだぽつぽつと人が会場に集ってくるのを確認しつつ、気付のための酒を買いに行く。いつもなら缶ビールだが、寒いのでなんとなく安いコニャックの小瓶を買う。夕闇の中、溶け出した雪にぬかるむ省線電車のレールの上を、滑らないように少し気をつけながら会場に戻る。今日、明日と、連続してこの会場でコンサートを行うことになるのだが、今訪れているこの場所にまた来ることはあるだろうか、小走りしながらふと思う。まだ小動物のように闇に佇んで衣裳の準備している亞弥にコニャックの残りを渡たし、先に小さなステージに向かう。
一時間ほど休憩なしで演奏。アルマティ、カザンでは演奏後に毎夜のように食事を共にし、同じ宿に帰ったレートフは、当たり前のように家族の待つ家に帰る。なお彼は60代半ばであるが若い奥様との間に幼子をもうけている。10月の韓国での「さんしょうだゆう」公演での再会を誓って別れる。
7 フリーセッションの面白さ

3/20
昨日と同じ小さな美術館で、ダンサーのアナスタシア・シュレヴァコヴァが主催する、ダンサーやミュージシャン、俳優などが集る即興のセッションにゲスト出演。当初、モスクワでの公演数はこれほど多くは予定していなかったのだが、近郊のグスリッツァを含め5つの異なる演目を行うことになった。
ダンスのシュレヴァコヴァは2016年のモスクワ公演(第二章)のとき、知り合いではなかったがSNSづてに急遽連絡をくれた。日本の舞踏に興味があるとのことで、われわれの上演の後に短いセッションをできないか、との申し出があった。その後現在まで共演が続くアーニャ・チャイコフスカヤとの初共演とななる公演後にその時間を設けた。初共演の彼女とのパフォーマンスがどうなるか、まだその時には予測がつかなかった、いずれにしても本編のなかでおこる私たちの出会いを観客のなかに残したいとの思いがあった。だからシュレヴァコヴァからの申し出を受け入れたものの、どのようなタイミングで行うか逡巡した。観客が帰った後のプライベートセッションもありかもしれない...
実際その日のチャイコフスカヤとのパフォーマンスは、その後の音楽詩劇研究所の作品の重要なモチーフになる、三木聖香と彼女が同時に別々の子守唄を囁きあうというラストシーンも生まれ、充実したものだった。私はやはり、そこで生まれた静謐な歌の交換で締めくくりたかった。だから終演後しっかり間を設けて、その後にと思った。
しかし会場「ドム」の芸術監督のリュドミーラ・ドミトリエヴァの挨拶の後、なしくずし的にセッションが始まってしまった。出演者全員が参加する即興パフォーマンスは想像した通りにややカオス。そのなかでもしなやかに演奏する巨匠トランペットのヴァチェスラフ・ガイボロンスキーとギターの小沢あきに演奏を任せ、演奏を止めて、薄目を開けて、なるべく肯定的にこの場を受け入れようと舞台の上から眺めていた。
そんな経緯もあったが、今回の私たちのモスクワ行きを知ったシュレヴァコヴァは、再び共演の場を望んでくれた。このあとのモスクワ近郊のグスリッツァというアートスペースでのワークショップも彼女がオーガナイズした。
この日は演奏家やダンサーが入れ替わり立ち替わり、名前も覚えきれぬまま約1時間半のセッション。同じ会場だが、共演を重ねてきた昨日のセルゲイ・レートとのまるでツアーでのコラボレーョンの集大成であるかのような濃密な演奏とは異なる。ダンサーだけではなく演奏家も現れた。ピアニスト、ヴオーカリスト、トランペット奏者がこの自由なコミュニケーションであるインプロヴィゼーションの場を求めて参加した。ひたすら即興のセッションが続く。
先の読めないこと、あるていど流れが予測できてきたところでまた違った状況にでくわすこともまさに「塞翁が馬」、人生とおなじだ。ならばこの時間のなかに生を凝縮して濃密に過ごす。共有するテーマもなく焦点が定まらないセッションではあるが、気負わずに、互いの音と動きだけを頼りにギリギリのコミュニケーションを続け、瞬間の出来事を共有しながら新しくうまれてゆくものを互いに感じる。考えてみれば貴重なことだ。会話も、まして外国語も苦手な自分が、初めて出会った見知らぬ人とこれだけの時間を濃密にともにできる。有り難い時空。そのような表現をどのように観客とも共有できるか。これまでの、そしておそらくこれからも私の音楽人生の大きなテーマである。
8 禊(みそぎ) 大斎・マースレニッツァ・どんど焼き

3/21
この日はアーニャ・チャイコフスカヤとの新しいプロジェクトの本番。会場の大きな窓の外からは教会と散歩道がみえる。今回の彼女との共演は、ウクライナ古謡を二人の即興演奏の巨匠とともに自由に解釈した彼女のCD作品の発売記念コンサートでもあり、内容もそれに準ずる。しかし本日に限りこから離れ、メンバーやレパートリーもかえて、私とのコラボレーションとして新しいテーマを試みた。渡航前のメッセージのやり取りは主に今日のコンサートのためのものだった。
前年の東京でのユーラシアンオペラ公演の中では、伝統的なウクライナの子守唄、嘆き歌(子捨て歌)とロシア正教の聖歌、それから私のオリジナル曲の旋律を歌ってもらった。ウクライナ民謡と、彼女が敬虔に信仰する正教との間にどんな関係があるのかが興味深かった。

今回まずはじめに彼女が今日のコンサートのテーマとして提案してきたのが、キリスト復活祭前の「大斎(Great Lento)」だ。正教の長期にわたる食生活などの禊(みそぎ)の期間を意味する。ちょうどこの時期、2月~3月に当たる。それについて尋ねながら、こちらも調べて日本のさまざまな祭などの慣習や、神道や仏教における禊の感覚や所作、儀式を、インターネット動画も使って紹介した。現在に至るまでの日本の宗教史の概略を説明し、私はとくに民衆の宗教受容と音楽性との関連からテーマを探った。
日本では民衆の信仰は古来のアニミズム的神道に加え、江戸時代には世俗化しながら仏教が定着した。仏教「芸術」は仏教画や仏像があっても、歌舞音曲の流動性や即興性はストイックな教義とは相性が悪い。それでも歌は民衆に対して布教的に用いられた。5・7調に乗せて歌われる巡礼歌は、江戸時代や和讃は江戸時代に「ご詠歌」となって親しまれた。山岳信仰や慣習と結びついたな歌などもあらわれる。古く神楽などに伝えられた外部からの来訪者である「まれびと」や放浪芸人の諸芸、日常の労働歌や童歌もまじり、仏教行事と結びつきながら時節の祭りや行事が形成されていったのだろう。一般的にアニミズム信仰には布教という概念はない。布教における宗教の世俗化による民衆の芸能への影響は、とくに三大宗教が根付いた土地には顕著だ。
正教の合唱などによる祈祷は、やがて音楽化したが本来はオルガンなど楽器を伴わない。芸能や芸術とは別の神聖なものだと彼女もいう。そのようにに戒律の厳しさがあらわれる音楽的儀礼として、日本の仏教では、法具を用いた大人数の僧による読経の声明がある。そもそも一般信者が経文を理解し唱和することはそもそも困難であり、聖職者がそれを行う。昨今は声明の音楽性や儀式性が再編され、音楽公演として声明が行われる機会も多い。
チャイコフスカヤには、宮内康乃の東日本大震災での被災者の鎮魂として作られた新作聲明「海霧讃歎(うみぎりさんだん)」の動画もみてもらった。作曲家の宮内氏は帰国後に東京で音楽詩劇研究所が主催して行う、フェスティバル「東方声聞録」(2019年6月)に出演していただくグループ「つむぎね」の主宰者だ。このフェスティバルには「つむぎね」の他に、鼓奏者で演出家の今井尋也が主催する「シルクロード能楽会」とわれわれ音楽詩劇研究所の三団体が声をテーマに交流する。声のアンサンブルをテーマに創作してきた宮内の声明作品は、本来はありえない、異なる宗派の唱法のミックスだ。天台宗と真言宗が、それぞれ舞台と客席側に分かれて歌われる。楽譜をみせてもらったが、その記譜法も宗派によって大きく異なるのが興味深く、チャイコフスカヤも強く関心を示していた。
彼女から「大斎」というテーマが与えられたのに先立って、トゥバのサインホ・ナムチラクからも、本日のコンサートの後移動する、モスクワから車で2時間ほどのグスリッツァで公演のためにいくつかのキーワードが提示されていた。やはりすべて宗教や信仰に関わるものだった。インドのヒンドゥー教のクンブ・メーラという聖なる川での淋浴の巡礼の宗教行事、チベット仏教の法具、広くロシアで行われているマースレニッツァ。彼女は出身地のトゥバの古来のシャーマニズムを創作と人生の基盤にしているが、その地ではチベット仏教、イスラム教、ロシア正教が共存して信仰されている。彼女は自らの身体の中に多様な宗教的感覚を吸収しているのだろう。
チャイコフスカヤが提案してきた大斎前に、ロシア周辺各地域でおこなわれるのが、サインホが言及したスラブの祭マースレニッツァだ。乳製品や肉食を禁じる正教の大斎の前に行う春祭だ。ソ連時代にも家庭内の習慣などとして存続した。現在はさらに大きな規模で各地で行われている。バターをあらわすマースラが名前に由来し、祭りを象徴する、薄力粉を使ったクレープ、ブリヌィの丸い形は、太陽を意味する。
大きな人形をつくりそれを燃やして豊穣を願う、火祭り的な要素も持つち、精霊を祀り、呑めや歌えの大騒ぎになる。日本の「どんど焼き」の習慣にも似ている。調べているうちに韓国でも近しい慣習があり、日本各地の田畑や神社で行われるそれらよりも、藁人形も大きく盛大だ。こうした火祭りは、特に冬が長く厳しい農耕文化には共通する予祝行事といえるのかもしれない。どこかの慣習が各地に伝搬したというよりも、自然発生的に各地で発生したようにも思う。
「大斎」の起源もこのスラブの土着信仰にあるといわれるが、日本のロシア正教関連の資料をみると、マースレニッツァについては、大斎から派生し土着文化と結びついた習慣であり、本来はキリスト教とは関係のないものだとの説明も多く見られた。
サインホやチャイコフスカヤの表現行為や創作は、信仰や祭儀の慣習と結びついている。私にはそのような感覚がない。コラボレーションにおいて、難しいのは、彼女たちの信仰に対峙する私自身の宗教的体験がほとんどないということだ。調べて紹介した日本の宗教的な慣習や儀式にも親しんでいるわけでも、詳しいわけでもない。だからたとえば「禊」や浄、不浄の感覚の無意識に日常的に習慣的に行っているさまざまな所作を遡ったり、演奏など音楽的行為の宗教的起源とのむすびつきを探したりするほか、リアリティの持ちようがないのだ。また、外から見れば、私の演奏、生活様式などにも、日本の古来のアミニズムや神道、仏教の痕跡が現れているのかもしれない。
前年のユーラシアンオペラ「Continental Isolation」では、参加するアーチストのシャーマニズムも含むさまざまな信仰や宗教を、現代の生と対峙させ、そこで生まれる音楽や踊りを「神なき時代の「神謡集」」と称した。「神がいない」のに神謡集が成立するという逆説的な意味もある。しかしこうしてて一人の人間が信仰する、ある宗教に向き合ってみると、そもそも見ている世界の景色が根本的に異なるのかもしれない、とも思う。私自身はたしかに「神なき」感覚の中に生きているが、それはけして当たり前のことではない。「時代」という言葉をつかって共時的な感覚として一般化してはいけなかったとも思う。
こうして今回もチャイコフスカヤと情報を与え合いながらいろいろと考えてはみたが、まずは何かやってみよう、という段階がこの日の公演だ。本番には、アリーナ・ミハイロヴァのダンスと亞弥の舞踏、それからギタリスト、マックス・ロスチャイルドが加わった。ロスチャイルドは彼女が最近共演しているアーチストと異なり、いわゆるアヴァンギャルドな即興音楽や伝統音楽のプレーヤーではない。正統なジャズやフュージョンを端正に演奏するギタリストだ。「ロスチャイルド」という姓から想像できるようにユダヤ人である。ユダヤ教を信仰しているかどうかはわからない。韓国に家族のルーツがあるミハイロヴァは、以前尋ねたとき、ロシア正教、仏教、無宗教という信仰の来歴をたどったとのことだった。
今回チャイコフスカヤが選曲したウクライナの歌は、たしかに宗教的な素材が多く、以前の共演では演奏したことがない曲も多かった。ペテルブルグでの巨匠たちとの公演と比較すると、どちらかといえば一曲一曲が独立してより音楽(コンサート)的だ。そのあいまを縫うようにロシアと日本の二人のダンスが絡みあう。ミハイロヴァと亞弥は、チャイコフスカヤが前年日本で購入した和服の生地を使いながら、それを身に纏ったり、そこにもぐりこんだり、それで道をつくったりしながら踊った。歌を軸とする展開と構成の中でしなやかに共演することができた。ロスチャイルドのキラキラと夜空を浮遊するような星々のようなのエレキギターのアルペジオにつつまれ、まさに「架空の宗教的儀礼」のような、不可思議な様式美が体現されていたように想う。
これまでの彼女のプロジェクトでのつねに変化の予断を許さない野性味溢れる即興演奏よりも、やや儀式的な今夜のほうが、かえってのびのびと演奏に集中できたとも思う。上演中に夜が深まって、終演後に気づくと背後の大窓から見えた教会が見えなくなっていた。
販売禁止となる23時直前にスーパーに滑り込んで、酒を買い込む。禊にまつわるパフォーマンスをおこなったばかりだが、車の中で大いに呑みながら郊外のグスリッツァまで向かう。
9 森のなかのアートレジデンス

3/22
モスクワ中心部から車で南に約2時間、深夜に到着し、森の中の宿泊場所、会場となる「グスリッツァ」に到着した。暗いので施設の大きさや外観もわからない。中に入り、さっそく施設の見学をということで、案内される。
驚いた。次から次へと、アトリエや劇場のような場所があらわれる。農村の伝統的な衣服を身につけた一団が、アコーディンを抱えて古そうな曲を演奏しながら通り過ぎ、御伽噺の中に放り込まれたようだ。 廃墟となった古く大きな工場施設から、劇場や人が集う空間をつくりあげてゆくこと自体がコンセプトなのだそうだ。ここで行われる「СВЕТ=0=ТЕНЬ(光=0=影)」で、舞踏ワークショップを行い、サインホ・ナムチラクとともに創作し、上演を行う。
朝起きて庭に出る。雪解けでぬかるんだ土と黒い水たまりにまた白い雪が吸い込まれてゆく。きのうまではもう春がきたかと思ったら、今日また少し冬に戻りました、と滞在者の誰かが私に話しかけた。広いので食堂やロビー以外でそう多くの人に出くわすわけではないが、ざっとあわせて150人から200人くらいの人が、いまここに滞在しているそうだ。
この日は公演がないので、新しい場所で時間に余裕があるほうがなにかとよいだろうと、チャイコフスカヤとのコンサート後で疲労していたが、昨晩中に無理にもこちらにやってきた。朝からもりだくさんの一日。まずはあらためて施設を案内され、翌日のワークショップや本番の会場を決めてゆく。椅子やテーブルのないティールームで会合。床に楽器がそこら中に転がっていた。みななんとなく勝手に手に取って音を出したりもしているが、小さな音色ばかりなので心地よい。尺八を吹く青年と、ダウン症のワークショッププログラムに参加している女性を中心に、次から次へいろんなお茶でもてなしてくれる。久しぶりに床の上に寝そべってリラックスした。
長期レジデンスの美術制作やダンサーなどのアーチストや、週末に自然とアートを求めて訪れる人、芸術や福祉関連ワークショップの関係者、イベントに出演する我々のような人々、運営スタッフが滞在している。掃除や建築、配膳、などを滞在者がボランティアで行う仕組みができていた。フェスティバルのゲストアーチストである私たちは、自分で食べた食器を洗って戻すくらいだったが、それらがとても上手く回転しているようにも見えた。良くできたシステムやベースとなる理念が共有できていないと成立できないはずだ。
たしかにこのような場所に特有なヒッピー共同体風を感じる。食べ物は全部ベジタリアン食だった。しかしどうやらここでは酒や大麻などがある匂いはしない。食堂やカフェはあるが酒の販売もないようで、スーパーや販売店がすぐ近くにある訳ではない。そもそもここで酒を飲もうとはあまり思わないのかもしれない
数日間の滞在でその全貌がつかめるわけはないスケールの場所だがとても興味深い。しかしなんといっても、まずそれを成立させるのは、この大地の広さと、豊かな自然環境なのだと思う。
10 街の小さな博物館

断続的に降り続く小雪のなか、車に乗って近辺を案内してもらうことに。ここグスリッツァは古い農村集落だったが、レジデンスの巨大な建物は19世紀の紡績工場の跡地だったそうだ。ここを含むエゴリエフスク市は、リャザン地域とモスクワ地域の境目にある。そのため貿易の拠点として市場等が栄えた時期もあったという。
森から出てしばらくすると、小さな市街地に出る。工場で栄えた時代はそれだけ人の交通もあったので、産業や文化も発展し、教会も多いという。ソ連時代は航空大学になった大きな修道院の跡地もあった。古いロシアの農村独特の木造平屋の建築が多く残っている。窓枠のオーナメントは日本で言うところの家紋のようなものだそうだ。とにかく取り残されたような古い木造建築が多い。むき出して茶色のままか、水色や緑を基調にペイントされていることが多い。古びていまにも倒壊しそうな、とても小さな郵便局は現在も使われているとのこと。「かわいい」といってミニチュアを好む傾向は世界共通なのか、同行のサインホ・ナムチラクが興奮しながら写真におさめている。シベリア育ちの彼女が知るロシアの郊外の古い小さな街の風景が残されているのだろう。
大きな教会に立ち寄ると、ちょうど祈祷の時間で比較的多くの信者の人々が訪れていた。キリスト教徒ではないサインホはむろん祈りの十字を切ることはないが、熱心に聖歌が唱えられているのを聴いていた、教会の中の壁を小さな声でなんども「ワオー」と感嘆しながら触ったりさすったりしていた。
限られた滞在の中で私は、美術館や博物館に自ら望んで訪れることは少ない。ぷらぷらその辺を散歩している方をいつも選ぶのだが、この地のフォークロアを伝える小さな美術館にも行った。ソ連時代に生まれたトゥバ人でありロシアを離れて久しいサインホが、いわゆるスラブの民俗文化や正教の信仰にどのように関心を示すか興味があったからだ。昨年岩手県立博物館と美術館に盛岡でのコンサートプロデュースしてくださった金野吉彰がサインホを伴い連れて行ってくれたときもそうだ。そのときの興味深いエピソードはwebマガジンの「Jazz Tokyo」に寄稿された興味深い金野氏の記事(https://jazztokyo.org/reviews/live-report/post-32987/)があるのでお読みいただければ幸いだ。
そんな興味もあって美術館に入ったのだが、まず私自身がとても興奮してしまった。13世紀から15世紀にモンゴルのキプチャク=ハン国による支配を受けた「タタールのくびき」以降のこの地に残された工芸品や絵画だ。食器やがらくたも含めて、この地の資産家がコレクションしていた工芸品から郊外の都市や農村の生活を想像する。工芸品や肖像画にみられるオーナメントには、タタールなどのアジア世界を象徴する竜を剣で退治し、脅威だった「悪魔」に勝利し、ロシアが築かれていったことを誇るような紋章が多くみられた。正教会の古い聖像画もあったが、民衆への布教、信仰心の強化に用いられた絵も多かった。
それらは、いわゆる美術的価値の高いものではないのだろう。そこで強調されていたのは、生への充足感や死後の世界ではなく、死の恐怖そのものだ。おどろおどろしい絵が多かった。民衆に死を強く意識させ、恐怖心をうえつけることにより、正教の信仰心へと直結させていったのだろう。ロシアの民衆の死生観の原風景なのだろうか。この地に残存する独特の聖歌の歌唱法が記された「歌の本」もあった。オーディオを聴きながら、われわれもサインホもいくつも写真に収めていた。
11 ロシアの霊性1 雑木林と雪道で考えたこと

3/23
朝早く、施設のそばの長い雪道を歩く。もうすぐそれが溶け、大地が露わになる季節だが、この冬もまた、そこに幾重の雪を重ねてきたのだろう。まだ小雪がちらつき、寒風に麻痺した身体は、他のいかなる存在とも断絶し、身体から現実がじょじょに剥がされてていくようだ。道のそばの雑木林をしばらく一人で歩いてみた。少しずつ日が射してきた。小川があった。日の当たらぬところ半分はまだ氷の上は白い雪、日の当たるところ半分は氷の下で水が湧き青みがかっている。雪の下の春がようやく芽を吹きはじめている。
そんな風景をひととおり眺めていると、ふとこれまでのさまざまな公演後に、いただいた賛辞を思い出した。今回もそうだったが、ロシアではいわゆる「スピリチュアル」な感想をいただくことが多い。たとえば大地からエネルギーから吸い取って、音でそれを私に与えてくれた、だとか、あなたの演奏する身体がまとう「オーラ」が万物とバイブレーションして波動のように伝わってきた、などという内容を直接伝えてくださる。ここでは大地との接触に生の根本がありながら、その地面の上で霊性に震わせられてときおり自分が自分でないような感覚になるのだろうか。
私自身はそのような「スピリチュアル」な感覚を意識しながら演奏することはない。老若男女問わずだが、とくに高齢の老人、それも老婆からのそのような感想が多いように思う。老若男女問わずだが、とくに高齢の老人、それも老婆からのそのような感想が多いように思う。わざわざ、周りを探して英語が話せそうな若い人をみつけ、伝えにきてくれることが今回のツアーでも幾度かあった。
宗教学者の井上まどかは、NHKラジオ宗教の時間「ロシア人の信仰と仏教ブーム」でこのように語っていた。(http://h-kishi.sakura.ne.jp/s-176.htm)
「ソ連解体から二十五年経つわけですけど、ソ連時代のメンタリティと呼べるものは、そう簡単にはなくならないだろうし、なくなっていないというふうに考えています。じゃソ連時代のメンタリティって何なのかっていうことですけど、例えば人間の可能性を信じる。あるいは人間の力を信じる。あるいは超越的なものを何かしら立てる、想定するというのではなくて、人間賛歌の側面がやはりソ連時代にはあったと思うんです。そういう人間の力、人間の可能性を信じる人間によって人間のよき社会を作るというような考え方っていうのは、そう簡単にはなくなってはいない。つまりソ連解体したから、帝政時代のロシアのような国家と教会が分離していないような時代に戻れるわけではない。そうすると、神による救いを待つというよりも、人間の可能性を信じつつ、人間の神化という言葉はあまり使わない方がいいかもしれないですけど、人間が人格的に、霊的に高められる可能性を信じつつ、その完成に向かって進んでいくような、まあそういうような宗教なり、実践なりが、人々に好まれていくのではないかなぁというふうに思います。かならずしも、超越的な存在を否定してるというわけではないですけれども、やはり人間の内在的な、あるいは神、あるいは宇宙とつながるような人間の潜在的な可能性を信じて実践していくような、そういうものが非常に親しまれていくというふうに思います。」
ロシアでは「霊性」や「神化」など、異教性をも包括してしまうような、神と自然とを一体化させる汎神論的コスモロジーが、人間自身にまで適用される、ということだろうか。この地の人々は、音や踊りをそのように感じる感性をもつのだろうか。
これまで他の海外各地で演奏したおりに、観客の方々からいただいた賛辞の言葉にも、それぞれに特徴や傾向があることにあらためて気づいたので振り返ってみる。こちらの思いや意図が伝わることも嬉しいが、思ってもみなかった感想をいただくのは、さらに嬉しいものだ。
ヨーロッパでは、創作コンセプト自体に関与する、批評的な賛辞をいただくことが多かった。英語で言えば、ヨーロッパが「interesting」でロシアが「amazing」かの違いであろうか。
そういう意味では日本では控えめな「interesting」が多い気がする。時折ロシアのようなスピリチュアルな賛辞をいただく場合もあるが、多くはない。稚拙な感想のように敬遠、自重されるきらいもあるのだろうか。日本では具体的な細部を批評的に評価したり、あるいは逆に、言葉少なく、素晴らしかったです、のように抽象的な感想をいただくことが多い。もちろん、言語の機微を互いに知るぶん、直接的な言い方を避けるという面はあるのだろう。
演奏機会が多かったトルコでは、残念ながらそのほとんどが大都市イスタンブールばかりだったからか、いま思い返してもなかなか特徴的な特色を抽出できない。アジアの同質性もあるから、ロシアやヨーロッパのように異文化として捉えてそれに驚く、ということは少ないのかもしれない。演奏する場が、現代的なアートシーンが多かったからかもしれないが、強いて言えばヨーロッパと日本のあいだのような感じだっただろうか。
アメリカでは、基本的にはっきりと感想が伝えられるが、内容はかなり人によるという印象がある。
アフリカ大陸では、たった一度しか演奏したことがなく、それもアラブ圏のエジプトのカイロのみだ。演奏の前に、関係者の方から、おそらく、お客さんの多くは途中で帰ってしまうが、そういうものなので、気になさらないでくださいと言われた。300人くらいの観客だったと記憶するが、実際はそのほとんどの人が残って最後までみてくれた。アフリカ大陸では、どんな反応があるのだろう、正直想像がつかない。芸術や芸能の存在のしかたや関わり方の違いの大きさがこのような差異に表れるのだと思う。
雑木林を抜けて、施設に戻るためにまた雪に埋もれた長い道を歩き、午前中の舞踏ワークショップに戻る。きのう美術館であやしげな予言者の肖像画をみたからだろうか、「ユロージヴィ」というロシア語が思い出された。「ユロージヴィ」または女性形では「ユロージヴァヤ」とは、乞食のように野宿しながら俗世に潜みつつ放浪し、ときに狂人や愚者を装いながら、祈祷し、齋(物忌み)を続けキリストの教えを明らかにする人。予言者的な存在になることもあった。キリストの受難の追体験であるともいわれている。日本の漂白の俳人や仏僧などにもイメージが連鎖する。アーニャ・チャイコフスカヤとの将来のプロジェクトでは、舞踏のモチーフとして亞弥に提案したらどうだろうか。
日本の舞踏、暗黒舞踏といえば、海外ではまさにスピリチュアルでアメージングな賞賛の対象となるだろう。これまでの経験から、海外での舞踏に対する過度な期待と幻想みたいなものを目の当たりにしていた。音楽詩劇研究所では、第三章に述べた、ウクライナのオデッサでの舞踏フェスティバルでのワークショップ経験もある。過剰な反応や過度の誤解を受けぬように、ワークショップの概要やキーワードをあらかじめ英語で先方に送る必要があった。亞弥と相談しながらあえて私なりに言語化を試みていた。しかし舞踏を言語化し、さらに翻訳することは難しい。それゆえの誤解も生ずるが、それはどんな表現にもいえることだ。しかしこの翻訳の不可能こそすべての表現の本質だと思う。
舞踏は無数の死者の中への連絡だ。かつてその心象風景のなかに鳴りやまなかった歌は死者の夢の中にもあらわれる。それはこの世の中にはあらわれなかった歌だ。あなたの夢の中にしか現れなかった歌。そこに想いを馳せ、独りの人間が、歩けなかった赤子の記憶を思い出すように旅をはじめる。大地が、そこにある生き物や無数の死者たちが、一人の孤独な人間を夢遊病者のように突き動かして歩かせる。そのようにして地を踏むことは、舞踏そのものかもしれないと私には思えた。舞踏も、第二部以降に述べる、音楽詩劇研究所の創作の念頭にあった「夢の歌」というものと同じではないかと思った。
冬の終わりと春の訪れの間で、雪に埋もれた道を一人歩きながら、この大地に生きる人は「夢の歌」を知っているのかもしれないと思った。
12 ロシアの霊性2 十字架と囚人の唄

昼になるにつれすっかり天気がよくなった。羽根を濡らした小鳥たちがあちこちで囀っている。明日ここで行われるサインホ・ナムチラクとの最終公演のリハーサルを兼ねた舞踏ワークショップを終えた後、アーニャ・チャイコフカヤとのコンサートのため車でまたモスクワに戻る。
胸元にうっすらとタトゥーのあとが残るちょっと怪しげな様子のおやじであるドライバーと、助手席には同じくらいの年の60がらみのおじさん。お二方ともあとあとも施設内でもよくみかけたので、施設で雇っているドライバー、小間使いみたいな方たちなのかもしれない。車に同乗する昨日のフェスティバルに出演したモスクワに帰るミュージシャンが、慎重に大きな楽器を後部座席にしまおうとしているとき、ドライバーがあわてて閉めようとして、バックドアがミュージシャンのおでこにかなりの衝撃でごつんとぶつかった。気の毒に、彼は相当痛がっていた。しかし彼は丁寧に詫びるでもないので、雲一つない青空のもと、なんとなく不穏な雰囲気で出発。
高速運転で飛ばすドライバーがカーラジオをチューニングし流れてきたのは、古い囚人の歌、アウトサイダーの歌。トラック野郎たちがヤクザ映画に憧れたような感覚に近いかもしれない。以前、こういう歌をみんなが好きなのかと尋ねると、あれは昔の歌で懐かしがって聴くようなものだけど...と眉をひそめられてしまったことがあった。韓国のカセットミュージックの「ポンチャック」を思い出す。高速バスやタクシーの運転手さんが眠気覚ましにきいていたというチープな音色のキーボードと、強烈な2拍子の打ち込みビートともに歌謡曲や民謡をエンドレスにメドレーで歌われる、品性よろしくない懐メロとして敬遠する人が多い一方で、根強く愛され続けている。
そういえば先に滞在したペテルブルグで空港まで向かう車の初老の運転手さんも古いヤクザ歌を聴いていた。話し好きな方なようで、なんとかロシア語で応答していた。すると唐突に日本の女優で好きな人がいて「コマキ・クリハラ(栗原小巻)」だと得意げにいう。ソ連時代に日ソ共同制作の映画で主演をつとめていらしたはずだ。会話の中で、おじさんがウズベキスタンの出身とわかったので、好きなウズベキスタンの歌も教えてほしいと頼んだが、インターネットの接続不良らしく、聴けなかったのは残念だった。
カザフスタンのアルマティでもタクシーの運転手さんが、カーラジオでロシアのヤクザ歌を聴いていた。ヤクザ者をテーマに歌う声はだいたい似ており、イメージ通りのしわがれた「だみ声」が多い。カリスマ的なユダヤ系の歌手アレクサンドル・ローゼンバウムの「だみ声」と優しい絹のような声が同居する声に似ていた。そうかと運転手に尋ねると、後部座席からダンサーのアリーナ・ミハイロヴァが、それは、ミハイル・クルグという歌手だと教えてくれた。素晴らしい歌手だったが殺されてしまったのだそうだ。トヴェリというモスクワ郊外の街で家の中で侵入者により殺害されていた。その事件は謎めいたまま迷宮に入ったらしい。彼のレパートリーの大部分は犯罪者の歌だった。
カーラジオで、安っぽい打ち込みビートで嗄れ声のおっさんの歌う囚人の歌を聴きながら、モスクワへと向かう。
陰影のない郊外の風景は続く。眠ったり起きたりを繰り返す。時折窓の外に目をやると古い教会が佇んでいるのが見えることもあるが、車は気にせずに走り続ける。途中で気づいたが、ドライバーとコンビの助手席に座る男は教会を通り過ぎるたび、反射的に十字を切っていた。数えていたわけではないが、モスクワに到着するまでいったい何度そうしていたであろう。
車で2、3時間くらいというと、真ん中を山脈が貫く地形の日本(本州)で言えば、ある程度の標高の山間部から都市部へとおりてゆく距離と時間の感覚だ。しかしここはずっと平地であり、そこに突然に大都市モスクワがあらわれてくるような感じだ。森林、郊外都市、大都市とグラデーションのある風景とはいえない。外敵からの防衛のために囲まれたヨーロッパなどの城塞都市の名残なのだろうか。そうして中心地に入りほどなく、会場のドム・カルチャーセンターに到着した。
13 バシコルトスタン出身のトランペット奏者、ユーリ・パルフェノフの眼

アーニャ・チャイコフスカヤのウクライナ古謡のプロジェクト「青い湖」のモスクワ最終公演。ロシアの実験的な前衛音楽や民俗音楽を紹介してきたこの会場「DOM(ドム ロシア語で「家」の意)」で演奏するのは5度目であり、まさに帰ってきた、という感覚がある。
昨晩のグスリッツァのフェステイヴァルのオープニングイベントで、サインホ・ナムチラクがここドムの創設者ニコライ・ドミートリエフ(私が2004年初めてここで演奏した時にはすでに亡くなり、未亡人であるリュドミーラ・ドミトリエヴァ氏が現在に至るまで芸術監督をつとめている)に捧げた詩「イデオロギストの肖像」の朗読と一緒に演奏をしたばかりだ。
ドミートリエフは、ペレストロイカ期以前から、西洋の現代的表現を受容しながら、民俗音楽の観点も視野にいれロシアの新たな音楽の独自性を画策した。1995年、かつてユダヤのシナゴーグであったその場所に、このドムをそのプラットフォームとして開設した。若かりしサインホはその渦中に彼と出会った。それまでの民俗音楽の研究や民族歌謡団での活動から、彼女自身のオリジナリティとしてそれらを独自に表現する道を開いてくれた氏はきわめて重要な存在だったのだそうだ。
ロシアを離れてヨーロッパに住んで数十年になるが、こうして戻ると、それを強く意識するのだろう。だから、昨日の詩の朗読会で7篇ほど声にした詩のなかでも、彼に捧げる詩を一番目に選んだのだろう。サインホはトゥバの昔話を語り聞かせする録音プロジェクトも行っており、子供も多く集まる施設なので、主催者側からはそれを行ってほしいとの提案もあった。しかし昨晩は自らの宇宙観を表すような哲学的な自作詩を朗読することを彼女は選んだ。
この日の「ドム」での公演案内のクレジットには書かれていなかった(私はさして気にならないが、ロシアではこのようなことが実にいい加減だ)のだが、本日もペテルブルグ公演に引き続き、トランペットのユーリ・パルフェノフが参加。もう73歳になるパルフェノフは大柄なロシアの人に囲まれるとかなり小柄である。そのせいなのか、基本的な視線が、少し下から窺うような目線になる。自分を主張せずに周りを静かに見つめているようにもみえる。声も小さくて温和だ。いかにもアーチスト然としたいでたちの、チャイコフスカヤやコントラバスのウラジーミル・ヴォルコフとくらべると、パルフェノフはたとえば出稼ぎで都会に来た、無口な労働者のようにもみえる。なんとか英語とロシア語を交えながら少しお話しすることもできたが、 英語はほとんど話さないので込み入った会話は難しい。しかし、ほかのメンバーとロシア語でよくお喋りしているのかといえばそうでもなく、やはり口数は少ない。
会場の入り口に、この月末にここで公演するらしい、トランペットの近藤等則氏のチラシがあった。トランペット奏者というと氏のように人間的にも主張がはっきりしている印象もある。実際木管楽器のサックスなどと比べれば、演奏する身体にもずいぶん負荷がかかるので楽器に対しても強い主張や意思がないと音が出てくれない。
しかし前回2016年にチャイコフスカヤの推薦により急遽共演したトランペットの巨匠、ヴァチェスラフ・ガイボロンスキーにも感じたが、パルフェノフもまたそのような自己の主張で音楽空間をみたすことがない。ガイボロンスキーは、シアトリカルに動きながら演奏する。その音は一筆書きのように澱みやけれんみがない。まるで老荘の言辞を思い出させるようなつかみどころのない軽やかさだった。先日のペテルブルグで初共演させていただいたパルフェノフは、ガイボロンスキーの融通無碍とも異なる、芯のつよい静けさがあった。音楽が即興的にさまざまなドラマを展開して行く中でも、まるで何事もなかったかのようにそこに佇みつづける。一方で、そんな佇まいから発せられる音は多彩だ。
パルフェノフのキャリアは長い。ご本人とこみいった会話をするのが難しいので、Wikipediaなどでも調べた。バシコルトスタン共和国生まれで、アルマティから山を越え車で3時間のソ連の大きな実験農場があったことでも知られるカザフスタンのフルンゼ(現在のキルギスタンの首都ビシュケク)の音楽学校で学んだ。その後ウズベキスタンの国立放送局の交響楽団のソリストを長く勤めた後、ジャズに転じ、モスクワで活動し、世界各地で演奏している。サックスのセルゲイ・レートフの管楽器のトリオ「Tri-O」にも参加していた。

帰国後にパルフェノフがプレゼントしてくれサインホ・ナムチラクと「Tori-O」が共演した時のDVDをみると、興味深かった。みな楽譜を見ないで即興的に演奏しているが、楽譜があるかのようにとても巧みに絡みあいながらアンサンブルが構築されていたからだ。早速セルゲイにメッセージを送り、アンサンブルの仕組みについて質問してみた。楽譜を用いて作曲したものを練習して血肉化した後、最終的に楽譜を離れてより自由に演奏するのだそうだ。一般的な創作過程とは逆であり、効率も悪い。ふつうは初めから自由、あるいは自由の中から揺るぎのない確固たるものが創造される。しかしここでは、アンサンブルの構造をとどめつつ即興で生まれる新たな関係性こそ重視される。パルフェノフはそこで、民族楽器の笛等も用いてコミカルな音も出していたが、やはり何事もないような顔で即興していた。控えめな出で立ちで、ここまで存在感がある演奏も珍しい。
先日の、ヴォルコフ、パルフェノフ両氏が参加したペテルブルグのアウクツィオン(Ayktion)のコンサートでも、小柄な老パルフェノフが、伏し目がちに、やはり身じろぎせず演奏をしていた。動き回るオレク・ガルクーシャや身をよじって歌いギターを演奏するレオニード・フェードロフ、はげしく身体を揺さぶりながらコントラバスを演奏するウラジーミル・ヴォルコフ、踊るように演奏するメンバーたちのなかで、かえってなんとも格好よい存在感をはなっていた。
ロシア伝説のバンド、ペレストロイカ期にはほかにみることができない特異なニューウェーブとして西側にも紹介されていたアウクツィオンも中心メンバーほぼ60代だ。チャイコフスカヤ、ダンスのミハイロヴァは別としても、70代のユーリ・パルフェノフや、スラヴァ(ヴァチェスラフ・ガイボロンスキー)、60代のヴァロジャ(ウラジーミル・ヴォルコフ)やサインホ、セリョージャ(セルゲイ・レートフ)、みな大先輩であり、それぞれにレジェンドとして扱われている。しかしソ連時代から現在まで演奏を続け、いまなお新たなプロジェクトに臨み、創作に対する熱い想いと工夫がある。そういうような方たちと共同作業させてもらっている。たくさんのことを彼らに教わっている。
14 キャンディーズ in モスクワ?

本番前のリハーサルが始まる。すでに完成された彼らのアンサンブルの上に私が即興的に新たに加わることになる。さらに効果的なアンサンブルを構築するために同楽器のヴォルコフが私のフレーズを提案してくるのでなんとか応える。こうかな、こうかな、おおっ、それだよ、という感じ。パルフェノフもここでファンファーレを2回吹くから、このタイミングでベースが激しくフリーで弾いてくれないか、と 音と身振り手振りを加えながら提案してくる。こうして新たなアンサンブルができあがってゆく。
夜になりここ「DOM」で、ウクライナ古謡「青い湖」公演が始まる。ステージの構造上、私とウラジーミル・ヴォルコフの二台のコントラバスとユーリ・パルフェノフのトランペットによるトリオがステージの下で演奏し、ステージの上で、亞弥、アリーナ・ミハイロヴァの二人のダンサーとアーニャ・チャイコフスカヤの唄。最終公演で気合いが入っているのか、チャイコフスカヤが随分と演劇的な動きで、ダンスもしている。
それにしても、ステージ下から眺めていたら、三人の女性が横並びになったときは一瞬キャンディーズにみえてしまた。アリーナ(ミキ)アーニャ(ラン)亞弥(スー)。見た目にもある程度言えるが、キャラクター的にもあてはまるような気がして可笑しかった。そういえば三人ともファーストネームはA、アで始まっている。。人、あるいは男性は、女性という存在に「ア」の響きを求めるのだろう,,,
今回のツアーカザフスタンから、ペテルブルグ、モスクワとほんとうに多くの時間をとともにしたアリーナ・ミハイロヴァとも今日でお別れ。もともとカザフスタンでの「さんしょうだゆう」以降は共演の予定はなかったのだが、アーニャ・チャイコフスカヤがこの一連のペテルブルグ、モスクワでの公演に彼女を必要としたので、再び共演することになった。ミハイロヴァはカザフスタンでこう私にいった。
「今回のカザフスタンの公演で、もうはっきり自分のこの先の生き方をはっきりすることができた。私のルーツが韓国人であることがとても大事なことになった」
と言った。10月の韓国ソウルでの公演の再会を誓ってお別れした。アリーナ・ミハイロヴァとの濃密なコラボレーションは後の第三部で詳しく述べたい。
ドムをあとにしてまた真っ暗な道を飛ばし、再び郊外のグスリッツァに車で2時間かけて戻る。カザフスタンから続いた長かった音楽詩劇研究所「トランス・ステップロード(草原の道)プロジェクト」もいよいよ明日が最終日だ。明日はそこでまた舞踏ワークショップを行い、それを元にサインホ・ナムチラクと創作し、夜に上演する。
15 テングリ・ヴァージョン「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

3/24
サインホ・ナムチラクが、上演で用いる自身のライブペインティングによる大きな布に描くカリグラフィーの案を説明してくれる。たくさんのパフォーマンススペースを持つここグスリッツァでも一番大きな体育館のような広さの部屋での上演である。ふだんはここで美術作品やオブジェの中で子供たちが駆け回ったり、大人たちが寛いだり遊んだりしている。
まんなかに遊牧民族の移動式の家であるユルタの骨組みを模した鉄筋のオブジェ。後方には、打ち捨てられた木舟のような、なんとなく象徴的な美術作品がある。サインホが描いてゆく布は一枚で15メートルほど。それが三枚ある。彼女のみたてでは「ユルタ」の手前に二枚、後方に一枚の布。客席から遠くに離れて行く形で手前から、それぞれ地下、地上、天上界をあらわす。これはまぎれもなく中央アジアのテングリ信仰の世界観である。シンプルな三階層構成だ。ロシア人だがトゥバのシャーマニズムを学び、実際に「シャーマン」として医療も含め音楽家としても活動するアコーディオンを弾きながら呪詛のような歌を歌う女性、ヴィエラ・サージナも参加する。

サインホが地下、地上と歌いながら描き、舞踏ワークショップに参加したアナスタシア・シュレヴァコヴァと10人ほどのダンサーたちが踊る中央にあるジャングルジムのようなオブジェの周りを歩み、木舟のオブジェの手前の天上にたどり着く。天上の絵を描いた後、最後は木舟の前でマントラを唱えるように息の長い倍音唱法(ホーメー)をおこなう。その声に導かれるように、「ユルタ」の中から外へとばらばらに離散したダンサーたちが踊りながら吸い込まれるようにサインホのもとに集ってくる。一人その中に残っていたシュレヴァコヴァは、踊り、最後にユルタを出て彼らとは別の方角に歩みながら姿を消す。
ユルタの象徴的な用い方を考えているうちに、内容や表現方法は異なるが、この作品も「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく(Continental Isolation)」のヴァリエーションだとあらためて気づく。人物設定は第一章のさいごをご覧いただければ幸いだ。
架空の民族の一族は、ダンサーたち。
異民族の捨て子だが一族の歌姫となった娘は、ヴィエラ・サージナ。
一族から離散し美術家となった女は、アナスタシア・シュレヴァコヴァ。
最後のシャーマンは、サインホ・ナムチラク。
マレビトは、亞弥。
こうして役割を変えながら、「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく(Continental Isolation)」に描かれた神話的構造をそのままに、それが装置となって新たな歌や踊りや踊りを発生し続ける。
リハーサルで、倍音唱法を続ける彼女の周りにダンサーたちがゆっくりと歩み寄るラストシーンについてサインホ・ナムチラクに意見を求めた。それは、彼女が「終わり」に対してどのようなビジョンをもつのかを知ることだ。
どのようにラストシーンのフォーメーションをつくり、観客に最後の絵としてみせるのか。そのときの声はどのようにあるべきかの二点を尋ねた。
サインホを囲むように円をつくるのか、密集型をのぞむか、横一列か、フリーか。そして、そこに響かせる声は、サインホの倍音唱法に対して、ダンサーたちもあわせて声を出すか。出すのならユニゾンか、フリーか。
サインホの答えはこうだった。ダンサーたちは、一列に横並びし、声はあわせるが、ピッチ(音程)はそれぞれずれていたほうが良い。自身の芸術に厳格なサインホも「ズレ」による「あわい」のなかに可能性を求めるアーチストなのだ。
その声の中で、「最後のシャーマン」であるアナスタシア・シュレヴァコヴァには「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」という言葉をロシア語でひたすれ連呼してもらうことにした。叫んでも、呟いても、歌っても良いというと、シュレバコヴァは「私はマントラのようにそれを唱え続けながら姿を消すだろう」と言った。
「カニエツ イショ ニ カニエツ(Конец–еще не конец)..........」
サインホは全体の演出を私に任せた。しかし私は、私ひとりのビジョンを体現することが演出だと思わない。サインホやシュレヴァコヴァだけではなく、できればほんとうは全員に意見を求めながら、それらを編集し、舞台のうえにまとめるのが、演出だと考えている。そのようなプロセスを経て、私自身のビジョンも形成され、それがまた次の創作を生む。そのような繰り返しによって生まれるのが、まさにユーラシアンオペラの副題とした「21世紀の神謡集」なのだ。
ところで、第五章に述べた、いわくつきとなったサインホのライブペインティングのパフォーマンスについて、ようやく謎が解けた。
昨年2018年の東京での「Continental Isolation」の本編が始まる前の会場中の舞台でサインホが布に描いた絵や邪悪そうな呪いのような声は、公演後に我々の間に物議を起こした。「シャーマン」として、なぜこれから始まる舞台を前にしてあのような、悪意に満ちた声で、邪悪を思わせる絵を書き、それを舞台に降ろすのか。彼女は本番数日前から表情が硬直し、疲れ、実際に戸惑ってわれわれに突如怒りとともに不満をもらすこともあった。個人的な不満があのようなパフォーマンスとなって現れたのではないか、とわれわれが考えるのは自然なことだった。東京ではサインホからその説明がなかったのでわからなかった。
今回ロシアでサインホが冒頭に描く内容についてこのように語ってくれた。「第一の世界」である「地下世界」は、 テングリ信仰では地下世界は邪悪神の世界なので、呪詛のように吐き捨てたり呟いたりしながら、大きな筆を使って激しく描くことのこと。あのオープニングの「邪悪な」パフォーマンスとはこのことだった。
地上は旋律的に線で描き、歌もそれに自然に沿わせる。天上は点描的に描き、歌唱も同じイメージだそうだ。今回サインホの説明によれば、これがテングリ、トゥバのシャーマンの儀式の考え方なのだ。まずはじめに地下の「邪」ありき、そして「地下」「地上」「天上」全てが揃って、宇宙を成しているのだ。「天上」に救済や安寧を希求する精神は、キリスト教をはじめ多くの宗教画や音楽にもあらわれる人間の死生観だ。しかし、天上だけでなく、その全てに対するビジョンを同時に持ち、それを体現するのが、中央アジアやシベリアのシャーマニズムの本質なのだ。
東京でサインホには会場中のパフォーマンスについて私は、彼女を尊重するつもりでこう伝えていた。「あなたのフィーリングで自由に描いてください」とそれだけいって任せた。しかしあれは、フィーリングではなく、彼女の信仰や伝統的慣習として当たり前の選択だったのだ。それらを先立たせるのが、彼女の表現、生き方の流儀だった。そして私はその後もあの「邪」がなんだったのかにつて特に説明を求めなかった。私が確認していれば、みんなの疑念もおこらなかったのかもしれない。私の甘さである。しかし同時に、知りたいが、関係を続けていずれわかれば良いとも思っていた。今回、彼女の説明をきいて、半年を経て謎が解けた。
ここロシアでは、寒くないか、とタオルケットを手配してくれたり、この施設の場所や使い方を隅々まで教えたり、私たちの世話をやく心優しき、心配しすぎな母、もしくは世話好きの近所のおばちゃんだった。
トゥバの伝統弦楽器イギル奏者の澤田香織里氏が、昨年東京でサインホと会ったときのことを話してくれたとおりだ。東京でじょじょにこわばっていった彼女の表情や、混乱を怒りとして露わにする姿をみて、私が電話してトゥバ語を理解する澤田に助けを求めたのだ。トゥバ語で話して彼女の心を和らげてほしいと思ったからだ。彼女はサインホのCDを聴いたのをっかけにトゥバに関心を持ち、けっきょくそこに移住し、日本で初めてのトゥバ国立大学の卒業生となった人物である。その後もしばらくその地に暮らした後、日本に再び帰国した。彼女が言うには、心の起伏の大きさも世話焼きも、サインホはトゥバのおばちゃんそのものなのだそうだ。
サインホ・ナムチラクはウィーンで娘、孫と3世代で暮らしている。個人主義のヨーロッパでは稀なケースで、そういうところにも自分の東洋的なルーツを自覚するそうだ。実際は海外の旅公演も多くて、まったくそれができていないが、良き母、祖母であることを自分なりに一生懸命やっている、といっていた。
終演後、サインホが布に描いたばかりの3枚の地下、地上、天上界世界の作品を、奴隷のように指示を受けながら手分けしてドライヤーで乾かす。かなり時間がかかった。そして、なぜか、また地下世界の「邪悪」な作品をプレゼントしてくれた。自分で持っていたくないということなのか。私の自宅の押し入れの中には、サインホが描いた中央アジアのテングリ思想の地下世界が、東京で物議をかもしたそれと今回のものを合わせ、二枚存在することになった。なぜ、地上や、天上のものをくれないのか、とも思うが、それも聞かないことにした。聞けば済むことかとも思うが、その理由もまたいつかコラボレーションするときに、わかるかもしれない。
これにてカザフスタン~タタールスタン~ロシアとひと月に渡りコラボレーションを行った今回のツアー、音楽詩劇研究所トランスステップロードプロジェクトの公演は全て終了。
私の自宅の押し入れの中には、テングリ信仰の地下世界を描いた邪悪な布が二枚、くるまったまま眠っている。



あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
