- Home ユーラシアンオペラへの道
- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物
- 囁きはじめるユーラシアの風と歌
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
- ユーラシアンオペラ・用語集・索引
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
うたものがたり「フォークソング考」

ユーラシアンオペラとしてのうたものがたり
「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
1 独り歌の源流
2 「死者の歌」から「夢の歌」へ
3 「楢山節考」と「日本春歌考」
4 マテリアルな響きとともに
5 フォークソング(民謡)にならない声
6 韓国民衆芸能のダイナミズム
7 ユーラシアンオペラとしてのパンソリ
8 「安里屋ゆんた」と春香伝
9 韓国のロミオとジュリエット 「春香伝考」
10 和人のユーカラ/サハリンのアリラン
11 オタスの杜について
12 文字のない歌 中島敦の「狐憑」とル・クレジオ
音楽詩劇研究所は、2015年に初演の「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」をベースに、翌年から海外で現地アーチストとのコラボレーションを続けた。
中露国境付近の遊牧少数民族の定住生活への移行が描かれた小説に着想を得た作品を、2016年にアルメニア、ロシアで公演した。翌年にはめざそうとする創作が、初演当初に意識した「死者のオペラ」から「ユーラシアンオペラ」に移行しつつあることを自覚した。夏に行ったロシアのバイカル湖の周辺と、トルコ、ウクライナでのコラボレーションの充実があったからだ。それらの地では、古い民謡が現代のアートとしての表現の中にいきづいていることに驚かされた 。それぞれの地の信仰やフォークロアを知り、アーチストと対話を繰り返しながらの創作を継続させ、その集大成として第一部で述べたユーラシアンオペラの完成を目論んだ。
2017年のこのツアーから戻った時点では、同時に音楽詩劇研究所自体の結成当初の方向性である、抽象度の高い「死者のオペラ」を深める必要も感じたが、各地でのプロジェクトで刺激を受け、こちらももっと日本の民俗文化へと接近してみたくなった。核となるメンバーたちが、能、狂言、神楽、民謡、舞踏という伝統芸能やフォークロアに関わる活動をそれぞれ行っており、そうすることが自然な方向だと思えた。現在まで受け継がれ洗練されたいわゆる伝統文化というより、実際にどのように庶民が歌ったり踊ったりしていたのかが気になった。残されたいわゆる民謡や口承芸能からそれを想像することができるだろうか。
そのような問いを創作に結びつけようとした作品は、思いもよらず韓国の口承芸能を題材にすることになった。そこから生まれたビジョンは、第一部ですでに述べた2018年の「Continental Isolation」や次の第三部に述べる次ユーラシアンオペラの第二作目「さんしょうだゆう」に引き継がれた。また、同時期に大学生の授業で創作していた口承芸能の成立と文字文化をテーマにした中島敦原作「古譚」を、2019年に音楽詩劇研究所の作品として舞台化した。本章は、この二つの試作的な作品の創作過程における考察を中心に述べてゆきたい。
1 独り歌の源流

現代ほど声に溢れている時代はない。歌声にかぎっても、テレビやインターネットも含め、私たちは何千人の声を聴きながら一生を過ごすのだろう。現代ではそこに、たとえばYAMAHAが開発した人声合成技術を用いた「ボーカロイド」など人工の声も含まれる。奄美民謡をボーカロイドで聴いた時はさすがに驚いた。五線譜で再現することがかなり難しいと思われる、「グイン」と呼ばれる無拍節で、声の表裏を使って音程の跳躍も激しい歌声でさえ、それなりに再現されていた。
いずれにしても現在、一般的に歌といえば「独り歌」をさすことが多い。歌い手の心情が、言葉や旋律になって演じられている。
「ウタ(歌謡)は、集団的モノローグの一形態である_ダイアローグを基本とするドラマに対して、ウタは、自己完結的、自己充足的な言語表現だというのである。この寺山の刺激的な指摘を今日の歌謡研究の立場から言葉を変えて捉え返すとすれば、それは「聞き手の不在」_歌とは聞き手の存在を前提としない言語表現である、ということになろう。ウタと名付けられた言語表現の特殊な形を、他の様々な言語表現の諸形式、ヨム、カタル、イウ、ハナス、トナエルなどと決定的に分つ分岐点がこの一点にある」
国文学者の永池健二は「逸脱の歌声 歌謡の精神史」(梟社 2011)という本で、さまざまな書物から「独り歌」を歌の起源として検証している。終章で、集団とモノローグ(独り言)の関係から「歌」をとらえたこの寺山修司の言葉が引用されている。柳田民俗学の根幹である農村共同体の生活の表象としてのフォークロア(ここでは民謡)は、たとえば労働歌や祭事など共同体の集団作業の歌にあらわれる。その共同体自体の新たなあり方を画策した宮沢賢治の「農民芸術概論」や、民芸の無名性に着目した鶴見俊輔の「限界芸術論」も射程に入れつつも 永池は、歌の起源は「独り唄」にあるとして、鼻歌や呟きに着目する。
永池の論考は、TWITTERなどのSNSやインターネットの世界も照射できると思う。音声コミュニケーションの速度を超えるかのようなそれらは、ダイアローグとモノローグの中間的なコミュニケーション領域だろうか。音声を介して直接的に交わされてきた会話によるコミュニケーションも、文字や記号に置きかわり「音のない声」を響かせる。
後世に残った独り歌は、まさに和歌などを指すように作者が存在する文芸の領域にあった。署名され、作品として残されたのは、主に貴族や僧侶、武家の人たちによるものだ。そもそも文字を使っていたのは限られた人びとだ。江戸の俳諧はじょじょに庶民に広がったが、基本的には、それらに親しんできたのは一部の上流階級だったといえる。しかし生の基盤を個人におくわれわれ現代の庶民は、たとえば宮廷や貴族の文芸にも共感することができる。
恋に悩む私たちは、たとえば昔の宮廷貴族やヨーロッパのお金持ちのような心性で生きているといえるのかもしれない。カルタ遊びで親しまれる、藤原定家が鎌倉時代に選んだ「百人一首」の約半数の50首近くは恋愛の「独り歌」だ。現代のポップソングや歌謡曲もほぼ恋愛の歌。ふつう恋愛は集団でするものではない。個と個の関係を基にする感情だ。こうして時代が進むにつれ歌や音楽も個人から発されるようになる。しかし日本では「民謡」として残された歌に、個人の恋愛感情があからさまに表明された歌は少ない。多くの一般の人々が、個人的な恋愛感情を歌ったり、他人の歌うそれに共感するようになったのは、近代、明治時代以降のことなのだろうか。
平安時代末期の「梁塵秘抄」や室町時代後期「閑吟集」などは、文字を用いなかった民衆や遊女等の恋愛感情も含まれて記録されている詩歌集である。無名の個人の心情を伺い知れる貴重な資料だ。しかし、言葉は残されても、声色やメロディについては知ることができない。残された言葉や芸能、民謡や祭など共同体の芸能や娯楽や儀礼や風習から想像するしかない。
口伝の記憶は、だいたい4世代くらいの間で風化するだろうか。だが文字はそもそも記録し残すことを目的に作られたものだ。文字の一般化は近代化に重なる。江戸時代からじょじょに庶民の識字率も高まり、1886(明治19)年に小学校の通学が義務化される。私はとくにこのような近世から、現代の生活に重なる近代への過渡期に着目した。その時期に訪れた西洋人たちが描写した日本のサウンドスケープを紹介した、章末のコラムを参照いただければと思う。それまで表出されることのなかった庶民のエネルギーや、その後近代国家によって形成される庶民の原像には収まりきらない声(歌)が、渦巻いて聴こえてくる。
2 「死者の歌」から「夢の歌」へ

インド、スリランカの森に暮らすヴェッダ人は、かつては必ず一人一人が歌を創って個人の歌をもち、逆に集団では歌うという習慣はなかったそうだ。そういう極めて珍しい文化もあるが、一般的に民謡や祭はたしかに柳田の説のように、共同体の生活や信仰のあらわれだといえる。だから庶民の歌である民謡は、多くは特定の作者などは存在しない。音楽は作品という個人から創造される「モノ」というより、かつては共同体の「出来事」だった。
私たちはほんの数世代前までは、孤独になることも許されない共同体の因習や山村、漁村の自然環境の中で生きていた、無名の民だったはずだ。たとえ現代人の心性が貴族や武士などに近しいとしても、私は農漁村の一庶民のなかに現代に接続する歌を求めてみたい。そこで「独り歌」はどのように存在したのだろう。
深沢七郎は「楢山節考」等、江戸時代後期の貧農の共同体の因習の中に生きる庶民の姿をよく描いた。この小説を映画にした今村昌平作品では、無名の農民の風景への眼差しが、突如としてズームアップで挿入される。たとえば一人で田畑の作業に向かう道で、無意識に視界に入る虫や草花が、グロテスクともいえる異形の微視的風景としてあらわされる。辺鄙な農村風景の映像の中に突如挿入されるミクロな視界は、深層心理をあらわす超現実的なともいえる。そのような極私的な眼差しは、共同体の民謡や舞踊などにはあらわれにくいものだ。
そのようなビジュアルイメージを音楽や歌に置き換えてみると、「独り歌」からさらに飛躍して、実際に歌われなかった歌も想像してしまう。かつての暮らしの中で、個人がの心性が現れるのは、眠りの時間くらいなのかもしれない。その歌は一人一人の深層にあり、夢の中で響いている。食欲、睡眠欲、性欲が個人の欲求の中心であるにしても、それ以外にもさまざまな社会的タブーを超えた感覚や妄念が乱反射している夢幻的なシュールリアリズムのような世界が、そこにはある。
しかし夢の中で強烈な体験として刻印されたイメージを、たとえば目覚めてからすぐに頭の中に再現しようとしても、難しいことが多い。現実の中に取り戻すことができないない感覚が、他者と共有できぬままに不確かに身体に残存する。「夢の記述」という文学的な再現も試みられてきたが、どのように脳内で響いた「夢=歌」を、他者と分かち合うことができるだろう。
「夢の歌」の交響。それは、フォークロアを超現実的に現代に蘇らせた、中南米の現代芸術や文学のマジックリアリズムにも通じるものがあるかもしれない。そのようなイマジネーションを「夢の歌」と呼んでみることにした。夢と夢とを響きあわせるようなイメージで作曲を始めた。すると第一部に述べた、架空の民族の一族の死者たちによる架空の民謡でを響かせた「死者のオペラ」の創作にも通じるものであることにも気づいた。自己を表現するというより、死者、架空の民族、他人の夢、けっきょくのところそういう他者への想像によるフィクションが、私の創作だといえる。
音楽は世界中の無数の死者たちのたった一人の眠りのなかの夢の痕跡なのかもしれない。
しかし想像にもそれなりの根拠を要する。そのためには残存する共同体の歌である民謡(フォークソング)にたいする私なりの考察が必要だった。
3 「楢山節考」と「日本春歌考」

どちらもタイトルに「考」がつく深沢七郎の小説「楢山節考」と、大島渚の映画「日本春歌考」は、伊勢物語や古典文学の形式のように、さまざまな歌がストーリーの軸となって展開される。二つの「歌物語」のなかでは、理性を超えた刹那的な民衆の死生観と行動がラジカルに描かれた。舞台はそれぞれ、「楢山節考」は江戸末期あたりに設定された 甲州の閉鎖的な貧しい農村共同体。「日本春歌考」は、第二次世界大戦後の学生運動の渦中の東京。
「楢山節考」は、母親を背負った息子が年越し前に雪降る山へ捨てに行く、村に伝わる姨捨山伝説を軸に村の土俗的な因習に基づく暮らしが描かれる。作者による架空の盆踊り歌を本歌とし、そのさまざまな「替え歌」が物語を進行させている。
今村昌平の映画バージョンではさらに深沢の関連作品からの場面も引用しながら、たとえば家督を継ぐ立場でないために結婚や性の欲望が叶わぬ次男や三男坊の欲望や恨みなども描かれる。作者による架空の盆踊り歌を本歌とし、そのさまざまな「替え歌」が物語を進行させていた。たとえば愚痴、子どもたちの皮肉、年老いた親を山に捨てる長男の逡巡や悲哀など、さまざまな心情が替え歌になる。
替え歌は、共同体の生活から少し逸脱したささやかな娯楽、共同体のタブーに対する嘆きや反発、皮肉、本音だ。だから個人の歌の創造の原初のひとつだといえる。それらは他者への共感を求めつつ隠れて呟かれて人目に触れぬまま、たいがいは消滅してゆく。SNS投稿のタイムラインにも似ている。反対に出回って広がり、密かに流行したり、あるい大っぴらに歌われたりすることにって、共同体の歌として本歌自体を更新することもあるだろう。
深沢七郎の諸作では、近世の封建社会に農村に生きる人びとの生活が、当時の現代の市井に生きる人びとの生活と連ね重ねられる。時代が変わっても本性が変わらないことを示しながら、庶民の原像を描いたのが深沢の創作だ。
1960年代の市井の若者を描いたのが大島渚の映画「日本春歌考」だ。演歌士である添田知道によって書かれた同名の書に着想を得た作品だ。
自治や民主化を求める大学制度改革に端を発する1968年パリ5月革命に向かうヨーロッパの反体制運動、アメリカの反ベトナム戦争学生運動を背景に、一方で虚無的な主人公たち男子受験生の性への渇望が描かれる。映画は1967年公開だから、まだ戦後20年ほどの頃だ。自由を求める若者の精神に理解も示す大学教授たちが、酒宴で懐かしむように前時代の軍歌や猥歌を斉唱する。このような進歩的な知識人の姿に、男子学生たちは欺瞞も感じている。教授たちが歌った「よさほい節」を茶化して歌いながらニヒリズムをきめ、教授の妻や女学生に対する性暴力を夢想する。酔ってガスストーブをつけたまま眠りについた教授を、若者は見殺しにする。教授はあっけなく死んだ。
一つ出たホイのヨサホイノホイ 一人娘とするときにゃホイ 親の許しを得にゃならぬ
二つ出たホイのヨサホイノホイ 二人娘とするときにゃホイ 姉のほうからせにゃならぬ
三つ出たホイのヨサホイノホイ 醜い娘とするときにゃホイ ハンカチかぶせてせにゃならぬ
四つ出たホイのヨサホイノホイ よその二階でするときにゃホイ 音の出ぬよに せにゃならぬ
五つ出たホイのヨサホイノホイ いつもの娘とするときにゃホイ 四十八手でせにゃならぬ
六つ出たホイのヨサホイノホイ 昔馴染みとするときにゃホイ 涙こらえてせにゃならぬ
七つ出たホイのヨサホイノホイ 質屋の娘とするときにゃホイ 入れたり出したりせにゃならぬ
八つ出たホイのヨサホイノホイ 八百屋の娘とするときにゃホイ ダイコン枕にせにゃならぬ
九つ出たホイのヨサホイノホイ 校長の娘とするときにゃホイ 退学覚悟でせにゃならぬ
十と出たホイのヨサホイノホイ 尊い御方とするときにゃホイ 羽織ハカマでせにゃならぬ
十一と出たホイのヨサホイノホイ 士(さむらい)の娘とするときにゃホイ 切腹覚悟でせにゃならぬ
十二と出たホイのヨサホイノホイ 十二単とするときにゃホイ かきわけかきわけせにゃならぬ
十三と出たホイのヨサホイノホイ 巡査の娘とするときにゃホイ 手錠覚悟でせにゃならぬ
十四と出たホイのヨサホイノホイ 年増女とするときにゃホイ 口説き覚悟でせにゃならぬ
十五と出たホイのヨサホイノホイ 十五夜お月さんとするときにゃホイ ぴょんと跳ね跳ねせにゃならぬ
十六と出たホイのヨサホイノホイ 十六(いざよい)清心とするときにゃホイ 心中覚悟でせにゃならぬ
大島は本歌からの替え歌であるこの猥歌(春歌)「よさほい節」を通奏させ、さらにそこにさまざまな歌を並べる。
軍歌、軍歌「討匪行」の替え歌である満州の朝鮮人慰安婦の悲哀を歌う「満鉄小唄」(朝鮮訛りで歌われる)、紀元節、「ワルシャワ労働歌」、反戦歌として歌われたウディ・ガスリーの「我が祖国」、東北民謡「ナニャドヤラ」などが歌われている。大島は歌い継がれてきた民謡や反戦や平和を願って歌われるフォークソングも春歌=猥歌であると仮説したのだろうか。
映画にはアメリカの反戦運動のフォークソングに共感する若者の集会も、シニカルに描かれる。敗戦後の朝鮮戦争の特需なども背景に育った主人公たちは、庶民といえども大学進学が許されるほどの経済的基盤を持ち、やがて高度成長期の中産階級層を形成してゆくだろう。一方で貧困や差別による生々しい事件も多発していた時代だ。翌年公開の「絞首刑」では、そのような事件のひとつである東京の江東区の在日朝鮮人の李珍宇少年による江戸川の女子高生殺人事件、小松川事件を題材とした。大島は民衆の虚無と無意識の暴力性をもぶつけあわせながら大衆、民衆の原像を問う作品を発表してきた。
「日本春歌考」のラストシーンでは、男子学生がこれまで妄想の中で性の対象であった反戦集会の闘士である女学生を、大学の教室で実際に犯そうとしている。そこに見殺しにした大学教授の未亡人が現れる。彼らの妄想のなかで性の対象でもあったその女は突然、このように高らかに宣言する。
「日本人のふるさとは朝鮮です」
ヤマト政権の成立が朝鮮半島経由の騎馬民族とする考古学者江上波夫による説が演説され、万世一系の皇国史観に対する異論が述べられる。北方に騎馬民族が朝鮮半島に流入し、さらに彼らが日本に流入した。彼らは、もともと日本列島に存在した原日本人を列島の南北に追いやりながら「日本人」が形成された。皇国史観もまた日本の「春歌(猥歌)」のひとつである、ということだろうか。
4 マテリアルな響きとともに

「日本春歌考」で音楽を担当した林光は、マルクス主義を演劇に体現することを試みたドイツの劇作家、詩人、演出家のベルトルト・ブレヒトの作劇と音楽に共感を示してきた。そうしてオペラシアターこんにゃく座、演劇センター68/69(劇団黒テント)などで日本語によるオペラの創作を続けた。人間に対するあたたかな眼差しの中に、客観的な批評的態度を内在させ、多くの「ソング」を作曲した。
ブレヒトが共作した作曲家は、「三文オペラ」のクルト・ヴァイル、ハンス・アイスラー、パウル・デッサウなどだ。たとえば、あえて感情や言葉に適合しない旋律や曲想を用いて作曲する。その「違和感」のなかで歌う役者や観客は、役柄に同化したり同情したりして得るはずのカタルシスを得られない。かわりに人間社会や歴史に対する、客観的な批評性が獲得される(ということになっている)。こうして宗教や芸術の放つ権威や「オーラ」にこれまでのように無条件にひれ伏さないようになる。
私は「日本の夜と霧」など、1960年代の大島の初期の諸作にブレヒトの演出法との類似を感じるが、さらに理性のみでは解決しえない人間のさまざまな矛盾を描いている。「日本春歌考」の中では、若者たちや群衆を演じる役者たちによって俗謡や、軍歌、フォークソングがたくさん歌われる。林はそれらの歌の背景にあたる映画音楽をどのように作ったのだろう。
林は電子音のような冷徹な音色を響かせることで、社会への告発の態度をあくまで「クール」に貫いた。歌声と対置するように、新しい電子楽器のような音色によるヒステリックなフレーズが、繰り返し響く。しかしそれは西洋の古い鍵盤楽器チェンバロによるものだ。西洋近代を象徴するふくよかな響きをもつピアノが誕生する以前の、残響音の貧しいこの古楽器の鍵盤楽器は、ジョルジュ・リゲティやイアニス・クセナキスなど20世紀の前衛作曲家も注目し、まるで「新しい電気楽器」のように扱っている。
第二次世界大戦後のヨーロッパでは、そのように「新しい響き」として古楽器を用いるだけでなく、古楽そのものの復興も目指された。オランダあたりからは、ロマン派以前の楽器や奏法を復権し、再現することが試みられた。そこでは、西洋近代の個人主義が獲得したロマン主義的なオーラに隠蔽された音楽の構造を再現することが重視された。たとえば、チェロ奏者のアンナ・ビルスマは、楽譜を恣意的な解釈で装飾して自由に朗々と「歌う」のではなく、オリジナルの楽譜に忠実に、音符一つ一つをぼそぼそと「語る」ように演奏した。
林光と同年代、1932年生まれのカナダのピアニスト、グレン・グールドは単旋律の絡み合いを重視し、再構築した。ポリフォニーはバッハが対位法として体系化した、それ以前の芸術音楽で重視されていた技法だ。ピアノの豊かな響きを消滅させることでそれを実現させた。和音や残響を豊かするフッドペダルを用いず、チェンバロのように小さな音色でピアノを弾いた。グールドは、残響を増幅させるホールでのコンサート活動を中止し、レコードというメディアでそれを発表した。そうすることで唯一無二の存在が放つ生演奏の特権的なオーラの発生を自ら回避した。
古楽器や古楽の復興は、いわば西洋近代に対する反省を背景に生まれた潮流ともいえる。近代以降の個性に端を発する芸術家の精神性、前衛性は、戦争に対して何をもなしえなかった。そのことをふまえ、豊かさより貧しさが、メンタルよりマテリアルが重視された。 そのような姿勢は二次大戦後の現代芸術のメンタリティに通底するものだ。
そのような「アンチオーラ」な態度はアメリカのジャズでも、白人たちによる「クールジャズ」の中にも聴くことができる。たとえばピアノのレニー・トリスターノやサックスのリー・コニッツは、ジャズの本質であるアドリブに体現される黒人のパセティックな身体性が放つオーラを回避し、「クール」な演奏を目指した。黒人に対するコンプレックスから生まれた白人のオリジナリティの獲得を目指した試みだったともいえる。トリスターノはレコーディングされた自らのピアノの音から、豊かな残響音をカットし、あえて人工的な「貧しい音」をつくった。そのことによって音符の一音一音が残響に埋もれず粒だって踊り出すように音楽が転がってゆく。グールドとも共通する、霊性ををまとう身体のエロスではなく、マテリアルが放つエロスだ。
それらはミニマルミュージックや、音色を特性づける倍音属性を制御したシンセサイザーの無機音を用いる、後のテクノ音楽にも通ずるものがある。たとえば、YMOは、世界中の民族音楽的な特性である有機的な五音階(ペンタトニック)を、無機的なビートと音色を使って演奏した。社会主義的な「没個性」と資本主義の大量消費社会を同時にパロディ化した。まるで「人非人」を演じるように登場したYMOの1983年の「散開」の演出は、林光の盟友、演出家佐藤信によるものだった。他のアングラ演劇のローカルでドメスティックな身体性への傾倒とは一線を引いた佐藤らの黒テントは、日本においてブレヒトイズムを継承するだけでなく発展させた唯一の劇団とも言える。
このような音楽がそのまま社会に対する批評として体現される、ポストモダニズム的創作は、1980年代から90年代くらいを境に、じょじょに消滅していったように思う。理念が先立ち、少なくとも短期的にはその効果が得られなかったからであろう。社会主義体制の崩壊も影響した。資本主義社会に抗うオルタナティブな態度は、共産主義を目指す革命の合言葉でもあった「前衛」と、かつては親和性が高かった。前衛はアクチュアリティを失った。マテリアリズムの美は、純粋に音楽、音響的な美と認識されながらアンビエントミュージック(環境音楽)やエレクトロニカミュージックとして展開した。
5 フォークソング(民謡)にならない声

映画のタイトルとして援用された「日本春歌考」の著者、添田知道の父添田唖蝉坊は明治大正期の演歌師であり、社会批判とユーモラスな風刺精神でたくさんの歌を作った。それは旧来の共同体の歌としての民謡(フォークソング)とは異なる歌だ。シンガソングライターの祖でもあり、後の日本のフォークシンガーにも大きな影響を与えた。読み人知らずのローカルなフォークソングは、1970年代よりシンガソングライターによる個の音楽に変容した。作り手である個がメディアを介して発信し、聴き手である個が共感する。それが広まって、新たな意味での「フォークソング」が成立した。
私が中学生の頃に好きになった歌は、友川かずき(現カズキ)や三上寛という「フォークシンガー」といわれた人の歌だった。出身は秋田、青森と、東北のフォークロアが、それぞれ異なる感覚ではあるが詩や歌唱に色濃く残る。しかし彼らの歌は、土着の民謡のようにみんなで歌う歌とはいえない。囁くような静かな歌も多いが歌の枠を超えるような絶唱も多かった。「想い出は標準語でやってきた」。三上寛の「BANG」という曲の歌詞の一節だ。標準語の50音の表記にはまらない方言の響きが、言語に収めることができぬ感覚や感情に突き刺さって、心が震えた。
友川の「一人盆踊り」という名前の曲がある。打楽器の石塚俊明や、私の師の一人であるコントラバスの故吉沢元治がエフェクターをたくさん使ったホームメイドエレキコントラバスで即興演奏し、そのカオスな音空間のなかで友川が言語から逸脱して意味を聞き取れないくらいに絶唱する。もちろんいわゆる現実の「盆踊り」とはまったく異なる音楽だ。みんなで合わせて歌い踊るものではない。一人一人の別々の盆踊りの集合だ。かつての農村や漁村の閉鎖的な共同体のなかに孤立する個(一人)の妄念の乱立を体現するようなアンサンブル(共同体)であるようにも思う。三上寛も山下洋輔らのフリージャズや灰野敬二らのノイズアヴァンギャルド音楽と「フォークソング」を融合させてきた。
三上や友川の詩や歌は圧倒的な個のオリジナリティが先立ち、詠み人知らずによる「フォーク(民謡)」とは遠い。詠み人知らずによる「フォーク(民謡)」とは遠い。むしろそれと対立する、個(性)に立脚した芸術とよばれるものの形に近い。私はそこに、共同体の歌としての民謡の裏に潜む個の声を聞いたような気持ちで、強く共感を覚えてきた。
一方で当時の私が友川や三上ほどには熱中しなかったのが、ほぼ同年の生まれである高田渡の歌だった。岐阜生まれだが8歳で家族で東京に移住して貧困生活を送った。高田渡の曲は、たとえば輸入されたアメリカのフォークソングであるカントリーソングやトーキングブルース「調」そのままで、ある意味凡庸だ。友川や三上も楽曲自体は似たような曲が多いが、歌声のダイナミックレンジがそれぞれの曲に大きな陰影をつける。高田は、絶叫したり、囁いたりはしない。そもそもの出自もあるが、高田は方言も用いない。歌詞もおそらくはあえて、自ら作詞したものでないものを積極的に歌う。辛辣なものも多いが、歌い方は気負いなく、気ままだ。
高田渡は「芸術」になることも「個性的」であることも意図的に避けたように思う。凡庸であることによって、民謡の本質であるローカリティを逆説的に体現している。それが民謡=フォークソングの本質だからだ。おそらくいくらその差異をマニアが力説しても、そうでない人が聴けば、たとえば古いブルースのようにどの曲も誰が歌っても似たように聴こえるかもしれない。日本語を理解しない人が聞けばなおそうであろう。実際に、三上や友川は、2000年代ごろから、ヨーロッパを中心に海外からの評価が高まっているが、海外で高田に対して同様の声は聞かない。しかしそもそも民謡とは遠くの他文化圏からみればそのようなものだろう。「商品」や「作品」として楽曲の個性や多様性を明らかにする必要などないからだ。
高田は、民謡の原義である「民」「衆」の一人としての「個」を体現していたのであり、現代においては、結果的にそれがアウトローで逆に個性的だった。商業とも芸術とも、民族的なルーツや故郷とも、共同体ともはなれ、「個」人の集合体である社会から投げ出されて、宙に浮かんだままのその声の「ざらつき」こそ平板な社会に浮き立ち、かえって類い稀なる個の存在なのではないだろうか。
みなで歌う「フォークソング」とは異なり、高田渡の呟くような歌も、友川や、三上の絶唱と同じく、たとえばコンサートで反戦歌のように声を一つにして斉唱したりするのには本来向いていない。友川や、三上の歌は、歌手本人の声の生々しさから離れることができず、日常の中でも歌うことができない。しかし高田の歌は、日々の暮らしの中で、それぞれが歌ったり呟いたりすることはできる。高田はそのような歌のあり様を、現代の「民謡(フォーク)」であると捉えていたのではないだろうか。「日本春歌考」で、学生のパーティーで若者が声を合わせて歌われていた、ウディ・ガスリーの「その土地は誰のものでもない(誰のものでもある)」という意の歌がある。高田の歌声も、まさに「その「誰のものでもない歌」の声の一つだ。だからわざわざ絶唱して声を際立たせて主張することがない。
友川や三上は民謡に収まらなかった民のなかの個の声が憑依して乱れる。他人には歌うことができない歌だ。それをともに歌い空間を一にするには、別の「独り歌」(演奏)を同時に響かせるしかない。それが先述した友川の「一人盆踊り」の「アンサンブル」だ。私自身はやはりそのようなアンサンブルこそ私の「夢の歌」の交響のビジョンに近いのではないだろうかと思っている。
しかし彼らの世代とは異なり、1975(昭和50)年生まれの私のような世代は、そもそも個に先立ったローカルな共同体は崩壊しかけている渦中に生まれ、現在に至る。しかも私は東京に生まれその近郊で生きてきた。かつて生の基盤であった共同体から分断された個の孤独と自意識にまみれたまま死を迎える準備が私自身にはまだない。だから、あらためて血縁、地縁のある共同体や信仰のある生活自体がどのようなものであったか、時空を伝わってきた民謡や口承芸能を頼りに、知る必要があるように思った。私には、友川や三上、まして高田のような「フォークソング」を「つくる」ことはできないだろう。しかしそこからさらに「独り歌」を想像し、その交響を「夢の歌」として表してみたい。
6 韓国民衆芸能のダイナミズム
ユーラシアンオペラとしてすでに進行中である前作は、中露国境の少数民族の運命を描いた原作小説のストーリーは追わず、むしろ時代や国や背景の異なる一見関連性もないさまざまな詩を交錯させた。物語劇ではなく「詩劇」として創作した。しかしこれから創作する新しい作品では、深沢の小説や大島の映画のように、物語の筋を追いながらで演じる「歌物語」を創作したいと思った。そこで物語じたいの機微を演じるのではなく、むしろ背景への考察を複雑に交錯させてみたい。だから素材となる物語自体は、誰でも知っているようなシンプルなものが良いと思った。それは、演じる私たちが最も身近な日本の説話や民話が良いと思った。その背景にある歴史や、内在するフォークロアを、海外のそれらとも関連させ、いずれはユーラシアンオペラとして成立させてみたかった。
まずあらためて日本の民謡や口承芸能を探しもとめたが、なかなか創作に適したストーリーがみつからない。そんな過程で、まさにユーラシアンオペラの創作ビジョンに繋がるような興味深いエピソードに出会った。
19世になるとヨーロッパの民俗学者や民族学者が未開の地である極東シベリア、韓国、北海道、日本を調査した。あるフランス人が日本と韓国の農村を訪れたときに、かならずフランス国歌を歌ってみた。すると日本人は恐れ、恥ずかしがって家のなかに隠れてしまったそうだ。韓国の農村ではそれを聴いた人たちが仕事の手を止めて、家に戻って太鼓等の楽器をもって叩きだして一緒に演奏した。
韓国の庶民には、農業祭事などで用いる踊りを伴う打楽器合奏の習慣があり、旅芸人がさらに専門的な芸をみせた。後の植民地時代には、日本の民俗学者たちが各地のそれらを「農楽」と総称した。ついでながら「民謡」という言葉も森鴎外がドイツ語から翻訳するまで存在しなかった総称の造語だが、それが韓国に渡り「そのまま「民謡 민요(ミンヨォ)min-yo」と呼ばれる。
楽器を伴う習慣のある韓国の民謡と比較すると、日本の農村では民謡、俗謡に楽器が伴わない。日本の農民が「隠れてしまった」のは、気質の問題以前にそもそも太鼓も含め、楽器を個人宅で所有していることが稀だったという理由もあるだろう。日本では江戸期には芸能や説話の語りに用いられてきた琵琶がすたれて、かわりに三味線がその伴奏楽器となってゆく。
江戸時代の町人文化の芸能として、端唄、長唄、小唄等の歌と三味線の 芸や、胡弓(明治以降尺八がとって替る)、琴などとの「三曲合奏」、浄瑠璃から文楽などの「室内楽」が生まれ洗錬された。江戸、大坂の町人文化、屋内芸である。それらは跳躍的要素を生みにくく、どちらかといえば静的なものに洗練されてゆく。また、そこにある楽器を伴う音楽が迅速に農村に流布することはなかった。それに対し韓国の民衆芸能は、後に述べる賤民階級による野外のダイナミックで賑やかな芸能の要素が、民衆芸能としても農村に保たれながら発展した。
民族音楽学者の小泉文夫が朝鮮半島は馬の歩行の3拍子、田植えなど農耕の日本は2拍子とあえて簡略化してまとめた。農耕の盛んな朝鮮半島の南部地方も考慮すると躍動的な理由をそれに限ることはできない。しかし北方の遊牧の躍動的な馬文化に近しい朝鮮半島の伝統音楽の3拍子の優性はたしかに認められる。私は両国の伝統音楽の躍動性の差異に、近世時代のそれぞれの仏教のありかたも影響を及ぼしたのかもしれないと想像した。
近世を成した李朝は仏教を保護した高麗の権威を排除するため、仏教を廃止して儒教を奉じた。しかしそれがたちまち生活の根底まで変えてゆくとは思えない。すでに土着化していた仏教やシャーマニズムの排除に抗う心や身体が、音楽の躍動性に民衆の芸能に発露するだろう。
日本の近世では寺子屋や寺請制度により、それ以前から存在した質素で禁欲的な仏教の教えや死生観が、民衆の暮らしに広まっていた。民俗芸能は仏教のもつ道徳的な諦念観により、朝鮮半島ののような躍動感が生まれにくかったのではないだろうか。仏教が推奨された江戸期に庶民への布教に用いられた御詠歌のような歌唱文化も、ダイナミックな賑やかさとは遠い。
日本の場合、仏教に関わる祭儀でも、躍動的な舞踊性は希薄だ。一遍上人の「踊り念仏」、さらにそれが歌謡化した念仏踊りなどがより郷土芸能化し、盆踊りの楚になった。そこでは太鼓や鉦も用いることもあるが、基礎ビートの単位が明確ではなく、比較的単調な2拍子系のリズムが直線的に持続する。そこからは起伏のあるリズムや跳躍的な舞踊は生まれにくい。 韓国の三拍子にポリリズムが重なり、さらに大きな塊となって円環するような躍動感がない。韓国ではそれを表現する舞踊が複雑な打楽器文化と一体となって発展し、それが民衆の主体的な娯楽となってゆく。ビートの円環は廻り続ける四季やそれに対応する農作業にも呼応する。日本でそこに伴う娯楽は、神々の来訪を待つことに重きがおかれる。いわば受動的なのだ。田遊び、里神楽など、神事などの予祝行事は、ゆっくりとした舞や所作で演じ、さらに禁欲的な仏教信仰も習合し、厳かさもある。そこからも打楽器を中心にした娯楽性の高い音楽、舞踊文化が発展することは想像しにくい。歌唱についても、祝詞や、七五調で平坦に歌われる仏教的な唱和が基盤となり、歌謡性に乏しい。こう書いていると、韓国を礼讃し、日本を貶めているようでもあるが、そうではない。私は海を隔てた隣国との音楽文化の差異こそ興味深く、民族ここえた人間の、民衆の原像を、その表裏にこそ求めたいのだ。そこでまずは隣国の音楽のダイナミズムの理由をもう少し知りたいと思った。そのうえでさらに比較すると、日本の民衆文化の深層にも接近できるように思えた。
近世の李朝時代に起こったという遊芸の民、最下層の賤民の身分である韓国の芸能集団男寺党(ナムサダン)は、基本的に男性のみで構成された。だいたい 一集団50人ほどを擁し、かなり大きな集団規模といえる。これほどの大きい移動芸能集団は日本では存在しなかった。男色(集団内で職能や役割に応じ、ペアをつくる)の要素も強い。「ピリ」とよばれる初入者は稚児として尊重され、各地で身売りされて、「花代」(祝儀)も収入源となった。さらなる人員確保のために、農家の「口へらし」も利用して各地で、スカウトしながら旅を続ける。ほかにも集団の旅芸人は、女性で構成され花代を稼いだ女寺党(ヨサダン)や、寺社と結びついて門付してまわる乞粒牌(コルリッペ)などがいた。そのような専門の芸能集団がやがて各地の「農楽」を形成して行く基盤になった。各地の農楽の要素やシャーマニズムを発展、統合させ、舞台芸術化させた現代の打楽器合奏であるサムルノリやシャーマニズムの音楽などにもその多様性が反映される。
1392年(日本で言えば南北朝が統一された室町時代)から1910年の日本統治まで長く続く朝鮮王朝(李氏朝鮮)時代の身分制度は階級も細かく定められるが、大きくは租税義務のある良民と賤民とに分かれる。 良民は両班(高級官僚)中人(下級官僚)常民(農民、商人)。賤民は職能により奴婢、僧侶(崇儒廃仏政策のため)、巫堂(ムーダン=シャー マン)、喪輿かつぎ、妓生(芸妓)、白丁(屠殺業)、工匠(職人)、広大(クァンデ=芸人)などがあった。時期によって異るが、人口比率では約3~4割が賤民階級に属していたそうだ。そのなかに、芸能に関わる 、男寺党(ナムサダン)、女性が約8割を占めるというムーダン、、パンソリを歌唱する広大も存在した。
日本では江戸時代の封建社会において賤民階級にあたるのが約1〜3パーセントだったといわれる。多くの芸能者が属するこの階級の人口比率がの点から比較しても、朝鮮半島の芸能の多様性を想像することができる。芸能集団男寺党(ナムサダン)の芸も六種もの演目、プンムル(風物、農楽)、ポナ(皿回し)、サルパン(曲芸)、オルム(綱渡り)、トッペギ(仮面劇)、トルミ(人形劇)で構成される。
広大が語り歌うパンソリによって17世紀くらいから民衆に広まった物語は、身分制度にくるしめられた人々の鬱屈を晴らすような内容も多く、過激な批判とエロッティクな表現もまじえてバイタリティーがあるものだ。禁じられている民間の仏教やシャーマニズム的要素も織り込まれる。いっぽう両班階級である貴族も喜ばせる必要があり、内容もそれぞれにおもねって儒教、漢文の教養を織り込むことも多かった。彼らはその近くに定住するようになった。西洋の小説や戯曲にも「庭師」、つまり貴族の領内で仕事をする下賎な立場の職人が、マージナルな存在として物語の鍵を握ることがある。さまざまな階級間の往来で形成されるパンソリの語りや歌は多様な価値観や表現がいりまざる。そのために一つの演目は4~8時間にも及ぶ。李朝の当初両班の官僚社会では旧来の漢字が用いられたが、15世紀に完成したハングルとの併用も進み、パンそりの代表的な演目も19世紀くらいには文字を用いて書物化されてまとまってゆく。
パンソリのように過剰なほどに抑揚をもつ歌謡性の高い口承芸能が、日本で親しまれてきたとはいえない。たとえば説経節、祭文なども歌謡性も含むが、歌唱というより語り芸としての要素が強い。さらに現在の日本ではそれらは、どちらかといえば昔話や童話、小説などの書物、読み物として認識されている。それに対し、1970年代の韓国の民主化運動における民衆の伝統文化の見直しが大きいとはいえ、「春香伝」や「沈清伝」などのパンソリのストーリーは文学化されつつも歌唱芸として現在も愛されている。
公共教育機関はもとより、現代でも各地の民俗芸能伝承サークルは多いというし、ソウルの中心街、鍾路(チョンノ)エリアには、パンソリや打楽器を学ぶ音楽スクールも多数みることができる。
イム・グォンテク監督の映画版「春香伝」(2000)では、はじめ現在の学校の伝統芸能鑑賞会のようなところで、パンソリが語る場面から始まる。そのようなメタ構造は、伝統芸能として形骸化、古典化されていることに対する皮肉のような意味合いもある。しかしその後、引きずりこまれるように物語の世界へと誘う魔力を、この芸能は持ち続けている。現在日本の伝統文化と称される芸術はそのほとんどが、宮廷、武家文化に大きく依存しているのに対し、韓国では伝統文化のなかに民衆の姿が現在にまで生々しく息づく。
7 ユーラシアンオペラとしてのパンソリ

金樽美酒千人血 金の樽に入った美酒は、千人の血からできており
玉椀佳魚萬姓膏 玉椀にある美味い魚は、人民の油でできている
燭涙落時民涙落 ろうそくから蝋が滴るとき、人々の涙も滴り
歌舞高處怨聲高 歌舞の音楽が高く鳴り響くとき、人々の怨嗟の声も高くとどろく
パンソリ「春香伝」でもよく知られる漢詩の一節だ。新たなユーラシアンオペラは、日本の近世の農民や身分制度の外にある人々の暮らしや死生観を探りながら、民謡にもなりえなかった「夢の歌」を想像することから民衆の原像を求める試みだ。民話や説話を考察してゆく過程で、日本ではなく、韓国の口承芸能「春香伝」に出会った。
権力者と民との間に顕在化する韓国の伝統芸能ダイナミズムに、まず向きあってみたいと思った。そうして民衆像への視野を広げたうえで、あらためて日本の民衆の原像に近づけると思った。「春香伝」を創作のベースにすることを私は選んだ。
むろん私たち日本人が、パンソリのように感情を駆使してこの物語を演じたり、伝統芸能の力強さを体現することはできない。原語も理解しない。だからまず、翻訳された異国語のテクストであることを前提に、できるだけニュートラルにそれに接するということを大事にしたい。複雑な関係性も持つ隣国の民衆芸能を安易に換骨奪胎し、双方の文化を表層的に「融合」することもためらわれる。それについて考えることじたいがこの創作なのだ。ゆえに作品のタイトルは深沢七郎の小説と、大島渚の映画作品に倣い「春香伝考」とした。そこから生まれる現在の歌や踊り探すのが音楽詩劇研究所のユーラシアンオペラだ。

「春香伝」は、韓国の妓生(キーセン:娼婦)の娘春香(チュニャン)と両班の息子夢龍(モンニョン)による、身分を越えた壮烈なラブストーリーだ。パンソリが歌い、泣き、笑いながら聞き手とともにともにつくりあげてきた物語であり、李朝時代のきびしい身分制度の中に生きる民衆の声だ。
口承芸能である「春香伝」は唄い手によって無数にヴァリエーションが存在する。
そのヴァリアントの一つとして、日韓や北方諸民族、琉球との関係を史実や想像に基づきながら、ユーラシアンオペラの創作を目指し、以下のような設定を設けた。恋におちた不屈の娘と官僚の息子の夢龍(モンニョン)が、階級差を乗り越え、別離のあとめでたく再会を果たし、都へと旅立って物語は終わる。、この二人の子孫が、現在のサハリンで暮らしていると設定した。。第二次大戦後もそのままサハリン島に暮らし続ける「在樺コリアン」である。「春香伝」のストーリーを演じ終えたパフォーマーたちが佇んでいると北の方から声が聞こえる。
舞台は、 後に春香の声を演じる三木聖香の、「不思議な言葉」を呟くような歌声から始まる。
オロ タ ネスン (その家に)
ラマッカラカムイ(命を作る神様が)
レ ホッネ シンタ (60のゆりかごを)
シロロ ワ アッテ(上座に吊るし)
レ ホッネ シンタ (60のゆりかごを)
シウトゥル ワ アッテ (下座につるし)
エロンネ ワ (上座の方に)
シキル キ コロ (ふりむいては)
レ ホッネ シンタ( 60のゆりかごを)
イラムノ スイエ (いっせいにゆらす)
エウトゥンネ ワ (下座の方に)
シキル キ コロ (振り向いては)
レ ホッネ シンタ ( 60のゆりかごを)
イラムノ スイエ (いっせいにゆらす)
ネノ イキ コロ (そうすると)
イキロク ポンペ (その赤ちゃんたちの )
ウ チシカラ ハウエ (なく声が)
アイヌ語の子守唄だ。「声のゆりかご」の中でパフォーマーたちは眠りについていたが、目覚めた亡霊のように舞台上に現れる。
異国の伝統文化を演じるという前提を観客に明示するため、彼らが「春香伝」のなかで登場する娼妓(キーセン)の源氏名を「配役」として与えられる場面から始まる。パンソリというと現代では一般的にどちらかといえば女性の唄い手を想像する。しかしそれは元来男性の芸能であった。男性の諸芸を習得した彼女らがさらにこの芸を発展させた。以後、劇中劇として「春香伝」のストーリーが、歌物語のかたちで進行する。
春香は舞踏家の亞弥が演じ、その声は三木聖香が歌う。夢龍はダンサーの三浦宏予が演じ、その声は坪井聡志が歌う。
ストーリーテリングとしても機能する歌は私が日本語で作詞したオリジナルの曲だ。2015年の「死者のオペラ」と同じく、あらゆる民族音楽的特性を極力排除して作曲した。しかし娼妓を演じるコロスたちが歌う歌の通奏低音には、あえて日本の民謡を用いたいと思った。それも歌詞ではなく囃子詞の部分だけだ。それらは、オノマトペだったり、元の意味が変容し、ときに無意味語となってしまったような「音楽語」ともいえる。
琉球、アイヌ、サハリン、日本と様々な要素が絡み合いながらユーラシアンオペラ「春香伝考」はそれらの背景を伝統音楽とは無縁の音楽で演じながら「歌物語」の形式で進む。以下、その背景にある要素のいくつかについて紹介したい。
8「安里屋ゆんた」と春香伝

娼妓の一人が、白鳥加奈子が演じた春香の母「月梅(ウォルメ)」だ。その娘が春香(チュニャン)だ。私は月梅を琉球から、潮にのって済州島に流れ着いた女と設定した。
沖縄諸島の民謡「安里屋ゆんた」は「春香伝」と少しにたストーリーをもつ。16世紀、八重山諸島の竹富島の娼婦、絶世の美女「くやま」が、琉球王国から人頭税のとりたてにきた役人(目差主)から妾になることを要求される。しかし「くやま」はこれを拒否する。このような反抗はゆるされることではなかった。それゆえにたくましさが讃えられる。おもしろ可笑しく男女で歌をかけあい、島の重労働の慰めでもあったという。それが琉球全般で歌詞を変えながら広まってゆく。きっと世界中にたくさん類型がある実話や物語だろうが、春香伝にもにも共通する権力に屈しなかった「烈女」の伝説だ。
韓国に漂着するとは無理のある設定のように思われるかもしれないが、たとえば済州島などにも、琉球から黒潮で流れ着いた人々がおり、文化の流入もみられるとのことである。
1 安里屋のクヤマによ あん美らさ生りばし
(あさどやぬくやまに あんちゅらさまりばし) またはーりぬちんだらかぬしゃまよ
2 幼しゃからあふぁり生りばし 小さから白さ産でばし
(いみしゃから'あふぁりまりばし くゆさからしるさしぃでぃばし)
3 目差主の乞よたら あたりょ親の望みよた
(みざしぃしゅぬくゆたら あたりょやぬぬずみょた)
4 目差主や 我な否 あたりょ親やくりや嫌
(みざしぃしゅやばなんぱ あたりょややくりゃゆむ)
5 何故でから否です 如何でから嫌です
(なゆでぃから んぱです いかでから ゆむです)
6 後のこと思いど すらの為考やど
(あとぅぬくとぅ'うむいどぅ すらぬたみかんがやどぅ)
7 島の夫持ちゃばど 後の為あるです
(すまぬぶどぅむちゃばどぅ あとぅぬたみ'あるです)
メロディが良く知られる沖縄諸島の民謡「安里屋ゆんた」の歌詞だ。七番まで書いたが、これは延々と続く歌詞の初めのほうのみだ。舞台では白鳥加奈子が、例外的に民謡の旋律を歌ったが、歌詞は琉球語ではなく日本語翻訳を用いた。
同様に沖縄には伝統的な琉歌の定型詩の韻律八・八・六のリズムがある。詠まれるだけでなく、歌われる歌である琉球民謡にもその韻律は用いられる。平仮名で書かれた琉球言葉の歌詞を声に出して読むと、習わずとも身体に染み込んだ七五の調べに慣れた感覚でいえば、歌になりにくいように感じられる。大和言葉にすれば、本来の響きは失われるが、あえてその違和感も含め、和三味線の伴奏による日本語で、琉球民謡を歌った。違和感は、むろん一概に否定するものではなく、新たな美を生み出す可能性も含む。むしろそのことにについて考える契機にもなる。この作品名に「考」をつけたのは、たとえばそういう理由だ。
琉歌は幅広く民衆にも詠まれ、女性も書いた。恩納なべ、吉屋チルーなどが有名で、瑞々しい恋心や、政府への反発も描かれている。
これは琉球王国の娼妓であった歌人、「くやま」より約100年前を生きた、チルーによる琉歌。8歳のときに那覇の仲島遊郭へ売られていく途中、比謝橋で詠んだ悲歌だといわれる。
恨む比謝橋(ひじゃばし)や 情け無(ね)ぬ人の
我身(わみ)渡さと思て 架けて置(う)ちぇら
流れゆる水に さくら花浮きて
色美(いろちゅ)らさあてど 掬くてみちゃる
寄る辺無(べね)ん物や 海士(あま)の捨て小舟
着く方ど頼む 繋ぎたぼり
たのむ夜や 更けておとずれも 無いらぬ
一人山の端の 月に向かいて
本作ではこの琉歌を日本語訳を歌詞とし、琉球音楽の特色を用いずに新たに作曲し、コロスが合唱した。
「寄る辺なきものは 漁師の捨てた小舟のようなもの どうぞれをつなぐように 私をつないでおいてください それがだめなら サバニを漕いで行く」
「サバニ」とは琉球ことばで小さな木舟のこと。
この合唱には通奏低音に秋田の最上川舟唄の船頭の囃子詞「エサノマッガーショ エンヤコラマーガセ エーエヤーエーエヤーエーエ エーエヤーエード ヨーエサノマッガーショ エンヤコラマーガセ」を重ねた。
私たちは稽古中、日本列島のさまざまな民謡の囃子詞を声に出してみた。不思議な響きの囃子詞が無数にある。
「ソーイ」(江差追分)「キタカサッサ」(秋田音頭)「ヨー オーホイ おどま いやばお どま しおる こま」(稗搗節 ひえつきぶし)ホーハエ・ホーハエデャ・ナーエ・アナーウアウヤー(ホーハイ節)「ナー ナンチャラホイ ヨイヨイヨイ あわしょ」(木曾節)「かなかい マドのサンサ・デデレコデン ハレのサンサ いくせ ササラ やしゃ男」(コキリコ節)「シュラ シュ シュ シュ」(金比羅船々こんぴらふねふね)
ナニャド ナサレテ ナニャドヤラ
ナニャドヤレ ナサレデ ノーオ ナニャドヤレ
ナニャドヤラヨー ナニャド ナサレテ サーエ ナニャド ヤラヨー
ナニャド ナサレテ ナニャドヤラ ナニャド
これは東北、旧南部藩周辺に伝わる盆踊り。これがだいたいの歌詞なので囃子詞ではないが、ヘブライ語説もあるそうだ。
民俗学者の谷川健一は、文字として残され古事記などから日本文学の起源を辿る限界から、琉球諸島の古代からの伝統である「草木言問う」アニミズム的な短い「唱言」にも日本の古代歌謡の始原を求めた。日常語とは異なる言葉を「唱える」という行為そのものが歌の原初であるおうにも思える。世界各地の民謡の囃子詞の中にもそのような痕跡が残っているに違いない。
9 韓国のロミオとジュリエット 「春香伝考」ストーリー
妓生の娘春香(チュニャン)と両班の息子夢龍(モンニョン)は、村祭りで出会う。ブランコをいきいきと漕ぐ娼妓の娘の春香を見初めた夢龍だが、身分違いの壁を超えられず、なかなか口説き落とすことができない。
その後、はじめて枕をともにして結ばれる場面では、舞台中唯一の韓国語を用いた。日韓の伝統芸能の踊りや音楽の要素や韓国語も本編では用いない本作の、二つの例外のうちのひとつだ。伝統芸能の要素を使わないので、出演の予定がなかった韓国打楽器のチェ・ジェチョルに特別に舞台に登場してもらい、韓国語のをしてもらった。このエロチックな部分を「教科書」のテキストとした。
韓国の娼妓を演じる旅芸人という設定である男女のコロスたちが、チェのコミカルな進行のなかで、今聞き覚えた韓国語をたどたどしく反芻する。
あなたは何を求めているのか
あなたが何を望むのか
蜜をたらし
あまい蜜をたくさんかけて 一気に飲むんだ。どうだい?
それは嫌
では、何がよいというのだ
あなたは何を望む
では甘いメロンをはどうか?
いいえ それも違う
あ・あ・愛しい人
ならば、何が欲しいのか?
何が食べたい?
杏子はどうだ?
つわりに効く
いいえ それも違う
では何が欲しい?
あなたは何を欲している?
林檎はどうだ?葡萄もあげよう
石榴(ザクロ)はどうだ? 柚子もあげよう
これもわたしの愛だ
愛しき人よ
なんたることよ
愛して止まない
あ・あ・愛しいあなたよ
チェ自身は朝鮮学校で朝鮮語を学び、その後彼自身の創作活動の中で、あらためて現代の韓国語を習得した。学校で習った言葉が、彼自身の家族のルーツである韓国の現代の言葉として通用しないことに悩み苦しんだ時期があったという。彼が習った言葉は、たとえば日本語でいう「〜でござる」のような言葉使いになってしまい、韓国で笑われたこともあったという。恥じらいや悔しさが失語状態を生む。在日韓国人であるチェの言語習得過程は、自身のアイディンティティに関わる繊細なことだ。その葛藤を伝統芸能の習得やさまざまな出会いを通じて克服してきたことを、今は笑いながら話してくれるが、、私はためらいつつ舞台上で言語教師を演じることをお願いした。
快諾し、パンソリ「春香伝」の中でも聞き手を楽しませながら最もコミカルに語られるこの場面を、楽しげに演じてくれた。舞台上で見ていて、笑いながら少し涙が出た。これが私たちがいまここで演じることのできる、パンソリだったのかもしれない。彼とパンソリとの私には意外だった関係は、のちに第3部で述べる「さんしょうだゆう」の創作過程で聞いた。
「授業」が終わり、結ばれた若い男女の永遠の愛を誓うアリアが三木と坪井によって歌われた。しかし父の任期に伴い、夢龍は都に向かう。永遠の愛を誓った二人ははなればなれになる。春香はそれを信じて夢龍を待つ。
春香の声を歌で演じる三木が三味線で弾き語る、この舞台のなかで伝統音楽的な要素を直接的に用いたもう一つの例外的な場面だ。歌うのは、春歌「よさほい節」の「本歌」といわれる数え唄だ。
1 ひとり淋しく残るのは 私ゃ死ぬよりなおつらい
2 ふたりは遠くへだつとも 深く契りし仲じゃもの
3 みんな前世の約束か ほんに浮世はいやなもの
4 よもや京都にいたとても ずいぶんお体大切に
5 いつものお言葉末永く 忘れてくれるな願います
6 むりな願いかしらねども 足ふみしゃんすな花の街
7 ながめしゃんすな迷うても 賀茂の育ちの京おんな
8 やはりかわらぬその心 勉強しゃんせよ末のため
9 こよい別れのこの野辺に 私ゃいつでも迷いきて
10 とおい京都の空の雲 一人淋しく眺めます
この地に赴任した官僚たちは、春香の美貌を聞きつけて我が物にしようとする。しかし夢龍への貞節を守ることを主張して従わない。そのため鞭で打たれて責め苦にあうこのシーンは、権力に屈さず愛を貫く「烈女」伝としての名場面であり、パンソリ演者の腕の見せ所だ。このシーンに、大島渚の映画「日本春歌考」で通奏音のように用いられた数え歌を用いた。三木の歌う本歌に重ねてコロスたちが替え歌の春歌をだんだんと声を大きくしながら歌い、にじり寄りって舞踏家の亞弥が演じる春香を責め立てる。
一つ出たホイのヨサホイノホイ....
投獄された春香は夢龍の言葉を信じるが、絶望し、衰弱し死を待つのみだ。
そこへ、夢龍が戻る。しかし、投獄された春香をそこから逃し、救い出すことは困難だ。夢龍は一計を謀る。乞食に扮して官僚たちの宴に侵入する。賎民らしからぬ見事な漢詩(*第七節冒頭)を書いて驚かせた。その内容は民をいじめる彼らを告発するものだった。宴は大混乱となる。春香は処刑される心構えでこの場に目隠しされて現れる。計画通り役人たちを屈服させ、この場を収めた夢龍は、春香の目隠しをとる。春香の目の前に夢龍が現れた。永遠の愛を誓ったアリアと同じ旋律が歌われる。
作詞 作曲 河崎純
1(春香)長い夢から いま目を覚まし
(春香)わたしの歌声 戻ってきたわ
(夢竜)春風 香る あなたの声で
(春香 夢竜)黄昏し広場に 光り与えん
2(春香)あなたの歌が 生きる力を
(夢竜)あなたの愛が わたしに歌を
(春香 夢竜)その歌は わたしたちのだけのものではない
(春香 夢竜)まだみぬ世界に 声響かせん
3(コロス)南の島から 声が聴こえる
(コロス)北の島からも 声が聴こえる
(全員)わたしたちは これから 何処へゆくのか
(全員)愛の歌探す 旅に出よう
再会を果たした二人は幸せに都ソウルへと旅立つち、「春香伝」は終わる 。演じ終えた旅芸人たちがパフォーマーたちが舞台に佇んでいる。
その中で、舞台冒頭でアイヌ語で歌った子守唄「60のゆりかご」の日本語訳に、私が作曲した曲を、三木が歌う。アイヌ伝統音楽の要素はまったく含まない。
「この世界に 世界の上に 降ってきて そこから生まれるのが 眠りというものです あなたはそれを聞きたくて 啼いているのですから 私が聞かせてあげますよ そう歌うんだと 」
パフォーマーたちは、北方少数民族の喉歌や口琴を奏でながら、亡霊のごとく蜃気楼に消える。姿を消した先は、現在二人の子孫が暮らしているサハリン島だ。パフォーマーたちは舞台裏で口々に韓国語で呟いている。
アリラン峠を越えていく。風波荒い海を渡って、恨の多い南樺太に 徴用で来た
鉄の壁は高くなるばかり、恋しい故郷への道は遠ざかる)
政治開放後、太陽は姿を見せ、私達の暮らしには良いことが多い
アリラン峠を越えていく。私を 捨てて行く貴方は十里も行けず足が痛む必ず帰ってくると誓って
あの人は、涙を流し 緑をかきわけ アリラン峠を越えていった
悲しみの時が流れ 季節は巡りゆけども あの人は帰らない
そして、悲しい歌だけが アリラン峠を越えていく アリラン、アリラン アラリヨ (作詞 鄭・テシク)
特別出演の打楽器奏者、チェ・ジェチョルが舞台裏から、韓国の銅鑼(チン)を静かに奏でて「春香伝考」が幕を閉じる。チェがこの舞台で奏でたのは、この一打のみ。
10 和人のユーカラ/サハリンのアリラン

私たちの「春香伝考」では、めでたくソウルの都に旅立った二人の子孫が現在サハリンに暮らしている設定で、そこに「夢の歌」を響かせようと想った。そのように着想したのには、「楢山節考」の作者の深沢七郎の短編小説「和人のユーカラ」と、かつて樺太時代に実在した、さまざまな北方の原住民族の人々が集められた「オタスの杜」という人造の村を知ったことに起因する。
「和人のユーカラ」は人種差別の多重構造を描く不思議なストーリーだ。
一人の青年が、新しい自動車道路建設反対の立場の人びとの調査のために北海道に訪れた。その時、大雪山のふもとで出会った不思議な大男は、終戦直後の復員軍人のような服装の、彫りの深い顔、太い眉毛の「アイヌのような」な男だった。二人は不思議な会話を続けた。タンポポの花をみて男は「シャモの言葉で"幽霊"という意味です」という。「シャモ」という敵対心もこめて和人のことをよぶアイヌの言葉をつかったので「あなたはアイヌか」と青年がきくと、男は答えともつかない、よくわからない言葉でなにかを喋るのみ。
「タモの木の枝と、枝の間は俺のもの」
「シャコタンの島は、持って歩けない」
「ノボリベツの煙は 俺のものだ 」
「太平洋の水は、持って歩けない」
などと不思議なことを言うので、青年が「歌のようですね」ときくと、これは「ユーカラだ」という。ユーカラとはアイヌの歌うように語られる口承叙事詩だ。
「ユーカラは、「言葉に現せない歴史」だから「歌になる」のだ」
と言う。大男は、シャモにもユーカラがあるが、それを歌う時の手つきや顔つきが恐ろしい、「バンザイ」と両手を揃ってあげる様や、「大勢で手を叩く音」が無気味だ、シャモは死んだ人を持ち歩くことは、「死の約束を諦めさせる呪文で、死の歴史を意味づけるための歌だ」とも言う。青年はそれは「経文といい歌うとはいわない」と言い返すが、「あれは歌を歌うのと同じです」と譲らないので、青年は不快になる。大男が言及しているのは、日本人の全体主義や、彼らのアニミズム信仰とは異なる浄土信仰の死生観における声や身振りだろうか。
青年が宿に帰ると、そこにいたアイヌが、あの大男は和人だけではなく、自分たちアイヌのことも「シャモ」と言うのだと教えてくれた。
一人の青年が北海道を訪ねる。3年には、日本の葬儀の儀礼を気持ち悪いと大男が言ったことに不快をおぼえた青年だが、もういちど大男に逢って、人が死んだらどうするか聞かなければならないと思った。宿で尋ねると、大男は「別荘」「涼しいところ」に行っていると言う。
「アイツの女はロシア女だよ」「アイツの親も、涼しいところに住んでいた」
と言われた。この男は、アイヌよりさらに北緯に住む、大男はサハリン先住民族のニブフだろろう。
大男との再会をあきらめた青年は帰り道の海岸線を走るバスの中で海が見えた途端、そこに大男が歩いているのが見えた。岩角から現れ、すこしずつ海の中に沈んでいく。
この謎めいたストーリーのなかに、差別の連鎖の多層的な構造が示唆されている。和人によって差別された北海道のアイヌ、さらにアイヌから差別されていたニブフなど北の先住民の存在が言及される。サハリンが日本領だった時代、ロシア人のほかサハリン(樺太)アイヌ、ウィルタ、ニブフ、エヴェンキ、ヤクートなどの人々が暮らしていた。チェーホフのレポートでも知られるが、サハリンは帝政ロシア時代から流刑地だった。日露戦争後、ポーツマス条約により南樺太は1905年に日本領となった。先住民族の人々は終戦前には日本の情報機関に召集されており、戦後ソ連によって戦犯としてシベリア流刑地に送られたケースもある。日本への移住の道を選んだ人々もいた。
11 オタスの杜について

サハリンの先住民族は、国境や国籍とは無縁の放牧や狩猟生活を送っていたが、一変したのは、日本やソ連が戦争を始めてからだ。原住民に対しては日本語教育等が行われたが、アイヌ以外の先住民族は戸籍上は「樺太土人」として内地人と区別されていた(アイヌも1931年まではこの土人だった)。教育所では日本語や日本名が強制された。男性は軍事訓練を受け、国境でソ連軍の動向を探るスパイをさせられたという。原野を知り尽くし、日本語が話せた先住民族はスパイにうってつけだった。その一人だったウィルタ(オロッコ)の青年、北川源太郎(ウィルタ名はダーヒンニェニ・ゲンダーヌ)は第二次世界大戦後、スパイ容疑でシベリアに抑留された。後に先住民族の軍人恩給の支給を日本政府に訴えた。しかし日本国籍がなかった当時の少数民族には、兵役義務もなく非公式の令状による召集だったとして、戦後補償が与えられなかった。ゲンダーヌは網走市に北方少数民族資料館(ジャッカ・ドフニ 2010年閉館)を建て、1984年に亡くなるまで先住民族の権利実現のために活動した。
樺太敷香町、現・ポロナイスク。ウクライナからの亡命者と日本人との間に産まれた昭和の大横綱大鵬の出生地だ。そこにあった先住民集落オタスは、幌内川と敷香川に分れる三角州の砂丘地にあった。「オタスの杜」ともいう。日本政府により、1926(大正15、昭和元)年に、樺太原住民族であるオロッコ(ウィルタ)、ギリヤーク(ニヴフ)、サンダー(ウリチ)、キーリン(エヴェンキ)、ヤクートの5民族がそこに集められた。1930(昭和5)年に「オタス土人教育所」が建設され、1936(昭和11)年にはオタス神社も竣成された。
林芙美子著「樺太への旅」の一節、1934(昭和9)年の紀行文にはこう記されている。
「やがて子供の歌声がきこえてきました。私は無礼な侵入者として、授業中の教室を廊下の方からのぞいて見ました。教室は一部屋で、生徒は、一年生から六年生までいっしょで、大きい子供も小さい子供も大きく唇を開けて歌っています。金属型の声なので、何を歌っているのか判りませんが、音楽的でさわやかです。台所から出て来たような、太った女の先生が素足でオルガンを弾いていました」「やがて校長先生は子供たちの図画を取り出して来て見せてくれましたが、皆、子供の名前が面白い。「オロッコ女十一才、花子」「ギリヤーク女八才、モモ子」などと書いてあるのです。描かれているものは、馴鹿だとか熊の絵が多いのですが、風景を描かないのはこの地方が茫漠としたツンドラ地帯で、子供の眼にも、風景を描く気にならないのだと思います」
遺体を放置する風葬などの風俗も残っていた。また、当時最北の観光地として多くの「見物人」を集めた。「土人村」を見せ物にする先行事例として、1903(明治36)年に大阪の天王寺で開かれた内国勧業博覧会の会場外で民間が興業した小屋「学術人類館」がよく知られる。沖縄の女性やアイヌ、朝鮮などの人たちが見せ物としてそこに「展示」された。沖縄から異議が上がったが、それは「未開人種」や「劣等種族」と並列で扱われたという抗議でもあった。
北の地では、北海道に暮らすアイヌと、さらに北で暮らしてきたニブフ、ウィルタ、樺太アイヌとの間に差別関係があったといわれている。また、戦後アメリカ統治下沖縄でも、奄美人差別があったとされる。アメリカ統治により、本土との経済的な流通が困難なため、奄美から多くの人々が沖縄に渡る。奄美諸島は沖縄に先立って1953年に本土復帰するが、そこに在留しつづけた人たちは、「在沖奄美人」として、制約を受け差別的扱いを受けることが多かったという。「非琉球人」であり「外国人」という立場になり、土地所有権の剥奪、公的融資を行わないなどさまざまな制限による不遇を受けた。このように差別の中の差別意識というものも根づよい。私は人種差別をはじめ、問題の告発自体を創作の目的とはしない。それを生み出す人間という存在を冷静に知りつつ、それでもなお人を慈しめるような創作がしたい。
この「春香伝考」の試作的上演は、次の第三部で述べる「さんしょうだゆう」の構想へと結びつき、ロシア、韓国、カザフスタンのアーチストとのコラボレーションによって、翌々年の2019年に音楽詩劇研究所の二作目のユーラシアンオペラとして発表した。この「春香伝考」の試作的上演は、次の第三部で述べる「さんしょうだゆう」の構想へと結びつき、ロシア、韓国、カザフスタンのアーチストとのコラボレーションによって、翌々年の2019年に音楽詩劇研究所の二作目のユーラシアンオペラとして発表した。
12 文字のない歌 中島敦の「狐憑」とル・クレジオ
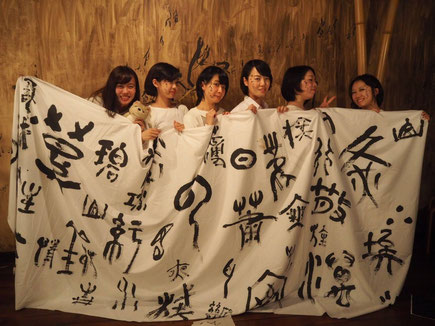
「ユーカラは、「言葉に現せない歴史」だから「歌になる」のだ」
先にも引用した、深沢七郎の小説「和人のユーカラ」で、アイヌとも判然とせぬ不思議な大男が、日本人の旅人に語った言葉が気になり続けていた。「言葉に現せる」、「歌になる」、まさにその「際」のところが私自身の創作でもあるように思える。しかしいったいなぜそんな風に考えるのか、と自問しても、その思考はとりとめもなく散乱し、いつのまにか音楽や歌らしきものができあがっている、というのが実のところだ。
そう思うと、中島敦の小説もそのようにして出来上がっているようにも思え、おこがましいが勝手に親近感を覚えるようになった。以前、中島の「わが西遊記」を元にミュージカルとして創作したことがあった。悟空の破天荒な行動ではなく、悟浄のとりとめない思索や内省を自らに重ねた、実にこの作者らしい「西遊記」だ。その独白を、コミカルな歌詞に脚色して歌にした。
「古譚」という短編群に出会った時は、まさに我が意をここに得たり、であった。そこには「木乃伊」、「文字禍」、有名な「山月記」とともに「狐憑」という話がある。これは「文字」や「作者」という存在の誕生以前において、憑き物に憑かれて語り始めた一人の男と、それらの誕生を許さなかった社会を描いた文学作品だ。中国文学者であり小説家(創作家)だった自身の葛藤を描いた作品でもある。ユーラシアンオペラの創作と並行しながら、ワークショップや、大学の授業で上演を重ねて試作してきたのが、この「狐憑」をベースにした音楽劇「古譚」だ。
「狐憑」の物語は、古代ギリシャのヘロドトスの世界最初の歴史書である「歴史」から、スキタイ人に関する叙述を援用して始まる。スキタイ人は黒海の北岸、現在のウクライナあたりからアジア方面に勢力をのばした古代遊牧騎馬民族で、後の日本文化に影響を与えたとの説もある。この「書物」によれば、スキタイ人にも風土、生活に応じて、王族、農耕、定住、遊牧さまざまな種族をもつ。小説に描かれるその一つであるネウリ(ネウロイ)族は、現在のリトアニアやポーランドあたりに暮らしたとされるが、小説の中では場所や時代は具体的に設定されていない。小さな湖で水上生活をのんびりと営んでいる。
そこに北方の強靭な遊牧騎馬文化をもつ別のスキタイ系の民族があらわれ彼らを根こそぎ襲撃、殺害する。青年「シャク」も弟を失う。そのときからシャクは憑き物がついたように、「野獣の霊」のような不思議なうわごとを語り始めた。いったん正気に戻った後、今度は動物や関係のない人の言葉を語るようになる。人々はシャクの言葉を珍しがって集まった。
語りの題材も、アニミズム的な自然から人間界のことへと変化してゆく。それらは現在においては伝説や叙事詩というものに近い。「語り部」となったシャクの語る物語の内容はさらに変化し、部落の中の出来事や三文記事的な事件についても語るようになる。伝説や叙事詩から出来事の風刺や恋愛などの叙情的内容へ変化する。聞き手は、身近な話題に喜んで共感し、熱狂的な聴衆となった。
「シャクの言葉は、憑きものがしやべつてゐるのではないぞ、あれはシャクが考へてしやべつてゐる」
一方、シャク自身は、人々を喜ばせる自らの語りを、まだ憑物によるものだと考えようとした。
「シャクの物語がどうやら彼の作為らしいと思はれ出してからも、聴衆は決して減らなかった。却つて彼に向つて次々に新しい話を作ることを求めた。それがシャクの作り話だとしても、生來凡庸なあのシャクに、あんな素晴らしい話を作らせるものは確かに憑きものに違ひないと、彼等もまた作者自身と同樣の考へ方をした。憑きもののしてゐない彼等には、実際に見もしない事柄に就いて、あんなに 詳しく述べることなど、思ひもよらぬからである。」
シャク自身は語り部としての才を自認するようになるが、その根拠がシャーマニックな「憑き物」によるのか、「自己の才能」によるのか 自問自答している。しかしストーリーが次々と口をついて出るように沸き上がることについて、やはり「憑き物」の一種だとして納得しようとする。
「但し、こうして次から次へと故知らず生み出されて來る言葉共を後々までも伝えるべき文字という道具があつてもいい筈だといふことに、彼は未だ思ひ到らない。今、自分の演じてゐる役割が、後世どんな名前で呼ばれるかといふことも、勿論知る筈がない。」
シャクの「創作」が、後にいう文字で記された「文学作品」であり、自身の言葉によって創作がなされているとすれば 彼はその「作者」である。しかし一族は「作者」の誕生を許さなかった。
「若い者達がシャクの話に聞き惚れて仕事を怠るのを見て、部落の長老連が苦い顏をした。彼等の一人が言つた。シャクのやうな男が出たのは不吉の兆である。もし憑きものだとすれば、斯んな奇妙な憑きものは前代未聞だし、もし憑きものでないとすれば、こんな途方もない出鱈目を次から次へと思ひつく気違いは未だ曾(かつ)て見たことがない。いづれにしても、こんな奴が飛出したことは、何か自然にもとる不吉なことだと。」
非難され、生気を失い、語らぬようになったシャクは、やがて古いしきたりにより、「生け贄」として差し出され、シャクの入った鍋をかこんで祭、饗宴がおこなわれた。
「ホメロスと呼ばれた盲人のマエオニデェスが、あの美しい歌どもを唱ひ出すよりずつと以前に、斯うして一人の詩人が喰はれて了つたことを、誰も知らない。」
この一族は古代の考え方と方法で、「詩人」を葬り、「歴史」を歩むことを自ら拒否した。自身の生が犯されない限りにおいて、自らを他に対して誇らず、暮らしや自然のなかにある古来の美観と因習、死生観のままに生きる。そこで、古来のしきたり反するものがあれば、「異分子」として一族の合意のもとに封殺するだろう。結果的に進化を拒否した彼らは、おそらく生存競争に敗れて滅亡しただろう。だが、この民族は、文字を使って知恵を広め、それによって他に影響力を及ぼしながら虐殺したり、支配したりすることもなかっただろう。
語り部シャクは詩人という「作者」になる手前で封殺されたが、シャーマニズム的な憑依から出発した語る内容の変化と、それを受容した聴衆との関係は、人間の古代から近代にいたるまでの芸能史の歩みとも重なる。前第一部で述べた、無文字社会から文字社会への変遷期の少数民族をテーマにした一作目と、と次の第三部で述べる、異なる文化の口承芸能の接続を試みたの二作目と、二つのユーラシアンオペラの上演を終えた音楽詩劇研究所は、そうした創作をあらためて総括する意味で、2019年6月にこの「古譚」を上演した。
その際に、さらにフランスの小説家 J.M.G. ル・クレジオの「地上の見知らぬ少年」という小説ともエッセイともつかぬ作品を並立させてみた。この地上にはじめて訪れた言葉を持たない少年の眼に映ったのは、人や人の手で作ったものも含めた自然だけだ。その眼差しそのものが詩であり歌でる。それらをル・クレジオがあえて言葉に「翻訳」したものだといえる。シャクの語りの変遷をとおして、ネウリの一族を歌いながら演ずる私たちと、それを見つめる異界から訪れた少年眼差し。それらを交差させることで生まれる音楽に期待した。旧友の音楽家高橋琢哉に久しぶりに連絡をとり、アイデアやアドヴァイスを求めた。ここ10年ほどは連絡をとることも少なくなっていたが、それ以前に彼の発案で行った二人のさまざまな試みが、この創作のベースになりうると思ったからだ。
高橋との出会いと創作は、私が音楽活動をはじめた20年以上前に遡る。彼とはたとえば、水木しげるの漫画の造語的オノマトペだけをとりだし、絵を取り除いてスライドに投射して、そこで演奏をした。彼が当時音楽を担当していた舞踊家の田中泯との創作で示唆を得た身体感覚と音との関係を、「演奏行為」に再現した。私たちは過去の試みの多くで、旋律やハーモニーや一定のビートにまとまったり、特定の感情や眼差しに集中したりフォーカスすることを避けるような意識で演奏した。思い返せばそれらはまさにこの ル・クレジオの少年の眼差しを獲得しようとする試みだったと思った。
久しぶりに再会した彼は、「古譚」や「地上の見知らぬ少年」を読んで、ウィリアム・バロウズなどが心酔したというアメリカの心理学者ジュリアン・ジェインズのバイキャメラルマインド(二分心)という概念を手がかりにこのように言った。
「(「古譚」は)人類におこったエラーの清涼な物語だなと。回収(シャクの死)がいまからみると地獄なだけで」
田中泯の盟友でもある松岡正剛はウェブサイトの「松岡正剛の千夜千冊」(https://1000ya.isis.ne.jp/top/)でジュリアン・ジェインズの著書、「神々の沈黙」を紹介し、バイキャメラルマインドについてこのように説明している。
「バイキャメラル・マインドとは何か。脳の両半球がブリッジされず、統合もされていない状態のことをいう。(中略)つまりはバイキャメラル・マインドとは古代人の脳のことをいう。古代脳だ。とりあえず、そう思ってほしい。とりあえずというのは、バイキャメラル・マインドは古代のある時期からいったん後退し、それによって形成されたバイキャメラルな社会文化も崩壊するのだが、その後もさまざまな多様な姿をとって復活するからだ。だから本来のバイキャメラル・マインド状態とは2000年ほど前までの人類の脳の状態のことで、そこで何がおこっていたかというと、ここから神が発生した。そして言語と意識が発生してきた。そういう何らかの未然状態をさしている。もう少しジェインズの推理文脈に沿っていえば、かつてそこには、脳の右半球に響く「神々の声」と、それに応える脳の左半球による「人間の応接」とがあったのだが、それがあることをきっかけに大きく変化して、そのあとに「意識」が誕生してきたというのである。それまでは、古代人には意識がなかったのだ。意識はバイキャメラル・マインドの崩壊後に生じたのだ。」
中島敦の「古譚」という書物を、どのやって声を出し、歌うか、について髙橋に意見を尋ねると、
「シャクはまさに前古代人としているわけで、そこでは生理と詩と言語が同時なわけだから、情念とかで(言語を)表わそうとするのは完全に間違えていると思う。(意識のない)透明な世界なのだから、棒読みか、別のことを喋ってる言葉が別の意味に聞こえるくらい離れていたほうが良いかなって思った」
言葉の意味を消滅させる声といえばサミュエル・ベケットを思うが、それをいかに体現させることができるのだろう。その問いを抱えたまま、意味を歌わない身体や声を想像し、そのための作曲を試みた。「春香伝考」も「古譚」も、まだ創作の途上にある。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
