- Home ユーラシアンオペラへの道
- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物
- 囁きはじめるユーラシアの風と歌
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
- ユーラシアンオペラ・用語集・索引
- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」
- アルメニア・モスクワ音楽創作記
- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記
- シベリアに訊く
- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」
- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」
- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記
- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って
- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」
- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ
- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」
- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」
- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)
- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」
- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記
- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え
- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー
中央アジアのノマドを演じる/ベルリン「デデコルクト」創作日記

「デデ・コルクト」ベルリン・トルコ・中央アジア2013、2014
1 下北沢に向かっていたら
2「デデ・コルクトの書」 ベルリンのトルコ街
3 デデコルクト ソリスト紹介
4 クリスマスキャロル
5 パウル・ツェランを歌にする
6 異教徒の孤独 ドレスデンの森にとりのこされて
7「中央アジアのニーベルングの指輪」でノマド(遊牧民)を演じる
8 レイプを演じた私・アゼルバイジャンからのメッセージ
■ 現代音楽を演奏する クセナキス、ユン・イサン(尹伊桑)
9 狂乱の宴 in リヒテンシュタイン公国
10 シュトッツガルド 「魔の山」
11 セルビアの狂乱 作曲家、オーボエ奏者ハインツ・ホリガー(スイス)
◆ 「これは音楽なのだろうか....」 トルコの振付家とのイスタンブールの日々 2011〜2012
1 下北沢に向かっていたら
番号表示のない唐突な電話の着信音が、これから述べる中央アジアの伝統楽器を含むオーケストラのプロジェクトの始まりだった。2013年9月のことだ。その日は、日本に住むアメリカの音楽家、プロデューサーのジム・オルークという音楽家と、ドラマーの山本達久と、下北沢のLADY JANEとうバーでの初顔合わせのセッションだった。私生活において思いもよらぬ悪い出来事が起きた翌日のことだったので、肩に担いだコントラバスの重さがさらに重くのしかかり、鬱々、茫然と、改装されて馴染みない東京の下北沢駅のなかを迷いつつ歩いていた。エスカレーターに乗っていたとき、携帯電話が鳴った。
電話越しの英語が聞き取りづらく、要を得ぬままに30分後にもう一度かけてくださいとお願いして、切る。その後会場に到着し楽器をセッティングしていたらほんとうに電話があったが、ノイズで英語も聞き取りづらく、途中から日本語が少しわかる絨毯職人なる人が電話に出る始末。
電話の主はベルリンので作曲家、ギタリストのマーク・シナンというひとであり、プロジェクトとは、彼とドレスデンの現代音楽のオーケストラ(ドレスデン・シンフォニカ)が作る新作への、ソリスト、パフォーマーとしての参加依頼だった。可能なら翌10月から始まるベルリンでのリハーサルから参加してほしいという内容。
私のように英語や外国語もそれほどできぬ身にとっては、コミュニケーションをとることだけで精一杯である海外での仕事は苦労は重なるが、創作だけでに集中せざるをえない環境はありがたい。懊悩や雑念、「悪い出来事」もひとときでも忘れられるような時間になるということは、経験的に予測できた。闇の中の一筋の光明のように思えた。まだ要を得ぬが、新しいなにかが始まる予感がし、引き受けようと思った。
あらためてE-メールに概要を送ってもらい、まだスマホではなかったので帰宅してから確認する。作品は、アルメニア系トルコ人であるという電話の主マーク・シナンの母の出自に関わるものだった。トルコ、アナトリア、 カザフスタンなどに伝わる「デデコルクトの書」という古い中央アジアのテュルク族の説話をモチーフにした音楽劇らしい。調べるとこの本は日本でも翻訳され、平凡社の東洋文庫から出版されていた。中央アジアについての知識はほとんどなく、この書の名も初めて知った。トルコ人がなぜ中央アジアなのか。トルコ人、すなわちアナトリア半島のテュルク系民族が中央アジアから移動してきた人々だったということすら、おぼろげだった。
2「デデ・コルクトの書」 ベルリンのトルコ街

ベルリンの飛行場で深夜に到着する私を待っていてくれたのは、ドイツ語やトルコ語を英語に通訳してくれる、トゥバという名のトルコ系の若い女性だった。彼女の運転で初めて来たベルリンの街を走り、あれが、いつかヴィム・ヴェンダースの映画に出てきた塔(「戦勝記念塔」)かと車の中から眺めた。そのまま連れて行かれたのはダウンタウウンっぽい感じの街のバーだった。待っていたのは一ヶ月前の突然の電話の主、プロジェクトの芸術監督マーク・シナンと、先にベルリンに来ていたトルコの振り付けのアイディン・テキャルだった。シナンは、イスタンブールと東京を何度も往復してつくったテキャルとの作品を映像で見て、私をこのプロジェクとにソリストとして招いたのだ。テキャルの身体表現メソッドをを駆使した、私が演じるパフォーマンス作品だ。
ドイツ人のシナンがテキャルとトルコ語で談笑していた。クロイツベルクという名のこの街は、ほとんどイスタンブールの裏町のような町並みだった。1960年代から西ドイツの労働者不足から移民が始まり、現在300万人以上のトルコ人(クルド人も含む)がドイツに暮らしているが、ベルリンでは、旧東ベルリン地域に多く暮らしているそうだ。
シナンの母がアルメニア系のトルコ人であり、このプロジェクとを含めた彼の作品は、片側のルーツを辿るような作品であり、今回その素材になったのが「デデコルクト」という説話だ。テュルク遊牧民オグズ族の想像上の吟遊詩人コルクトによって語られた、英雄がダイナミックや怪物が草原や乾いた大地でダイナミックに跋扈する口承説話だ。
「古代にさかのぼるオグズ族伝承を核心に15世紀ころ現在の形態に完成された。中央アジアからカフカスをへてアナトリアにいたる遊牧世界を舞台とする12の物語から成り、散文体に詩や格言が点綴されている。《オデュッセイア》に登場する一つ目巨人キュクロプスの物語など、オグズ族に接触した他民族の説話要素もとりいれている。」(世界大百科事典 第2版 平凡社)
われわれの作品は、この中の第八章「テペギョス」という一つ目の怪物の話をベースに作られる。図書館で借りて、ようやくベルリンに向かう飛行機の中で読んでみた。勧善懲悪的な寓話性が希薄で、道徳性が強調されるというよりは、異教徒などを迫害する残忍とも言える英雄譚、というのが初読の印象だ。英雄バサトが、羊飼いと妖精のあいだの子である一つ目の妖怪テペギョスを退治する物語。伏線かと思われる記述がそのまま置き去りにされたり、プロットや設定に理解に苦しむ矛盾点もある。倫理観や善悪の根底のようなものが、日本の説話や、比較的なじみぶかいのキリスト教的な西洋のそれとも明らかに異なり、???だらけだった。
ホテルと稽古場の往復が始まる。翌朝、舞台の参考のために、冷たい雨の降る中を、古いベルリン動物園にまず向かう。象の背中に舞い落ちる枯葉が美しく、それを受けるその皮膚が愛おしい。数時間ひたすら動物達の動きを凝視し、渡航前にお古で譲り受け、初めて使うアイフォンで撮影した。そのあと東側にあった、ベルトルト・ブレヒトやその後継者といわれたハイナー・ミュラーが芸術監督をしていた劇場であるベルリナーアンサンブルやブレヒトハウスも見学した。
1989年に壁が崩壊して25年近く経っていたが、東側の郊外の風景や建物は東欧やロシアの街並みを思い出した。東西ベルリンの違いは思ったよりも残っていている。私たちが通った1932年創立のマクシム・ゴーリキー劇場の稽古場は、東ベルリン地区にいくつか存在していたが、いずれもやや郊外にある工場や刑務所の跡地という場所もあった。現在そういう場所が、アートスペース、レジデンス、劇場の稽古場として開放されているそうだ。われれの作品はエンターテインメントとはいえない作品で、たとえ満員のお客さんが入っても興行収入だけでは採算がとれないのは明らかだ。それでもこのような広い場所を使って、舞台セットを組んだまま連日の稽古ができる。日本、東京では考えにくい恵まれた環境だ。
舞台芸術の制作状況や公的助成金の充実は、ヨーロッパ、ここドイツでも日本と比べ物にならないくらい良いように見えた。2年の製作期間を経てオーケストラ、スタッフのような直接的な人員だけでも100人近くはいるだろう。エンターテインメントとはいえず、社会に対する批評性が高い作品に対して、それだけスポンサーがあるということだ。ヨーロッパでも文化芸術を巡る苦しい環境も聞くが、日本とは根本的な感覚が異なる。芸能、芸術がが、公的な助成を受けたり、私的に援助を受けることには逡巡がある。しかしアーチストたちがそこでしっかり、じっくり「仕事」をしているように感じ、その環境は羨ましかった。
3 デデコルクト・ソリスト紹介

イスタンブールや東京で作品を作ってきた60代の振付家のアイディン・テキャルの他は、主要メンバーやプロデューサーを始めスタッフ3、40代で、世代が近かった。
テキャルと稽古を続けることになる私以外の3人のソリストは、みなベルリンに暮らしている。ヴォーカルのエレーナ・クルジチ(Jelena Kuljić)は、セルビア出身の女性歌手、俳優。ドイツの現代演劇を牽引するシャウビューネやフォルクスビューネで、アルバン・ベルクの歌劇「ヴォイツェツク」や「ルル」などに出演。現代歌劇音楽、コンテンポラリーダンスのシーンで活躍し、ドイツの老舗現代音楽、JAZZのECMレーベルで発表されたプロジェクトの芸術監督マーク・シナンのCD(「Fasil)」でも歌っている。イスラム教の開祖、ムハンマドが最も愛し、最も若かった妻、アイーシャの人生を歌った歌など女性たちをテーマに作られた作品だ。2018年には劇団のチェルフィッチュの岡田利規演出のドイツ人俳優による「能」のプロジェクトの主要キャストとし来日した。ベジタリアンとのことで、ストイックさも感じるが、稽古中、ロックやR&BやJAZZのスタンダード曲なの一節を、よく唐突に口ずさみ、愉快だった。
フルートのザーシャ・フライドル(Sascha Friedl)は、チャーミングなベイビーフェイスとバイキングを思わせる髭面が同居した風貌をもつ物静かな巨人で、まるで劇画のキャラクターみたいだ。アンサンブルの中では小さなピッコロフルートも吹いたが、今回パフォーマンスで扱う楽器は、彼自身の背やコントラバスよりさらに巨大なコントラバスフルートだ。オペラの演奏仕事で日本に2回行ったことがあるとのこと。公演のみの東京滞在で、サントリーホールからみえる高速道路の風景しか覚えていないそうだ。稽古中、我々のリーダー、シナンがブレヒト/アイスラーの「子供の国歌」(東ドイツの第二の国歌といわれた歌)を弾いたので、私が反応してブレヒト/アイスラーの「ソリダリテ(連帯)」という革命歌を弾くと、フライドルが大笑い。フライドルは旧東独の名門で現在もその名を冠する、ハンス・アイスラー音楽大学を卒業している。アイスラーの旋律が大好きとのことで、第二次大戦中のアメリカ、ハリウッドへの亡命時代につくられた短い歌曲「小さなラジオによせて」という曲を、巨体に似合わぬ小さな声で歌ってくれた。
プロジェクトの芸術監督であり、カルテットの室内楽やオーケストラを作曲をしたマーク・シナン(Marc Sinan )は、今回は直接会う前にインターネット動画でみた。その険しい顔で演奏する表情や、難解な音楽から想像していた印象とは違い、かなりハッピーな方だった。いたずらに爪弾くガットギターのフレーズが、抽象的だが優しい。彼とオーケストラドレスデン・シンフォニカとの共同作業は、トルコ・アルメニアなどアナトリア半島の「Hasretim」に始まり、その後この「デデコルクト」、さらにアルメニアの作曲家コミタス、パキスタン国境の北インドのラジャスタンの音楽にジプシー音楽の起源を求め、中国と伝統音楽と現代音楽を融合するプロジェクトにまで広がってゆくらしい。
ドレスデンシンフォニカ(Dresden Symphoniker)は 、旧東独の街ドレスデンを拠点に現代音楽を中心に演奏するオーケストラだ。中近東や南米、中国などにまつわる作品、委嘱新作の演奏や、映像を駆使したインターメディアな上演も多い。ジョン・アダムス、譚 盾、アンソニー・タネジ、フランク・ザッパの曲。それからイギリスのテクノバンド、ペットショップボーイズとエイゼンシュタインの「戦艦ポチョムキン」の無声映画に音楽をつけたり、アクティブなオーケストラだ。
クラシック音楽の素養を基礎にもちながら、 メンバーの多くは、ロマやクレツマーなど自らのルーツである民族音楽や、JAZZ、ジャンル分け不能なビッグバンド.など、それぞれに主軸となる活動ももっているようだ。そのうえで、このオーケストラで「現代音楽」を演奏することに、とても誇りをもっているようだ。日本のオーケストラの成員が、基本的に他ジャンルへの関心が低いのとは違い、自らの創作の主軸を持ちつつ当たり前のように古典を演奏し、さらに現代の音楽を求めている。
「このオーケストラで新しい音楽を演奏できることがほんとうに嬉しいんだ」
そんな内容のことを、何人かの若いメンバーが、私に言っていた。
4 クリスマスキャロル

テキャルとの日々の稽古は、彼女特有の身体の基礎訓練が主となり、演奏じたいの稽古時間がなかなかとれない。ディテールにこだわってトレーニングを繰り返すため、全体の内容やコンセプトとを理解し向き合うまでには至らない。「デデコルクト」という作品の中で、なぜこのように演奏し、身体を動かすのかがまだ私の中で腑に落ちていない。大枠を捉えられないまま、稽古を重ね、夕方稽古が終わるとホテルに帰って、街をぶらつく。
そんな日々の中ある夜、マーク・シナンに招かれて、娘(小学生)の友人やその家族やいろいろな人が集まるクリスマスパーティーに行った。彼の家はベルリンの中心部から離れたやや郊外の、素敵な一軒家だった。ヨーロッパの都市部の一軒家にお伺いした記憶がそういえばなかった。庭先から広がる湿地帯の野原のすぐ先には沼があり、日暮れ前には老人の釣り人が往来した。そこまで出て佇んでみたり、部屋の中の会話に加わったり。やがて子供たちは飽きてしまい歌うのをやめ、床でごろんとしたり、床に転がっていたおもちゃで遊び始めたが、大人たちのクリスマスキャロルはしばらくつづいた。シナンと、フライドルがギターとフルートで伴奏をつとめた。
翌月の二度目の稽古期間は、ホテルも稽古場も郊外のヴァイセンゼーという小さな沼の近くで、オフ日も無く、稽古後の夜にも、疲れ果てて、寒いのであまり街中に出なかった。ホテルと歩いて5分ほどで行ける稽古場との往復が続いた。帰国後の東京での仕事の準備をしながら、煮詰まると近辺に散歩に出たり、ときどき、同じホテル暮らしのテキャルと夕食に出るくらいだ。
街の中心部から少し離れた旧東独の町並みや、建物は無個性に思えた。そんな風景を見ながら、密室の孤独や狂気みたいなものも想像てしまう。寒い土地では、室内と屋外の生活の境界がはっきりしているのは当然だ。文化や習慣は重いドアに閉ざされた室内で育まれて、外に開かれることはない。外に開くには、たとえば書物という間接的な媒体や、人が集う屋内の場所が必要になる。媒体や空間は「公」という概念を形成すると同時に、対立的に「私」という概念も形成し、パブリックとプライベートを分断する。
冬の寒い夜、暖かい家のなかで、パーティーでみんなが歌っているのか、冷たい壁に囲まれた孤独があるのか、外からはわからない。ヨーロッパの都市では、多くの一般市民はアパートに暮らしている。日本の都市、下町を歩いていると、あらためて一軒家の低層住宅の密集を感じる。よくこれだけ家を建てたものだなぁといつも感心する。露路の人びとの暮らしのなかに、「プライバシー」がちらっと垣間見える(見せる)くらいなのが、私には一番いいかもしれない。そう思いながらも、琉球諸島の古い民家は玄関をもたないそうだが、そこで縁側や庭先でで三線を弾き、歌うような、さらにおおらかそうな南の風景に私は憧れつづける。私自身は生まれてから現在に至るまで、マンションの中層階(なぜかたいがい7、8階)に暮らした経験しかないのだが,,,いずれそういう住環境もまた、音楽や人生観や感性にも与える影響は大きいはずだ。
傾斜する屋根をもたない、鉄筋の集合住宅には屋上というのもある。ある夜、シナンの友人だというピアニストのマーク・シュモリングと、プロジェクトの制作にたずさわっている日本人の御夫人(お母様がドイツの大学で楽器を教えていたそうだ)暮らす、市街のアパートに夕食に招かれた。4階建てくらいのアパートの最上階だったが、煙草を吸うために屋根裏のような階段を上り屋上に出た。真冬の屋上でぶるぶる震えたが、高い建物があまりなく、電飾看板も多くないので4階の屋上からも夜の街が一望できる。出会ったばかりの友とともに、気持ちのよい冷気に包まれた。日照時間の短いベルリンの街は暗い。約十日間のうち晴天は二、三日ほどだった。そのかわりに夜になると都会なのに星々がくっきりと瞬いた。街灯が少ないせいか、暗い町並みに、ぽつぽつとクリスマスの飾り付けの灯りも見える。
ある夜、彼とともにジャズやフリーな即興音楽のジャムセッションに出た。小さなバーに楽器を持ったミュージシャンもお客さんもたくさん集まっていた。私は翌朝の身体稽古を考えて0時頃に失礼したが、朝の4時まで続くそうだ。彼が紹介してくれた実験音楽のコンサートにも行った。シュモリングの母親はチェコの代表的なビート詩人インカ・マチュルコヴァだ。1968年の改革「プラハの春」の直前1965年にアメリカのビートニクスのアレン・ギンズバーグが二ヶ月間チェコに滞在し、チェコの詩人やカウンターカルチャーに影響を与えたらしい。彼は母親の詩など用いて「沈黙」をテーマにした興味深い合唱プロジェクトも行っている。動画を見ると、自作とクラウディオ・モンテヴェルディのマドリガーレ(無伴奏合唱)を引用、解体、即興演奏が交錯しながらアンサンブルが作られていた。いつか、シュモリングとも共演したいものだ。
彼が教えてくれたコンサートにも行ってみた。フリーインプロヴィゼーション、カール=ハインツ・シュトックハウゼンのクラリネット独奏曲の演奏とシュトックハウゼンをテーマにしたアニメなど。音 を一音も吹かないサックスによるシアターピースや、なんらかの共通のテーマ性をもったギターなどの弾き語り演奏が一人一曲(詩)ずつ入れ替わり立ち替わる。価値観も多様で、演奏レベルも高く、構成も良い。両方ともよく人が集まっていた。東京だったら多分お客一桁だろう。ここではまず入場料が安い。おそらくギャランティーも安い。生活保障が安定している。税金は高い。
終演が遅くなり、出演されていたベルリン在住のピアニストの千野秀一が、真っ暗な道をトラムの停留場まで送ってくれた。かつて宇崎竜童のダウンタウンブギウギバンドのキードード奏者、アレンジャーだった千野は、1980年代から、映画テレビ音楽や舞台音楽を多数制作。コンピューター音楽や演奏システムの作成、ピアノやさまざまな楽器を用いて即興演奏を行い、数年前にベルリンに移住していた。ベルリンでは実験音楽での活動の他、中世多声音楽を教会のオルガンで演奏する活動も行っているそうだ。誰も乗ってこないまま三十分、旧東ベルリンを郊外のヴァイセンゼに帰る。誰もいないトラムで、夜のトラムで帰路につく人々の佇まいを思い出しながら、この街の人々の、あたたかすぎず、つめたすぎない感じが好きだと思った。社会主義国家が崩壊しもう20数年ほど経ち、もうそんなことはないかもしれないが、なにか、かつてのその密告社会の警戒感によって示される他者への無関心と、一方、その奥のほうから滲み出る、一人ひとりの人間の、素朴でさりげない優しさのようなものを感じてしまう。ロシアや東欧の街では、なんとなくそう思う。
5 パウル・ツェランを歌にする

ヴァイセンゼのホテルのすぐそばにユダヤ人墓地があり部屋のベランダから見えた。稽古の傍らで、東京である翌月のある公演のために、部屋の中で歌の作曲していた。夕方にリハーサルが終われば、部屋に戻り、買い込んだビールもそこそこに、帰国後の仕事のため、ユダヤ人の詩人パウル・ツェランの詩を歌にする。その孤絶した結晶のような言葉は、旋律になることを拒んでいるかのようだ。
祈りなさい、主よ
私たちに向かって 祈りなさい
私たちは近くにいます。
――パウル・ツェラン「テネブレ」(飯吉光夫 訳 )より
「テネブレ」とは暗闇を表す。これ以上は無理だな、と放棄し、真冬の夜明け近くに、墓地や湖畔の雑木林を、訳詩を書き写したメモを手に呟きながら、歩く。
ホロコーストによりどのように父母が死を遂げたのかは知っているが、ツェラン自身はそこには居なかった。 そこに、不在だったことがツェランを創作に向かわせた。ツェランの詩は祈りや鎮魂のような精神ではない。祈るのは神。詩篇は、ホロコーストや「救済しなかった神」への告発として読むことができる。それは言語が死を獲得する臨界地点で瞬間に語が石化し、鉱物になる。イメージの乱反射するように散乱し、飛沫や光の筋、石化し凝固した物質、物体,,,それらの物質的恍惚だ。
それらの言葉が、「水」のごとく流れるような時の連なりをもつ旋律を拒むのは当然のことと言えるだろう。だがツェラン自身はパリのセーヌの流れる水のなかに自ら身を投じた。私はツェランの詩において死者である、「石」 を「鉱物」を「星」を「墓石」を再度、生の粘着質へと、液体へと、戻す。蘇生させて行くようなイメージで。やっと旋律らしきものが生まれ、小声でしつこく反芻していると、なにか薄明の曇天に溶け、消滅にむかって塵になってゆくような体を感じた。
6 異教徒の孤独 ドレスデン の森にとりのこされて

マイナス二十度。ベルリンを数回往復した後、いよいよ初演の地ドレスデンに入った。「デデコルクト」の二つある写本の原本はなぜかドイツのドレスデンの図書館に残されている。もうひとつはバチカンの図書館にあり、イスラム圏には存在しない。この謎についてアゼルバイジャンの作家カマル・アブドゥッラの小説『欠落ある写本 デデ・コルクトの失われた書』(水声社 伊東一郎翻訳)により、日本でも2017年に邦訳され出版されている。先日(2020年)ベルリン在住のピアニスト千野秀一と東京でコンサートをおこなったとき、ドレスデンや大きな旧東独都市がネオナチズムの拠点になることが多いらしいと仰っていた。
ドレスデンは黒い街だ。かつて「エルベ川のフィレンツェ」とも謳われた美しい街並は第二次大戦連合軍の爆撃を受け、火災した。黒こげになった建物の瓦礫からかつての街並を復元したのは、戦災の記憶を留めるためだという。空爆により広島以上の死者をだし、破壊されたという街は見事に以前の姿を再現しているという。ドイツの極東ドレスデンはまだロシア語の表記も多かった。オーケストラのプロデューサーのマルクス・リントは旧東独出身で私と同年代の1970年代半ばの生まれだ。彼らは学校でロシア語を習った世代で、リントも中央アジアの音楽家ともロシア語で話していた。
身体パフォーマンス、カルテットでの演奏、即興的な独奏などのソリストとしての役割のほか、オーケストラにも参加することにもなった。膨大な枚数のオーケストラ用の楽譜が送られてきたが、忙しくしていたので、ようやく飛行機の中で楽譜を読んだ。複数拍子、変拍子、テンポチェンジだらけで目が眩む。東京~ドレシデン経由地含めて丸一日間、一睡もできなかった。
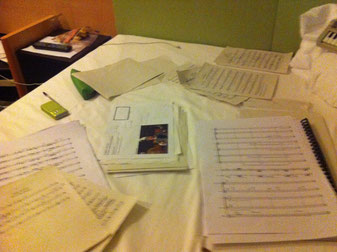
指揮者のいるオーケストラのなかで複雑な現代音楽を演奏するのは、経験も少なく苦手だ。当初は負担が大きいので、ソロとカルテットに集中してくださいとのことだった。しかし言語でのコミュニケーションが難しい分、作品理解のためにはオケへの参加と楽譜の情報の読み込みと分析(アナリーゼ)も不可欠と思った。そう痛感し、前回のベルリンの稽古のとき、自ら希望して参加することにしたのだが、こんなに大変だとは,,,
一ページの中にたった数秒の出来事が、びっしりと書き込まれている。ホテルの部屋で楽譜と格闘しながらヨーロッパの伝統の狂気を呪う。しかしオーケストラの面々はそれを当たり前のようにその通り完璧に演奏する。劣等生気分ゆえに、他人は完璧に見えるだけかもしれないのだが...指揮者のファビアン・パンシエロはアルゼンチン人だが、オケの練習が始まると、コミュニケーションはほぼドイツ語になってしまい、ソリストとしては巨人の異教徒の怪物を演じる私も迷子の子猫だ。「うわっー、何小節目からはじめるのだろう...」とあたふたしているともう演奏が始まっている。「アイン、ツヴァイ、ドライ、フィアー」。ドイツ語をほとんど知らない私には、「フィアー」も4ではなく5な気がして、そういうところからすでに頭とカラダを連動させる配線が乱れる。リズムをつかみとるというより、数字を数えることに苦しんだといっても過言ではない。「フィアー」が4に思え始めた時、だんだん指揮やオケに慣れてきたような気はしてきた。
練習を終えてホテルに戻っても、カウンターバーで酒を飲むメンバーを尻目に毎晩楽譜とにらめっこ。そのまま眠らずに朝、トラムに乗り劇場に通う。
トラムで市街から森の中に入りそのまましばらく乗ったところに劇場はあった。雑木林と原っぱの中にぽつんと大きな無機的なモダニズム様式の建物がある。そこが初演の劇場だった。ちょうど我々の前は、舞踊家の勅使河原三郎の舞踊公演があったとのことで、まだ日本語で書かれた舞台裏と楽屋をつなぐ劇場経路案内の紙があちこちの壁に残されていた。古いが機能美を感じさせる良い劇場だと思った。初演を前に一週間ほどの稽古。
1907年に建築されたこの劇場は、「Hellerau」といい、当時において斬新なコンセプトで建築された。天井と壁には白いワックスのかかった布が敷かれていて、何千もの白熱灯が拡散した非物質的な光をつくり、可動式で自由な座席設営も可能だそうだ。劇場としてだけではなく、身体の動きをベースにした音楽教育「リトミック」の創始者、エミール・ジャック=ダルクローズが教育機関としてもこの場所を用い、モダニズム芸術運動の拠点になった。しかしわずか数年で、設備投資のいきすぎと、第一次世界大戦の出征により学生がいなくなったことで教育機関は破綻する。1938年には警察学校に変わり、1945年よりソビエト軍の病院、スポーツセンターとして機能し、1996年にようやく、現在の形への再生を始める。修復された現在は、コンテンポラリーダンスと現代音楽の中心地となっているそうだ。味気ないが心地良さも感じた、この建物にもこんな歴史があったことをは後になって知った。
遠い日本から来たソリストとして大事に扱ってもらっていたが、オーケストラメンバー、中央アジアの伝統音楽家と加わりながら大所帯になってくるとそうもいかない。あるとき、口頭で伝えられた稽古時間の進行をよく把握できず、メンバーが先に帰ってしまい、ひとりこ森の中の、古くなったモダニズム建築の劇場に取り残された。夜も更けて、マイナス20度の極寒。劇場の外は、原っぱと雑木林が冷たい風に晒されて音をたてるのみ。暗闇。乗客が居ない二両編成のトラムが時々目の前を往来するが、それがこの一帯の闇を照らす唯一の灯だった。次の終着駅で折りかえせるかと思いそこまで歩いて乗ってみてが、そこで停まったままだ。誰かがまだ残っているかと劇場に引き返すしても、鍵は開いていたが守衛さんしかいない。途方に暮れる。そんなことをくり返す。ドイツといえども旧東独地域で英語もあまり伝わらない。スマホもはじめて持たされてはいたが、WIFI接続なるものも当時良くわからずちんぷんかんぷん。あとから思い出すと自分でも笑ってしまうが、人生ワーストテンには入る淋しさだった。やっと行き先の分らないトラムに乗り込んでホテルに帰れたが、また徹夜で譜読みをして翌日も朝から最終稽古。

朝、ホテルから劇場まで車に分乗して向かう。途中から合流した中央アジアからのゲストの演奏家、ウズベキスタン、カザフスタン、アゼルバイジャン、彼ら同士で話すときはロシア語だ。彼らがロシア語を話すことの意味。私たちが当たり前のように異国語である英語でコミュニケーションするように、ロシア語で話す。ソビエト、社会主義が20世紀のインターナショナルたらんとした痕跡。そのことを負の遺産、だといってしまってよいのかどうかはわからない。車には、彼らと乗り合わせることもあった。車中はまったくわからないトルコ語と少しだけわかるロシア語。ドイツ語と中途半端にわかる英語のなかでの感じる孤独より、アジア人の話す言葉の響きのなかに身をおくことのほうがまだ気楽で心地よかった。だから私は、彼らが乗る車に同乗させてもらうことが多くなっていった。
7「中央アジアのニーベルングの指輪」でノマド(遊牧民)を演じる

公演はリヒャルト・ヴァーグナーやイーゴリ・ストラビンスキーの作品名を引き合いに、「中央アジアの「ニーベルングの指輪」」とも「現代の「春の祭典」」とも、新聞やメディアの見出しで喩えられて、宣伝されていた。
中央アジアの伝統音楽演奏家の方々が演奏する、コブス、ドンブラ、サト、ケマンチェなどの弦楽器の音色の美しく、幽けきこと。そして歌、倍音唱法の力強さと、 指で弾かれる打楽器の軽やかさ。弓弾きされるウズベキスタンの弦楽器サトの瞑想的な音楽の中で、私たちソリストが楽器をかかえて遊牧するように歩く場面(ノマドウォーク)があったのだが、それに心が動かされた瞬間から空っぽになるまでの幸福感がたまらなかった。
このような海外のプロジェクとでは、起きている出来事や進行を、立ち止まって言葉に置き換え、さらにそれを日本語にして自らの腑に落とし、さらにそれに対する自らの感情を言葉にして胸の内にしまう。そんな幾重ものもどかしさに疲労が重なる。言葉と言葉とのあいだにある、言葉にならない感情が優しく撫でられているようだった。平均率の12音に収まらずに揺らぐ、その幽かな音色に揺さぶられつつ浄化され、コントラバスをかかえて歩きながら落涙を禁じえなかった。
西洋のオーケストラの演奏家が一つの楽器の演奏に特化したプロフェッショナルであるのに対して、彼らは歌も太鼓も、弦も弾く。いわば、ある「楽器のマスター」ではなく「音楽のマスター」なのである。日本でも三味線、琴、謡、踊とあわせて稽古しながら習得することが多かった。練りに練られた設計図のように構築された楽譜と格闘する日々だったので、中央アジアの伝統楽器の、風のような一筆書きのようなその旋律が私には救いや慰めとなった。
一方でこのような多民族都市のベルリンで多民族が同居するプロジェクトのなかに長く居ると、あらためて日本人が「遊牧の民」「混血の民」ではないことを強く意識せざるをえなかった。正確無比のドイツのオーケストラと、繊細に歌うアルゼンチン人ファビアン・パンシエロの指揮、中央アジアのテュルク族の音の揺らぎのなかで、ソリストであるヨーロッパや日本の私が、ノマドを「演じる」ことは逆説的だ。私は、ふだん特に日本人であることの自負や気負いはないけれど、このインターナショナルなプロジェクトの中では、日本人の私がそこで何を表現すべきか、何を演奏するべきかの、その「意味」について考えてしまう。
ところで、この遊牧民を演じる、楽器を弾かずにもって歩くだけのノマドパート。稽古も半日、丸一日と続くが、ほかのソリストはギター、プラスチックでできたコントラバスフルート、ボーカルのエレーナ・クルジチにいたっては手ぶら。わたしはコントラバスですよ!ギター1キロ、コントラバスバスフルートだって楽器と思えないほどに巨大ではあるがプラスチックなので持たせてもらったが重くなかったし...しかも私が「運ぶ」ドイツ製のコントラバスは、普段使っている自分の楽器よりさらに重く、15キロ近く。音も出さずに一日中楽器を運んで歩いて、足の運びやら感覚やら上半身の姿勢やら目線やら、怒られながら...後々、舞台の演出をする時など役には立っているが、「もう一回」とテキャルにいわれると、もういやだぁーっ、といつも反抗的な感情がむくむくと芽生える。
私は指揮を観ながら演奏するのも苦手だ。多くの指揮者と演奏をした経験がないので、振り方の癖をつかみにくいのだと思う。リズムのわかりやすさ重視か、表現のニュアンスを重視するか。自作曲のリハーサルに出向いたラテン系、アルゼンチン人の指揮者ファビアン・パンシエロの代わりに一度リハーサルに来た若いドイツ人の指揮者は彼とは異なり、とってもリズムが明確というかスクエアで「分りやすかった」。リズムが複雑な難曲のため、「オケの面々も「このほうがわかりやすいよなぁ」と口々に。彼(ファビアン)の指揮は細かく歌いすぎてわかりにくい、と愚痴っていた。「ドイツ人の指揮」に慣れているのだろうか。「民族性」を安直に個人の特性にあてはめたくはないが、やはり「歌う」ラテンとスクエアなゲルマンというプロトタイプな民族性があてはまるのだろうか?しかし、作品のテーマの異民族の共生というテーマと呼応させ、このような「違和感」も前提をふまえ、ドイツのオーケストラにあえてドイツ人ではないパンシエロを指揮者として招いたのだろうか。
映像の中で演じられる中央アジアの伝統歌は自由に歌われるが、その自由に伸縮するリズムが楽譜と指揮によって統制されたオーケストラがそれに併せる。繊細に揺らぐ歌や音楽にあわれるので、楽譜としては難解なものになり、さらにいくつもの楽器の旋律が同時に重なり合いながら演奏される。映像で批評家による語りも入るが、その語りの一語一句にリズムにあわせる音楽も徹底的に楽譜化されている。かと思えば、私が楽譜を用いずに完全に即興するパートもある。それらさまざまな形式や演奏方法自体が、「異」とされる存在への、多義的な解釈だ。
羊飼いが妖精を姦して生まれた怪物「テペギョス」はこのデデコルクト」のなかで、血縁的結束を逸脱した異教徒というカテゴリーをも超越した異物として禍々しく存在している。私はあるパートでそれを演じる。そのシーンの演出としてこのような提案をした。舞台の四方を囲むオーケストラピットから私がコントラバスを抱えて抜け出て、カルテットでの演奏する。私がピットからでると、同時に指揮者が指揮台から退き、私がそこを占拠して譜面台に置かれたカルテットの楽譜を、一節弾き終えるごとに一枚一枚、舞台上に向かって投げ捨ててゆきなが演奏をする、楽譜を全て投げ去ったあと、私が指揮台をはなれて舞台上がる。即興的な独奏で演奏しはじめ、じょじょに激しいパフォーマンスを加えながら一つ目の怪物テペギョスの暴虐と孤独を演じる。
指揮者=オーケストラ=楽譜=西洋=キリスト教社会におさまりきらない、異教徒の怪物の悲しみを、人間からモンスターへの変身と捉え、一連の儀式のように演じた。次々と投げ捨てられた大量の楽譜は、クルジチが腹の中にため込んで、妖精が異物、怪物テペギョスを誕生させる懐妊と堕胎のシーンで用いた。
本番間近になって、ようやくそんなふうに作品を解釈して演じられるくらいまでにはなって、ドレスデンで何とか無事初演を終えた。

本番のステージ後、劇場のロビーで中央アジアの楽器によるアフターコンサート、セッションがあった。前晩の最終リハのあと、美音の爆音カーステレオでブラジリアン・コンテンポラリーファンクをかけながら、鎮まりかえる夜の街を「マシュケ・ナーダー」と歌いながらレストランまで危ないくらいの速度で飛ばしてくれたオケの打楽器アルディティも加わった。彼の活動の中心はコンテンポラリージャズのドラマーであり、グル−プのリーダーをつとめ様々なイベントを企画しているようだ。つねに独特の「ノリノリ」感をもつが笑顔をみせず、なんとなく攻撃性もある独特の男であり、偏見かもしれないが、ある種の「ドイツ人らしさ」を感じる。いつのまにか、ジャズも演奏するチューバ奏者のトム・ゴッチェもコントラバスで参加した。彼は本来はコントラバス奏者。私がソロ、カルテットと身体パフォーマンスに徹し、オーケストラのなかでは演奏しない可能性もあったので、チューバとコントラバス両方スタンバイしてくれていた。オーケストラでは私は彼のその楽器を弾いた(楽器破損の恐れもあるパフォーマンスやソロ用には別の楽器が用意されていた)。リハーサルで、ドイツ語がわからずあたふたしているわたしのとなりで、練習を始める小節番号をぶっきらぼうに英語でささやいてくれた。

仏頂面で大柄のトムがニコニコと嬉々とした表情で、おおいかぶさるようにコントラバスを抱きかかえて即興で弾いていた。持ち主の元に帰り、よく歌うコントラバス。わたしの出る幕ではない。観ていてコントラバスってカラダの大きい西洋人が弾いてきた楽器なんだなぁとも思った。
しばらくして「一緒にどう?」とスタッフの方に促された。西洋楽器を弾く日本人である私は「アジア人」ではないのかもしれない、、などと淋しい想いもしながらみつめていた引っ込み思案な私は、自分から言い出せずにその言葉を待ってもいたのだ。でも彼らの音楽を後ろの方で聴いているだけで幸せだったし、それは今度、またいつか。トイトイトイ・・・彼らのセッションを見ながらおぼろげに、ほぼ同年のマーク・シナンとドレスデンシンフォニカによるこの充実した仕事に刺激を受け、今度は私自身がこんな作品を創ってみたいと思った。この夜の「またいつか」があのイスタンブールの空港での夢想、その後のユーラシアンオペラプロジェクトへの道の実質的なはじまりだったかもしれない。


ベルリンの劇場は「どん底」や「母」で知られるロシアの小説家、劇作家の名が冠されたマクシム・ゴーリキー劇場だった。
本番前の劇場の中で、スタッフや出演者が通り過ぎるときお互いに「トイトイトイ」と言っていた。なにを言っているのだろうと不思議に思った。楽屋に、衣装スタッフの若い女性たちが、コスチュームを綺麗にたたんでくださったその脇に、チョコやクッキーといっしょに「Toi Toi Toi」とメッセージカードが添えられていたりする。好かれてでもいるのか、と気がはやるがそういうことではない。「きっとうまくいくよ」とか「がんばってね」とかの意味で使われているそうだ。ドイツやフランスでしかわたしは聞いたことがないのだが 、帰って語源を調べたら「Toi」とは「Teufelトイフェル)」は「悪魔」の意味の略語だ。悪魔払いのおまじないで、「トイトイトイ」といいながら三回つばを吐いていたそうだ。中世から芸人の出番前のときなどに呪文のように言われていたそうだ。今回わたしは退治される悪魔を演じていたのだが...
8 レイプを演じた私・アゼルバイジャンからのメッセージ

アゼルバイジャンの女性ケマンチェ奏者はアルメニアとアゼルバイジャン間の民族問題であるナゴルノ-カラバフでおこなわれていたアルメニア人によるレイプを思い出してしまったのだという。それに関する記事が送られ、パフォーマンスについての説明を求められた。私はその問題の詳しいことは知らず、それを意識してパフォーマンスしたわけでもなかった。
「政治と音楽はおなじことです」彼女は私へのメッセージをこう結んだ。
彼女に限らずだが、彼女たち中央アジアやコーカサスの音楽の誇り高く守られてきた伝統の美や力の、儚さと強靭さの同居する音楽、音色に、私の心や身体はずっと揺さぶられ、慰められてもいた。スコアにびっしり書かれた音符を精確に表わす複雑なオーケストレーションから浮かび上がる彼女のケマンチェの幽けき即興演奏、カザフスタンのシャーマンの弓奏楽器コブスの雑味のある太く瞑想的な響き、繊細にグリッサンドされるウズベキスタンの弦楽器サトの弓弾き。いずれも言葉にならない部分の感情や感覚が、優しく愛撫されているようで、稽古中に思わず落涙したこともあった。伝統音楽の純粋な美の力を強く感じ、それらは政治とは遠く無縁のように思えた。彼らの音色や旋律を「純粋」や「美」や「伝統」などと、言葉にして得心してしまう私自身の安直な感性も残念なものだが、それにしても「政治と音楽はおなじことです」という彼女の一言はとても意外だった。
「音楽に政治をもちこむか否か」とはよく耳にする論議だ。そのたびにこのエピソードを思い出す。もちこむ、もちこまないという論議以前に意図せずとも反映されるもので、議論はどうでもよいことのように思う。私はあえてもちこもうとはしていないが、おのずと何らかの形で音楽や創作に反映される。そしてそれがどのように伝わるかは、さらにまた別の問題だ。私も音楽は政治でもあると思う。いや、音楽は政治に限らずあらゆる言葉に変換可能なものであり、そもそも音楽という言語を定義することにあまり意味はない。このような実感は、ダンスと音楽の領域を曖昧にするアイディン・テキャルとの苦心の末の共同作業から得たもののように思う。
私はこの一場面を、立場によって善悪が入れ替わるという、普遍的な現象として抽象化して表現した。それに対しアゼルバイジャンのケマンチェ奏者の彼女は、もっと具体的事実の想起という形で受け取った。社会のさまざまな諸問題をコンセプチュアルに包括して表現する現代アートのような抽象が抽象として受け止められるということは、欧米や日本のような社会や一部の愛好家層に限られるのかもしれない。抽象芸術に安住することは難しいと感じた。
そんなことを考えながら、私の創作意図や考えを説明し、いくばくか通じ合っているのかよくわからない英語のメッセージを重ねていた。その終わりに、唐突に「あなたの演奏からはムガームを感じるので、ぜひ私の父が体系づけたムガームに関する本を送りたい」と言ってきた。ムガームとは、ひろくアラブ、中東、中央アジアで用いられる、音楽とくに旋法の形式、理論である。テュルク、ペルシアなどイスラム文化圏でマカームと総称されるものの、アゼルバイジャンでの名前だ。彼女の父はソ連時代の音楽大学でそれらを「アゼルバイジャンの民族音楽」として体系づけた「民族音楽の父」のような大家であるそうだ。
芸術監督マーク・シナンの次の仕事はアルメニアの作曲家 コミタス・ヴァルダベット(Komitas Vardapet)について。マークの母はアルメニア系トルコ人だ。私はその2.3年前トルコで知ったこの作曲家に惹かれていた。私はマークにこの話をきいたとき、はじめは、関心のあったこちらのプロジェクトの方で一緒に仕事をしたいと思ったものだ。このプロジェクトの参加したはじめは中央アジアやトルコの説話というのも現実感が希薄で、「デデコルクト」を初めて読んだときも話の因果関係がよく理解できず、子供でも知っている話としてたしかにインターネット動画で子供用アニメもたくさんみつけたが、残忍さと不条理的も感じるお話が子供のとき自然に入ってきたらどんな大人になるのだろうと思った。子供のときに自然にカラダの中に入る倫理観や論理というものは随分影響を与えると思う。やはり文化の違い、遠さを感じたのも事実。しかしわたしが芥川龍之介(1892−1927)の原作で公演した参加しているグループKhkhsによる「momotaro」(2014)で演じた、わたしたちがよく親しんでいる昔話の「桃太郎」も、勇気ある少年のときに滑稽な楽しい昔話になっているが異民族の象徴としての鬼をかなり残忍に退治し、殺害する話しだ。
さて、アゼルバイジャンのお姫様メフリは、半年後この作品の再演の時は出演しなかった。政治なのか、宗教か、お金か、その理由は残念なことに良くわからなかったが、なんとなく彼女についての話題を芸術監督のマークふると、彼は「彼女は難しい、、」とだけ言った。再演の時はもっと若い女性のケマンチェ奏者か参加。メフリさんの幽玄な響きとは異なり、音も溌剌として若い。小さな国リヒテンシュタインで、一緒にバーに行くと(物価めちゃめちゃ高い!)、 踊りまくり、突如にリンボーダンスも疲労する陽気な若者だった。



カザフスタンの歌手ウルジャンもやはりお姫様だった。伝統楽器奏者の中では、歌も歌う彼女がメインにフューチャーされていた。ウルジャンが伝統的な衣裳で舞台中央に出てきて歌い始めると空気が変わる。リズムよくドンブラを弾きながら、草原や乾いた土地のずっと先の遠くにまで届いてゆきそうな芯のある声。そんな声が劇場という建物のなかに響く。彼女もまたふだんはあまり口数が多くなく、保守的でフランクな感じではない。ドレスデンの中央広場の露店で、ウルジャンが一目でまがい物とわかる宝石を熱心にみていたので、思わずくすっと笑ってしまい、ちょっと睨みかえされたが、その後少しうちとけた気もした。
熱心なイスラム教徒であるウズベキスタンとカザフスタンの男性奏者の二人は、「おじさん濃度」高し。ウズベキスタンの弦楽器サトや打楽器も弾いたタイール(Toir Kuziyev)は、演劇的なプログレッシブロック時代のジェネシスのピー ター・ガブリエルのツアーに参加しソロを弾きまくったりしていたのだった。もう一人はカザフスタンの弦楽器ドンブラや口琴、喉歌を歌うカザフスタンのアスカー(Askar Soltangazin)は私と世代が近い屈強な若い男。いつも親しげなボディータッチからそのまま相撲でもとりはじめそうな彼と話すと、ある意味保守的な男尊感も垣間見えるが、宗教的伝統であろう。日々かれらの音を聴き、少しずつ打ち解けてゆくなかで、いままで縁がなかった中央アジアの音が少し身近なものとなった。
ホテルで朝食の時、オーケストラの監督のマルクス・リントが、今回の公演の映像のための、コーカサスやアナトリアや中央アジアのオフショットの写真をたくさんみせてくれた。田舎や街のとても素敵な風景や人々の顔。都市の広場にたつカザフスタンの首都アスタナの威圧的にもみえる、未来都市計画による巨大モニュメントや現代建築は黒川紀章さんの設計。カザフスタンのドンブラやホーメイのアスカーの生徒の民族衣装を着せられた子供たちのなんと可愛いらしいこと。ウズベキスタンの弦楽器サトや打楽器のタイールはピーター・ガブリエルのツアーの動画をみると、大観衆を前にひょうひょうとサトを弾き、振り付けられた踊もはいOKッて感じで受け入れ、ソロを弾くのおじさん。なんでもこいだなぁ!どうこうして気負いなく演奏できるのだろう?そもそも演奏するとは彼らの生活の中では気負って何かを表現しようよすることではないのかもしれない。
中央アジアやコーカサスの伝統音楽奏者、オーケストラ、わたしにとって普段馴染みのないアンサンブルの経験は、その難しさも含め創作過程自体がまさにドキュメント作品のようなものだった。帰国し、半年後にはまたツアーが行われる。




■ 現代音楽を演奏する クセナキス、ユン・イサン(尹伊桑)
帰国後は、数ヶ月後に、リヒテンシュタイン公国やアゼルバイジャンの首都バクー(後に延期となった)などで予定される再演に備え、指揮法も理解した方がよかろうと思い、指揮法の入門資料を眺めてみた。作曲家一人の頭の中で生じた膨大な情報量をどのように指揮者が「交通整理」しながら演出し、リプレゼンテーションするのか。自分がもし大きな編成のアンサンブルの作曲をするということを想定すると、やはりその存在の重要性をあらためて思う。
私の親戚に指揮者の故岩城宏之がいて、生前、チケットをもらい(クラシック公演に比べ、人気のない「現代音楽」はチケットがもらいやすかった)、ルーマニア生まれのギリシアの作曲家イアニス・クセナキスの大編成オーケストラをサントリーホールまで聴きに行ったことがあった。インターネットで情報を調べると1997年だったので、まだわたしが大学卒業手前の頃だった。
クセナキスは両親の故郷であるアテネで建築や数学を学び、第二次世界大戦中1941年にドイツ、イタリア、ブルガリアの3分割されたギリシアでナチズムに対するパルチザン、レジスタンス運動をおこなった。ドイツ、イタリアの撤退したあとは、イギリス軍が進駐し新政府を設立、亡命を試みるがその際に左顔、眼、耳も負傷する。
「1944年12月、アテネの寒い夜、街路での巨大なデモンストレーション、時々の、えたいのしれない、致命的なノイズ、ここから集団という発想、確率音楽が生まれた。」(高橋悠治「音楽おしえ」晶文社1976よりクセナキス)
本国ギリシャでは死刑が確定されたが、パリで活動した。建築家としてコルビジェの建築にたずさわり、西洋音楽の古典的作法と理論、ロマン主義を一切合切廃棄し、科学、数学、確率により、楽譜書き、オーケストラやコンピューターがそれを演奏した。
クセナキスの作品をCDで好んで聴いていた。難しい数学を用いた理論理解することは私には難しい。「音の雲」などといわれたり、密集する音群やグリッサンド(音のピッチを上下しながら滑らす奏法)を多用する。人為を排した自然科学を表す音の運動を聴き、音楽表現に対する概念じたいが、根底からくつがえされるようだった。私のような世代にとっては、インダストリアルノイズミュージックや、非音楽を指向する音楽はよく知っていたが、クセナキスの音はそれらとは違って、なぜか「音楽」そのものように思えた。
初めて生で聴く興奮、日本や世界の同世代の作曲家の作品に指揮者として取り組み、「現代音楽」という人気のない音楽をを紹介しつずけてきた親戚でもある岩城の情熱は誇らしかった。しかし日本のコンサートホールで日本のオーケストラによって演奏されるクセナキスはすこし虚しい絵空事のようにも思えた。たしかに大オーケストラの音はダイナミックだが、もっと別の場所、たとえばできれば屋外でこの音楽体験に浸ってみたいと思ったし、逆にひとりでCDで聴いたり、楽譜を眺めたりしているほうが、強く心に刻まれるものかもしれないとも思った。もしもこの音楽を演奏するのに指揮者がいなかったら、どんな音楽になり、その出来事はどんな意味をもつのだろうか、と客席で想像した。
音楽とは基本的に「一回性」の現象ではあるが、再現を目的としながら、難しくて「弾けない」ことによって価値が高まる。身体感覚や言語表現などの人智を越えて先立つなにがしかを特別な人間が表し、それを享受するのが人間が産み出した芸術や芸能の一面ではある。コンサートのプログラムの一つ、ピアノ協奏曲「シナファイ」は、ときに左右十本の指を独立させるようにして弾かなければならない。ふつうは2段だが、同時に10段以上読まなくてはならない楽譜が使われ、ピアノ史上の難曲といわれていた。正確なことはわかりかねるが、おそらくこの曲の楽譜を再現してあるていど弾くことができるのは、世界でも数人だろう。再現の困難を前提に書くのが「現代音楽」の不思議でもある。そこでは、作曲家がわざわざそれを作った動機、思想という背景から独立して鑑賞することは難しい。直接的に聞き手の情動、情緒と結びつかないことが多い現代芸術とはおうおうにしてそのようなものだろう。間接的で複雑な手はずをふむことが、「知」といわれるものかもしれない。
高かったがわたしも早速クセナキスのコントラバス独奏曲の楽譜「Theraps」をフランスの楽譜屋から船便で取りよせた。大編成の曲にもよく用いられた速いパッセージのトレモロや音程差が激しいグリッサンドがが多く、身体を目一杯使って弾く曲だった。後にこの曲を録音した現代音楽のコントラバスのスペシャリストである溝入敬三はこの曲を「スポーツ現代音楽」と称している。思った通り難しかったので全部弾くのには相当な根気がいると思い少しずつ少しずつ練習してみた。
その頃、イタリアの神秘主義的な作曲家のジャチント・シェルシの曲にも魅力を感じた。みずからの即興演奏を協力者が譜面に書き起こしながら創作するという独自のスタイルは、現代音楽、西洋音楽のアカデミズムの観点からは、「正統」な芸術音楽の創作とは言えないインチキであるという非難や無視もあった。西洋の「作曲家神話」に対するアイロニーにも思えて痛快だった。おなじように、その頃興味をひき、関心を持ったのは、すでに亡くなっていたユン・イサン(尹伊桑)という朝鮮半島出身の作曲家だった。ユン・イサンの曲は苛烈な流動と鎮けさの同居する心や身体に残る「きびしい」音楽だった。ファゴット独奏曲やヴァイオリンとコントラバスのDUO曲の楽譜を手に入れて練習した。
そのような曲をこつこつと練習しそれを少しずつ再現できるようになるのは楽しいことでもあったが、ふとあるときこの曲を演奏する目的がよくわからなくなった。練習して弾けるようになり、それを人前で演奏し、かつお金をいただくということもまた、私がするようなことでもないように思えてきた。その後少しずつ「現代音楽」というものから自然と遠ざかった。むしろ、アメリカのジョン・ケージやイギリスの実験音楽、JAZZの影響の強いヨーロッパの即興音楽へと関心が移行しつつ、それらへの関心もまたいつしか薄れてきた。
クセナキスを弾いた高橋悠治はこのように言っている。
「1950年代の終りから たくさんの音を操り 前もって計画した全体構図を実現する技術 複雑なリズムや跳躍する音を正確に配置する技術からはじめた 最小限の時間で 細分化した断片をつなぎあわせる練習をかさねて 確実なものにしあげる技術 その頃でも 名人芸や超絶技巧ともてはやされる技術の誘惑は避けたいと思っていた 確率空間に点滅するクセナキスの音の霧と そのなかに不規則に打ち込まれる輝く点のイメージは 5分割と6分割を重ねた時間の二重の網で掬い取られ 楽譜に書かれる 音符やリズムの正確さは すでに歪んだ静止画像にすぎない 分析的な技術ではない 別な技術はどこにあるのだろう 漂い移りゆく響きの雲は 軽くほとんど重みのない指先と 響きの余韻が消えた後の 何もない空間の奥行きがなければ 表面的で暴力的なノイズになってしまう 制御できないほどの複雑さと疲れ切ってからだがうごかなくなった時の力がぬけていく感じ その時やっと重力から解放されて 静けさでもうごきでもない何かが現れる そんな瞬間があった
その後の演奏技術は スポーツのように進化してきた 当時できなかったことも いまやたやすくできる人たちが何人もいる そこでかえって失われたこともあるだろう スポーツとなった技術は長続きしない 若い時は力でぶつかってできることは衰えは早く 鍛えたからだはある日突然こわれる
そんな例を時々見かける
クセナキスと最後に会ったのは1997年だった その後のTV番組のために『ヘルマ」を弾いた それからまた年月が経って いままだ弾けるだろうか クセナキスのその後のピアノを使った曲にはない「初心」がある その時の演奏もそうだった 分析的でなく 名人芸でもなく 音に別な音が続くだけの「白い音楽」漂う音の雲の無重力を 毎日1ページずつ習うだけの練習だった というのも後付の思い込みかもしれない
」(水牛のように「ピアノを弾く」http://suigyu.com/noyouni/yuji_takahashi/)
私が参加したドイツの現代音楽プロジェクト「デデコルクト」は、久しぶりに自ら望んで、「現代音楽」や指揮のある西洋音楽のオーケストラで演奏する機会だった。もともとオーケストラはヨーロッパのものであるし、「現代音楽」というものも、ある意味特別なものでも、新しいものでもなく、彼らの伝統や表現としては、自然なようなものだと感じた。オーケストラの面々も誇りをもって現代曲を演奏するし、日本とは異なりそこに特権意識のようなものも感じられないのだ。それがあたりまえのことだからだろう。それはなんだか嬉しかったし、生きている「現代音楽」を体験できた爽快さもあった。まったくそれらとは別種の中央アジアの伝統音楽が対置されていたから、余計にはっきりとそれを感じることができたのかもしれない。
私にとって、現代音楽や西洋古典音楽の楽譜を再現することは、人生の糧となる、いわば身体を使った「読書」のような体験であり、わざわざそれを発表するものでもなく、またそのような技術もない。ただこのような曲を身体を使って練習したり、取り組み、他者の価値観に向かい合ったことは、自身の生や創作になにがしかをもたらしてくれたようにも思う。
2019年に音楽詩劇研究所の「さんしょうだゆう」韓国公演を終えた翌年、新型感染症による自粛生活で、ひさしぶりにゆっくり本を読む機会があった。書棚にあった韓国の作曲家ユン・イサンの生前の自叙伝的インタビュー「傷ついた龍」(未来社)をなんとなく手に取り、あらためて読んでみた。
ユン・イサンは1917年、王朝時代の官僚である旧両班の父と農家出身の母との間に、東海岸釜山よりやや南方の慶尚南道の統営(トンヨン)で生まれた。戦前日本の大学で音楽を学んだが民族独立運動ヘの参加により投獄され、韓国に戻り、逮捕の難を逃れつつ逃亡生活を送る渦中に終戦を迎える。日本より帰還した孤児の救援活動、楽士、作曲、小学校教師など行うが、やがて朝鮮戦争が勃発して祖国は分断される。正式に西洋音楽、十二音音楽などの現代音楽を修めるためにフランス留学し、後にドイツを拠点にする。貧困生活のなか徐々に作曲家として認知されてゆくが、朴正煕政権下のKCIA(大韓民国中央情報部)に、東ベルリンでの北朝鮮出身者との接触などを通じ、スパイ容疑を受けソウルに送還され、死刑宣告を受ける。カラヤンやストラヴィンスキー、シュトックハウゼンら各国の音楽家が解放を請願した。その結果、政権が対外的な体面を取り繕ったために死刑、終身刑はソウルで逃れるが拷問や、獄中生活を強いられ、ドイツに帰国する(すでに市民権はドイツだった)。以後、生前北朝鮮には招かれたが、韓国の地を踏むことは生涯出来なかった。死の前年に韓国で尹伊桑音楽祭が開催されたが健康悪化、日本での金大中拉致事件が重なり叶わなかった。
幼少の頃に聴いた農村の女のシャーマンの声、寺のお経や打楽器の音色、リズム、大道芸の合奏の音の重なり、漁夫の歌、全羅南道の民謡、田んぼの蛙の合唱、そのような原風景の中にある音が、ドイツの監獄の中にいても消え去ることはなく、頭や身体に鳴り響き続けたそれらの音を現代の西洋音楽の音に置きかえたのだと作家ルイーゼ・リンザーとの対話による自叙伝「傷ついた龍」で自身が語っている。急進的な実験音楽の風潮とは距離を置き、十二音技法に基づきながら、朝鮮半島、中国、東アジアの音楽技法の西洋的な流線的な音の動態、和声、対位法ではなく、一音(主音)を繋いだり、束として収束させる独自の音楽技法を確立させた。それらは、老荘思想、道教、仏教、シャーマニズム、あるいは儒教的な精神が楽想のベースになっている。それらの宗教、信仰の感覚は、たとえばキリスト教のような一宗教への信仰心として音楽のなかに告白されるのではなく、つねにそれらが分ちがたく混在している、実生活に根ざした感覚であるといえるのかもしれない。
ユン・イサンは自らの音楽の創作と政治活動は別のことであり、政治活動も止め、晩年は音楽も書かず、故郷に帰り、海で釣をしながら自らの中だけで「音楽」を産み出しつずけたいと言っていた。それは叶わなかった。ユン・イサンが幼少の頃きいた地域のフォークロアや韓国の伝統音楽や、牧歌的なサウンドスケープの哀しみやダイナミズムは戦争や被差別、拘束の哀しみとは別種のものだ。しかし、朝鮮の伝統音楽的のエネルギッシュで流動体的な音色と旋律をもつユン・イサンの旋律からは、20世紀、戦争の世紀の最前線に飛び込まざるを得なかった哀しみが通底する。
読みながら、「現代音楽」とはなにか、もう考えることもなかった問いを、自ら立ててみた。様々な答え方があるだろうが、ひとつの答えとして、二つの世界大戦期周辺において当事者的だった「芸術家」の体験そのもの、真摯な問題意識や思想、救済、政治や社会に対する前衛的態度(新しい方法の発見や実験)、反省、あるいはそれらの強い影響下にある後世の創作をさす、という言い方も出来るかもしれない。
ユン・イサンは偉大な「現代音楽」の作曲家だから、もちろん後世にも継がれてゆくだろう。ユン・イサンの器楽独奏曲のいくつかは、日本の音大でも大学院あたりの試験曲となり、コンサートでは自らの技術の蓄積を示すレパートリーの一曲として加わることもある。いったい何を「試験」し、聴かせるというのだろうか。半世紀ほど前にユン・イサンがソウルの獄中で書いたという作品も、インターネットで手に入れることができる。わたしも早速ダウンロードした。ユン・イサンの苛烈な生も時代も、作品もわたしには遠いものかもしれない。記録、情報だけが残り、そこにある大切なものは忘れられてゆく。
2020年春、新型感染ウィルスで仕事がなくなり、部屋の中で楽譜屋コンピューターに向かい合いながら、韓国の宮廷音楽の歌手ジ・ミナの歌や「沈清歌」の言葉から作品をつくっている。そんなとき、書棚の奥からユン・イサンの本をみつけた。私が韓国で上演した「さんしょうだゆう」に繋げた、パンソリ「沈清歌」を素材にしたオペラを ミュンヘンオリンピック(1972)で上演されたことも知った。その音源は、インターネットの中に、みつけることができなかった。亡き作曲家が遺したものから学ぶものがある、と思った。
9 狂乱の宴 in リヒテンシュタイン公国

楽器をセットアップするために、メンバーより1日早めにリヒテンシュタイン公国に到着せねばならなかった。ベルリンから深夜バスで一人、ミュンヘンを経由しオー ストリアの小さな街で降りた。そこで中央アジアやアゼルバイジャンの演奏家のためのロシア語通訳などのアテンド役のミーシャさんが車で迎えに来ることになっている。初対面の人物と、二人だけで数時間共にするのかと、しかも英語でとなるとさらに気が重かった。しかし出会ってみると、同年代の気さくな優男で、車の中でぽつぽつといろいろと話してくれた。15才までヴォルガ川流域のロシアのタタールスタンで育ったそうだ。
ヴォルガ・ドイツ人とは、帝政ロシア時代18世紀初頭にピョートル大帝が農地耕作のため誘致したドイツ人のことをさす。その後エカチェリーナ2世はドイツのプロイセン人であったため、積極的にドイツ人を誘致しプロテスタントプロテスタントや貧困層が移植したという。1917年のロシア革命後、民族政策によりヴォルガの地に「ヴォルガ・ドイツ人自治ソヴィエト社会主義共和国」が築られたが、第二次世界大戦において独ソ戦が展開されるにおよび、共和国は廃止され、スターリンによりドイツ人スパイの嫌疑によりカザフスタンへと強制追放させられた。農業不毛の乾いた大地で集団農場の耕作に従事した。その後解放され、ソ連、社会主義が崩壊し、ロシアやドイツへの帰還が進んだ。大量移民を抑制したいドイツ政府により、ロシアでの自治共和国の復活が提言されたが実現しなかった。というような歴史も、とくにこのとき知っていたわけではなく、だいぶ後になって調べて知ったことではある。
「ヴォルガ・ドイツ人」の末裔だ。ロシア地域に残るヴォルガ・ドイツ人はすでにロシア人との同化が進んでいる。ペレストロイカ時代から知られ20世紀のロシアを代表する作曲家とされるアルフレッド・シュニトケはユダヤ系のヴォルガ・ドイツ人として知られている。
ミーシャが生まれ育ったロシアのタタールというと、ドイツの現代美術のヨーゼフ・ボイスの逸話が思い出される。ナチスの青少年組織ヒトラーユーゲントの組織員であったボイスは、独ソ戦に突入した1941年にドイツ空軍に入隊し、クリミア半島に駐留する。1944年3月、ボイスの乗った爆撃機はウクライナ近くのクリミア戦線でソ連軍に撃墜されて墜落した。しかし、当時クリミアにいた遊牧民のタタールの部族に機体から救出され、体温が下がらないようにするため傷口には脂肪を塗られ、フェルトにくるまれるなど手厚い看護を受けて、蘇生したという。国土をもたないタタール人の看護によってボイスは奇跡的に戦争を生き延びることになったことを繰り返し語り、のちの創作の重要なモチーフになっている。しかしクリミアには当時、タタールの集落は存在しなかったので このタタールの話は作り話しとされている。
日暮れ前に、リヒテンシュタインの首都ファドゥーツに到着。この小さな公国の面積は小豆島と同じくらいだ。アルペンの山々に囲まれた田園風景の中に古城を有する、小さくて長閑な街だ。ホテルから10分程の劇場に数日間通ったが、山に囲まれ、野原や小川の小道を抜け劇場に通うのが新鮮だった。保守的なお金持ちが暮らし、物価は異様に高い。ここで上演する現実感は薄い。入り組んだ人種問題が扱われている前衛的な響きと伝統音楽が混沌とするこの作品を見て、この地の客は何を感じたのだろう。ホールは満員だが、途中で席を立つ率も一番多かった。いっぽう劇場やスタッフは充実しており、整った環境だった。
そういえば、車で到着した夜、調達した楽器の調整を終え、部屋に戻ろうとすると、ミーシャが近寄ってきて隣にある部屋を指差す。ついてゆくと、そこにはピアノが置いてある。彼はピアノ椅子に腰掛け、即興でピアノを弾きはじめ、しばらくするとはにかんだ表情でちょっとだけセッションしようという。リハーサル室に戻ってにコントラバスをとりにいき演奏した。彼のメロディやハーモニーにはなんともいえぬ愁いがあり、不思議な安らぎを覚えた。10分ほど共演し、彼が丁寧にお礼を述べた。私は、時間が空いたら、またここで一緒に演奏しようよ、と提案し、彼も嬉しそうにうなづいた。翌日からは、オーケストラや、彼が通訳をつとめる中央アジアの伝統楽器奏者たちが合流し、慌ただしく、彼ともすれ違いざまに顔を合わせたときに挨拶する程度だった。あの短いセッションはなぜかよく思い出す一コマだ。
ベルリンの稽古で長く時間をともにしてきたカルテットのメンバーはとは、どこかで食事をしたり呑みに行ったりなどしたことがなかった。そういう習慣はあまりないようで、稽古が終わるとみな、すぐに自宅へ帰ったり、次の用事に出向く。しかしツアー先では、一緒にカフェやバーで過ごす機会でもあった。オーケストラも一緒に滞在したこの地では、最終公演の後、ホテルの誰かの一室に集まって、打ち上げパーティーをすることになった。顔を出すと、端正な表情で黙々と難曲をひきこなしてきたオケのメンバーたちが、部屋に入りきれないくらい集まり、クラブミュージックをガンガンにかけた狂乱の宴、馬鹿騒の渦中だった。これまでで体験したことのない、常軌を逸した宴だった。こいう狂乱もまたヨーロッパの、あるいはドイツ人の?狂気の一つだと思った。オン/オフが激しいというのか。そこに混じる他なく、ビールやワインを飲み続けた。起きたら知らないベッドだった。頭にディップをべたべたに塗り固められた記憶があるが、そのまままま泥酔したようだ。シュトッツガルドへ向かう車の出発時間がせまっており、部屋に戻りいそいで荷物をまとめた。
10 シュトッツガルド 「魔の山」

リヒテンシュタインからシュトッツガルドに向かう車は、南ドイツロマンス街道と呼ばれるらしい美しい風景のなかをを通る。優雅なドライブ気分の予定でいたが、二日酔いの私はずっとディップで針金のようにかたくなった髪の毛のまま後部座席で眠り続けた。オーケストラや中央アジアの伝統音楽家から離れ、カルテットと打楽器のマリーア・シュナイダーとドイツのソリスト、私の5人だけ。運転はリーダーのマーク・シナン。心地の悪い眠りから覚めると、もう味気ない都市の風景のシュトッツガルドに着いていた。ベンツの街で富裕層が多いときいが、たしかに落ち着いた街という印象。
翌日は録音。西ドイツ時代から多くの現代音楽作品の演奏や録音を残した功績でも知られる名門南ドイツ放送局(SRW)の巨大なスタジオは静かな森の中の巨大な建物。現代曲、即興、ソロの録音。集中。はじめての楽器、難しい曲なのでつかれた。いくつか予定されていた他の場所での公演は準備が整わず延期されていたので、今回の旅のミッションはこれにて終了。
放送局からホテルへ向かうタクシーのカーラジオからジョン・レノンの「イマジン」が流れて、メンバー各々呑気に口ずさんだりリズムをとったりしていた。海外のアーチストとの仕事の時は言葉のコミュンケーションについていけず、いろいろと物事の段取りが理解しきれず、状況に流され、そこに孤独も気楽さも同時に感じていたが、絵空のようでもあるこの歌詞とジョンのナイーブな声が、西陽の射し込む車の中でずいぶん沁みた。
その夜はヴォーカルのクルジチの友達が出演しているという演劇をみんなで観にいった。公共の劇場による、トーマス・マンの「魔の山」(1924)の初演。
死に限りなく近い結核サナトリウム(療養所)のなかで、ヨーロッパの歴史と哲学の対話、第一次大戦前の「ドイツ民族」のあり方について療養者の会話によって進行する。その一人、主人公のハンス・カストルプが言葉のない超自然世界、雪山の深淵と沈黙の白い世界に没入して行き、快感にひたってゆく文学史上の名場面とされるシーンがある。その恍惚感の中で、主人公を含め、 死に近い患者たちが愛国心から第一次大戦に参加へを決意する。この演劇では、雪の中で「ひたらずに」終わっていた演出だったような気もしたが、決意のシーンの前で舞台は突然幕を閉じた。
愛国心は民族主義として他のユダヤ民族や、ロマや他民族、人種の差別や虐殺に繋がってゆく。「魔の山」はドイツ敗戦後の1926年に完成されたが、トーマス・マン自身も第一次世界大戦前にドイツ民族主義から大戦参加にについて積極的であったようだ
この日の観劇ではそのあたりの機微がどう描かれていたのかまでは、ドイツ語も分らず、小説も未読だった私には分からなかった。二時間超の舞台で、言葉は全く分からず、音楽的な要素もない。以前、ニューヨークでブロードウェイミュージカルに連れられて、立て続けにたくさんみたことがあった。少しは分る英語で歌や音楽があるのに舞台の流れに追いつけず、いつも眠ってしまい、まぁ雰囲気は味わったかな、という感じで終わってしまった。このような残念な経験もあり、読んだことがないドイツ近代文学で最も知られる名作「魔の山」のあらすじと背景だけをパソコンで調べ、人物相関図を押さえノートに整理した。それにしてもドイツで観た舞台はいろいろ考えたり、同じ敗戦国である日本と比較したり、想像しながら見いっていたらまったく眠くもならずに楽しんだ。単なる相性だろうか。
1000人ほどを収容できる大きなホールは満席だった。しかしトーマス・マンのドイツらしい観念的な対話はドイツ人にも難しかったようだ。同行のメンバーはよくわからなかったそうで(でも面白かったねぇ、みたいな)、私のにわか理解の説明を、ふうん、なるほどと関心しつつも、聞き流していた。
11 ハインツ・ホリガーとセルビアの狂乱

「魔の山」観劇後、出演していた友人と会うクルジチと別れ、フルートのフライドル、打楽器のマリーヤ・シュナイダーとホテルへの道を迷いながら手頃な値段のレストランを探していたが見つからずに途方に暮れていると、シュナイダーのところに友達から連絡が入り、われわれは「食べ物と酒にありつけそうだ」という情報を掴んだ。すぐ近くで、今日録音した南ドイツ放送局の交響楽団のコンサートがあり、その打ち上げパーティーを劇場の楽屋でやっているとのこと。そこに紛れ込んで食べ物にありつこうというわけだ。ベルリンからシュツッツガルドはずいぶん遠くはなれているが、公演をしている友達がいたり、彼らアーチストはそういう風につながっている。
「そろそろアンコールの時間じゃないかな」などと、楽屋口の外の裏庭で待機していたが、扉の中を覗いててみるとすでに、その日の公演で自作曲の指揮をしていた、スイスの作曲家、オーボエ奏者の老ハインツ・ホリガーがいた。ピエール・ブレーズ(の後継者ともいえる、20世紀を代表する前衛音楽の巨人であり、オーボエという楽器の演奏領域を拡張した名演奏家だ。かつてCDでよく聴いたのでびっくり。武満徹にも彼に捧げた「ディスタンス(オーボエと笙のための)」という作品がある。
関係者の顔をして巨匠ホリガーに「ブンバダー、おつかれさまっ」と握手した。日本人とおぼしき女性のオーケストラメンバーもいたが、気まずいので何となく目も合わせず。われわれ三人は、まるで銀座のアートギャラリーとかで話しをきく、個展初日の「パーティー荒らし」よろしく、どさくさにまぎれて酒も含めてただで飲み食いした。ホリガーが催した祝賀ではないだろうが、ホリガー様、ごちそうさまでした。

翌日たまたまホテルの下の喫煙所であったので、そのままクルジチと二人で30分ほどの短い間街をふらついた。セルビア出身の彼女は、ベルリンに居を移して長いが、女優、歌手、ダンサーとして幅広く活躍している。次のプロジェクトは南アメリカの振付家とのパフォーマンス作品とのことだった。以前即興のコンサートで日本で共演したことのあるSAX奏者とバンドもやっている。パーティーでの前夜の蛮行を打ち明けると、それは「パラシューター」というのだと教えてくれた。パラシュートで空から降りたってなんの脈絡無く突如としてあらわれて、場を荒らしてずらかる人々の喩えだと笑いながら言った。
そしてセルビア時代の話をしてくれた。セルビアのユーゴスラヴィア時代の80年代後半の話で、某かの家で「フリーパーティー」が行われる旨のポスターが街中に貼られるのだそうだが、それは嘘なのだそうだ。パーティーには誰ともわからない大勢の若者が見知らぬ家に集まり、カオスとなり、家はめちゃめちゃに破壊される。もちろんその家の人たちは自分の家でパーティーが開かれるなどということは知りらない。指導者チトーの死後ユーゴスラビアの社会主義体制が崩壊に向かうなかで、街そのものが混乱していた時期だそうだ。バルカン半島というと、のエミール・クストリッツァ監督の映画「アンダーグラウンド」(1995)などの狂乱のカオスを思い浮かべてしまうが、まさにゴラン・ブレゴヴィッチの音楽が聴こえてきそうな光景だ。
ちょうど一年前の秋、下北沢の駅で受けた一本の電話から始まったこのプロジェクト。その冬からベルリンに渡り2月にドレスデン、ベルリンでの初演。そしてあれから約一年後、リヒテンシュタインでの再演。マークやソリストの仲間、オーケストラの面々、中央アジアやコーカサスの伝統楽器奏者たち、そしてトルコのアイディン・テキャルとの再会、この作品に参加し新しい音楽と出会い、創作に集中することができた一年だった。
それらの喧騒の波が去って、マーク・シナンとソリストたちだけで訪れたシュトッツガルドの街はそれだけで残り火のような淋しさを覚える。安定感のある中都市シュトッツガルドの無機的な雰囲気がさらにそれを後押しする。芸術監督としていつも忙しそうにかけまわっている、一つ違いで同年代のシナンとはゆっくり二人で話したことはなかった。最後の晩に彼の誘いで二人だけで、ドイツ料理屋でビールを飲みながら食事した。そのあと回転すし屋に行き、甘すぎる日本酒の熱燗も馳走になった。再演は予定されていたがまだ具体的に決まっていなかったので、最後のお礼にご馳走してくれたのかな、とも思い、少し淋しくもあった。今回プロジェクトをふりかえったり、未来を語ったり、ぎこちない英語でそれなりに深い話もしていたはずだが、そんな淋しい感情のほうが勝っていたのか、話した内容をよく思い出すことができない。
翌朝メンバーは車や電車でベルリンに帰ったが、私は航空便の都合で一日空けての出発だったので一人ホテルに残った。街中に出かける気は起こらず、帰国後のことを考えたりしながらホテルの部屋に居るのも落ち着かず、うたたねし、冷めたピザをほうばり、またうたたねし、日暮れ時近くになってようやく、さまようように歩行者天国の目抜き通りを歩く。デパートの地下で土産を買い、一人でバーやレストランに入る余力もなく、スーパーでビールと、またピザを買って部屋で横になる。ドイツ最後の一日を実に空虚に過ごす。
リヒテンシュタインで別れ、もうトルコに帰国している振付家のテキャルも、わたしとはまた別の意味で孤独だったと思う。わたしと違い英語が堪能でコミュニケーションに問題はないが、二年かけて創作した私と二人だけのプロジェクトとは異なり、スタッフも含めると100人近い人間が動員されるこの慌ただしい大きなプロジェクトの中では、彼女の思うようには事が進まない。振付家として彼女の特色が十全に活かせたとはいえず、不完全燃焼感があったと思う。
オーケストラや中央アジアの演奏家が合流する以前は、私とテキャルだけがホテル暮らしだった。ときどき、暗いベルリン郊外の街を一緒に歩いて夕食に出かけた。疲労や英語でのコミュニケーションのストレスも重なり、それぞれのエゴや孤独をしまいきれず、口論になったり、不平不満をもらしあったり。大事な話しもあったと思うが、なにを話したか、やはりあまり思い出せない。そして帰りはたいていお互い無言のまま、味気なく静まり返る旧東独の夜の街を、道を見失いながらホテルに辿り着く。
それでもこうのようなプロジェクトのホテル暮らしの日々は、ただパフォーマンスのみに集中すればよいので気楽なものだ。稽古が終われば、東京での生活に比べれば一人の時間は長い。仕事ではあるがそこに「生活」はない。料理をつくらず、ゴミ捨てもせず、銀行に行ったり、誰かとあって酒を飲んだり、(常設の稽古場に置いてかえるので)コントラバスを電車で運んだり、そんなことがほとんどないのだ。言葉の問題もあり、仕事以外ではたいして人と話さない。生活と言えば時々財布の中身を気にするくらいなものだが、とくに金も使わない。だから、2011年よりイスタンブールで始まったアイディン・テキャルとの仕事と、2013〜2015のあいだにベルリンを中心に行われたこの「Dede Korkt(デデコルクト)」の期間は、個人的には、よくひとりで歩き、物思いに耽った時期であったともいえる。このドイツでのプロジェクトへの誘いの電話があった前日に、突然別れることになった妻も、演劇の公演のためにちょうどスイスやフランスに滞在し、帰国してもひとりだった。そういう時間がはからずも与えられた。そんなころの散歩や物思い、慌ただしいが創作に専念できる安堵とともにある、贅沢で少し孤独な日々を、あとになって振り返りながらながらこうして書いみたというわけである。いずれ、創作も含めたこの一年のドイツでの経験が、のちのユーラシアンオペラの創作の大きなきっかけとなった。

Dresdner Sinfoniker – Conductor: Fabián Panisello Soloists:
Jelena Kuljić, Voice
Jun Kawasaki, Double Bass
Marc Sinan, Guitar/E-Guitar
Sascha Friedl, Flute/Subcontrabass flute Ulzhan Baibussynova, Zhirau
Mehri Asadullayeva, Kamancheh
Askar Soltangazin, Dombra
Toir Kuziyev, Sato Production: Markus Rindt & Marc Sinan
Artistic direction: Marc Sinan
Choreography: Aydin Teker Technical direction and Light Design: Albrecht Leu
Video and stage: Isabel Robson Sound: Volker Greve, Silvio Naumann
Dramaturgy and text: Holger Kuhla Co-direction: Cornelia Just Assistant director: Mizgin Bilmen Costume: Cleo Niemeyer Costume assistant: Marcella Sewella http://dedekorkut.eu/news/
★「これは音楽なのだろうか....」 トルコの振付家とのイスタンブールの日々 2011・2012

・「db-Ⅱ-bass - 音、身体、楽器」
この本では、海外でのコラボレーションを軸に創作してきた音楽詩劇研究所のユーラシアンオペラプロジェクトを中心に述べてきた。そこは、各地のフォークロアと関わりを深めることを主眼とした。しかし私自身の創作は以前から、そうだったのではない。むしろ民族性やジャンル、伝統、性差などの属性にとらわれない、ニュートラルな表現を求めてきた。その根本は現在も変わらない。トルコの振付家、アイディン・テキャルとのイスタンブールや東京での二年間の作業は内容的に、そのような作業を象徴する仕事だった。トルコや日本の文化や伝統とは直接的に関わりを持たず、民族的な属性どころか、自分が音楽家であることすらも、意味を持たないような創作だった。
しかしその後彼女と共に招かれて参加した、他章でもふれてきたドイツの現代音楽プロジェクトは民族の移動がテーマだった。この作品をきっかけに、ユーラシアンオペラというビジョンをおぼろげに描き始めた。私が深く関わったもうひとりの舞踊家について述べる「最終章」への橋渡しとして、アイディン・テキャルとの二つの作業を振り返りながら紹介したい。まずはじめに、彼女と私の「db-Ⅱ-bass - 音、身体、楽器」のウェブサイトで紹介された、作品概要を引用する。
「db-Ⅱbass - 音、身体、楽器」は、歴史的に築かれてきた身体と楽器の関係を再検証しそれぞれの可能性を相互に拡張させることで、あらたな創造の領域を構築しようとする試みで、楽器の拡張としての身体に強い関心を持つトルコのコレオグラファー、アイディン・テキャルと、音楽の宿る源泉を身体に求めたコントラバス奏者、河崎純の共同作業です。プロジェクトは2011年にスタートし、以来、テキャルと河崎は、東京とイスタンブールで楽器と身体の関係を見直し、より自由でダイナミ ックな関係を再構築する作業を続けてきました。このプロセスはまた、音はそもそもいかにして生まれてくるのかの発見のプロセスでもありました。1年間の作業を経 て、作品は2012年10月にトルコ・イスタンブールの「アクバンク・ジャズ・フェスティバル」(トルコ最大の国際ジャズフェスティバル)の一環として初演されました。」(db-ll-bass -音、身体、楽器 ホームページより)
テキャルのプロフィールに次のような言葉がある。
「私と作業するダンサーは非常に忍耐強くなければならない。私は彼らを殺してしまうし、自分自身も殺してしまう」




・音楽を奪われた音楽家
イスタンブールでの彼女との日々は、ぶつかりあいや反発のくり返しだった。演奏家である私に対してテキャルが行う振付けは、たしかに動きは美しいが音楽がない。反対に私が音楽を優先して演奏しやすいような体勢をつくると、「ダンス」としてはつまらない。彼女が「これは、美しい!」と思う動きはどれも、コントラバスを弾くことが困難というより弾けない、楽器を弾くには不自然すぎる動きばかりで、弦にまともに触れることもままならない。
さて、それでは彼女が提案する動きから、どのように音楽がうみだすことができるか。テキャルは、「音を出そうと思う前に、身体の声を聴くように」という。それを阻害する要因を取り除くために、まず身体の構造に注視するのが彼女の創作方法だ。人間の「骨格」は他の多くの動物と同じくシンメトリーな「構造」だ。構造にまとわりついた肉や感情、精神、習慣(癖)をとりはらえば、民族、年齢、経験、強度の違いはあっても、骨格構造はほぼ人類に等しい。まず表現に先立ち、そのような構造を基礎において優先しながら創作する。
テキャルがユーモアのある動きを考え、私がたどたどしくそれを試みる。現代舞踊の最前線にたつ彼女は、むろん骨格の整合性を基にした「健常な身体」から生まれる表現を礼賛するだけではない。もちろん私もダンサーのように身体が動かなし、彼女にはプロレスラーやダンサーでもパフォーマーでもない自身の母親に振り付けた作品もある。その振り付けの根幹においては、民族性や性差、あるいは修練されたプロフェッショナルかそうでないかも前提にはならない。
世界中の多くの楽器も人体同様にシンメトリーな形状をもつが、楽器とそれを弾く身体との関係は基本的にシンメトリーとはいえない。楽器を演奏する身体はどこかのパートには必ず過重に負荷をかけているので、そのような意味では常に歪んでいる。
イスタンブールの中心部にある総合病院の最上階にある彼女のスタジオに通い、今日は鎖骨、明日は踝(くるぶし)、明後日は背骨というように人体模型とそれぞれの骨の仕組みについてレクチャーを受けながら、実際にそれぞれの部位を起点にしながら身体を動かし、それから楽器と私の身体の関係を模索し、振り付け(あるいは音楽)をつくってゆく。
野良猫の多いこの街で、つねに彼らのエレガントな身のこなしに嫉妬する日々だった。そういえば実際にこのプロジェクトのあとのドイツでも、初めて訪れたベルリンで、到着したその翌朝、動物の身体や動きを観察しに動物園に行くことを彼女から課された。晩秋の冷たい小雨が降る中、自意識を持つ人間という生き物が、そんな無駄のない美しい動きを作れるはずがない、と途方に暮れながら、一日中動物たちの動きを追った。

・音のない音楽
彼女の求めるダンスは、感情や意図が入り込むことを容易に許さない、具体的で機能的な神秘にも思えた。しかし私のなかの「音楽家」としてのアイディンティティ、感情は揺さぶられ続けた。これは音楽なのだろうか....ましてわたしは「ダンサー」ではない。ダンス作品というのもおこがましい。楽器は踊りを演出するための「小道具」でもない。身体との関係から音がいかに生まれ、それを「音楽」としてとらえることができるか。それが可能になって初めて二人のコラボレーションがようやく成立する。だがそもそもそんなことをする必要があるのだろうか。身体を知り、肉体のトレーニングを行うことじたいは、とても貴重な得難い経験なのは間違いないのだが、それを作品として上演するにはさまざまな逡巡がある。
彼女は非常にクリアな思考の持ち主で、教育者としても大学の学部長でもあり、飲み込みの悪い私に対して教育者としても粘り強く懇切丁寧に説明した、ときおりコントラバスをかかえて動きを示してくれる。
楽器を「ふつう」に弾くことができない彼女は、そもそも楽器を「演奏」しようと思っていないからほとんど無音。彼女の身体と弓が弦に触れて、ときおり音が聴こえた。それは無音や沈黙を、際立たせるための音だ。そしてその沈黙の中に無数の音楽が潜在する。わたしは楽器を「ふつうに弾くことができる(ふつうにしか弾けない)」音楽家だ。さまざまな音楽的意図が先立って、彼女のように音楽を奏でることはできない。
「音楽として」、「ダンス作品として」成立させたい、と、つい色気をだそうとしてしまうこともあった。でも、テキャルの身体と一体化したコントラバスから溢れた音をきいて、「音楽」でも「ダンス」でもない、何とも名付けることができないことをしているのだ、と思うようになった。あるいは、身体と楽器との「関係」がそのまま音楽やダンスでありたい、と考えるようになった。
それでも実際にそれを体現するにはさまざまな葛藤が続いた。2012年のイスタンブール、2013年春に横浜、東京で行われた本番公演もまだ、作品として自信を持って人前で発表できる確信はなかった。どうにでもなれという思いで無心状態を「つくり」、一人、コントラバスのほか何もない舞台に飛び込んでゆくよりなかった。思った通り、ダンサーや音楽家からは評判があまり芳しくなく、落ち込んだ。でもそうでない方からは、なんとなく不思議なものをみた、というような感想をいただくことが多く、嬉しかった。

◆アイディン・テキャル
トルコのコレオグラファー。同国コンテンポラリーダンスのパイオニア的存在として内外に知られる。 アンカラ国立コンセルバトリーでバレエを学び、卒業後、アンカラ国立オペラ・バレエ団でダンサーとして活動。1976年に退団し、ロンドン、次いでニューヨークに渡 り、ニューヨーク大学ティッシュ・スクール・オブ・ジ・アーツで芸術学士号と芸術修士号を取得。1982年に帰国し、イスタンブールのミマールシナン大学でモダンダンスを教え始める。 サイトスペシフィックな作品の創作に打ちこんだ時期を経て、1997年に、自分自身の身体を知って有効な動きを繰り返しトレーニングすることで身体の可能性を高める、フェルデンクライスメソッドに遭遇。身体構成理論を学び、ダンサーたちとの長期にわたる細かい作業を通して身体の自由と独創的な動きを導くという、ミニマル的なスタイルを築く。そうした独自の方法論による作品は、ヨーロッパを中心に世界各地のフェスティバルで上演されている。「aKabi」(2005年初演)では、高さ35センチもの不安定な履物をつけることで身体の自由を奪われたダンサーの極限のバランスが生み出す美しさが話題となり「harS」(2008年初演)では、ダンサーと、ダンサーの身体の拡張としてのハープが創り出す共生空間が高い評価を得た。最新の作品「三つの位相」(2013年初演)では、二人のダンサーが平台に乗り、その位相が変化することで、身体をコントロールする2人から、予期しえぬ多層的な関係ーふたつの身体の関係、身体と台の空間的関係、二人の思考の関係、さらには2人の女性そのものの関係があぶり出された。 ミマールシナン大学の舞台芸術学部ディレクター、モダンダンス学科長を兼任。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
